時価総額とGDP(2005年11月23日)
戦後の日本経済を支えた功労者の中山素平さんが亡くなられたそうで…長い間ご苦労様でした。更に自民党の結成50周年とか…そこで今日は少し日本の現状について、考えて見たいと思っています。日本は未曾有の構造改革に取り組んでいます。この姿勢を評価して、海外投資家が日本に投資をしているのですが、GDPと株式の時価総額からみると奇妙な構図が見られます。下のグラフを見てください。時価総額に対するGDPの割合を示したものです。
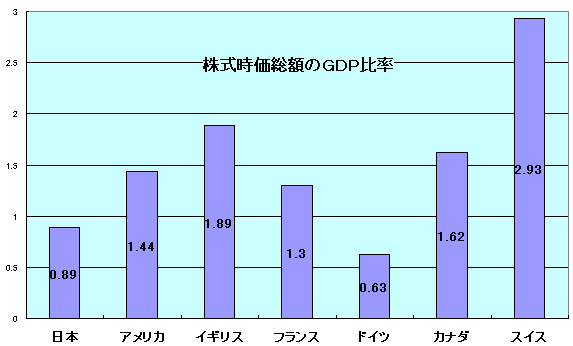
アメリカ・グローバル・スタンダードが世界の統一基準と考えると、日本も積極的に現地生産化を推進し、国際競争のある強い国を創らなくてはなりません。通貨の価値も基準のひとつなのですが、世界の会計基準が統一され、同じ土壌で企業価値を比較することが出来るようになって来ました。アメリカでは株式交換によるM&Aが盛んに行われています。企業が国家を動かす時代に、なっていると言っても過言ではないでしょう。サムソンの原動力の一つは、大量の日本人技術者の確保です。有利な条件で日本の技術者を雇い、技術移転を成し遂げたのです。その成果が現在のサムソンの姿と言えなくもないでしょう。
国力とは…企業を育てることでもあります。長らく、日本では画一化教育が行われ、国民のロボット化教育が行われてきました。良い学校に入り、良い会社に勤めれば、豊かな生活が送られる。ところが現実は、優秀な人材を集めたはずの山一證券は倒産し、大手銀行は企業淘汰されていきました。この15年間ほど、日本人の価値観が大きく変わったことはないでしょう。インターネットが発達し、真の実力が問われるように、情報公開がなされてきました。これまでは、仕組み社会の力が強く、新しい力の前に既得権力が立ち塞がってきたのです。何処か、おかしいと感じていながら、なかなか改善されない現状に、多くの人は挫折感を感じていたのです。しかし、ネット社会のおかげで新しい世代が主権を握る新時代が幕開けしたのです。野村證券とSBIとの逆転は一つの象徴でしょう。現状ではまだ格差はありますが、予断を許しませんね。
何故、日本とドイツは株式の評価が低いのでしょう。私は残念ながらドイツの仕組みを良く知りませんが…。日本とドイツは第二次世界大戦に破れ、戦後復興のために統制経済を強いられました。中山素平氏はGHQに興銀の役割を説いて興銀の存続を獲得したといわれています。内務省を解体し大蔵省を残し、GHQは戦後の日本の復興を考えるわけですが、効率的な資金配分を成し遂げたために、順調な経済発展を成し遂げてきました。池田隼人の「国民所得倍増計画」など代表的な計画でしょう。しかし、その影では自由を奪うのですね。義務教育の推進によって画一化教育が浸透し、学生服、セーラー服に象徴されるように、リクルートスーツでも同じことですが、個人的な動きが抑えられていきます。
明治政府の時代は、村単位で国民の動きを抑えました。村八分と言う言葉がありますからね。核家族化が進むと、今度は会社単位で規制を始めます。今でもNHKの職員が不祥事を起こすと会社名が公開されますね。面白い現象です。個人的な社員の不祥事に、社長が責任を取るのです。いつしか雇用を守るのが経営者の勤めとされ、非効率な内製部門を抱えるようになります。ところが最近では効率化が問われ、外注するようになって来ましたね。派遣社員や請負業などは代表的な例でしょう。人まで部品感覚で扱われる世の中です。
これだけ、資源が上がっているのに、何故、消費者物価指数はなかなか上昇しないのでしょうか? おそらく、日本の改革スピードが物価上昇より勝っているのでしょう。姉歯建築設計のような弊害もありますが、官が支配するより民が作業したほうが効率的で早いのです。安全と効率の問題のバランス感覚が求められますが、経済効率に重点を置いた改革は始まったばかりです。いよいよ役人の本丸に改革の手が伸び始めています。政策失敗の責任を銀行に押し付けたのが不良債権問題です。みずほの一兆円増資は官との決別を民間が告げた出来事なのです。官から民への流れが加速したのが、郵政民営化などの一連の改革です。その為に非効率な無駄な経費がなくなる現象がデフレ圧力なのですね。
日本にとっては、「官の無駄」と言う「のりしろ」の大きな部分があるために、原材料費が上がることは、効率的な状態に置かれている先進国より有利なのです。資源価格高騰は日本の相対的な競争力を高めているのです。ここに、これから投資の要が存在する可能性があります。もう少し補足をしないと、分からない人が多いでしょうか? 従来型の経営スタイルをしている会社が新しい経営者により、改革を促進されると成長スピードが増すのですね。楽天とTBS問題など…その一つか。構造改革投資が大きなリターンを生む可能性がありますね。わが国のGDPは、およそ512兆円で、時価総額は461兆円です。0.90倍ですね。少なくともアメリカ並みに効率化が進むと、時価総額は1.44倍ですから737兆円になります。
アメリカは時価総額を守るために、企業経営者はインテルやマイクロソフトのように自社株買いを実施します。企業の利益は適正規模の現預金のほかに、研究開発費や設備投資資金の除き、配当や自社株買いに、余った利益を当てるのです。わが国の企業は過剰債務のために、長年苦しみましたが、必要以上に借金を返済し、資金が余ってきているのが現状です。株主公約した村田などの会社の株価は、これからドンドン上がるでしょうね。ここにヒントがあります。時価総額経営が、新しいグローバル基準のひとつなのです。松下もそうでしょうし、トヨタもある意味で実施しています。
今日は少しまとまりのない文章ですが、GDPと時価総額の現象を考えて見ました。道路特定財源が一般会計予算に使われる。既得権が排除され、効率的な資金配分が始まるのです。国債30兆円発行の枠をはめ、資金源と断つのです。やがて時間と共に衰退は始まり、内部崩壊するでしょう。村上は通産官僚ですからね。賢い奴は早く転進を図ります。黄金株発行を拒否する東証は、官の要求を断ち、市場経済の促進に努めなければなりません。日本にある資金のパイプの出口を変えるのです。やがて株の儲けを不労所得と蔑む傾向はなくなるでしょう。株で儲ける人を賞賛する時代が新しい時代がやってくるのです。