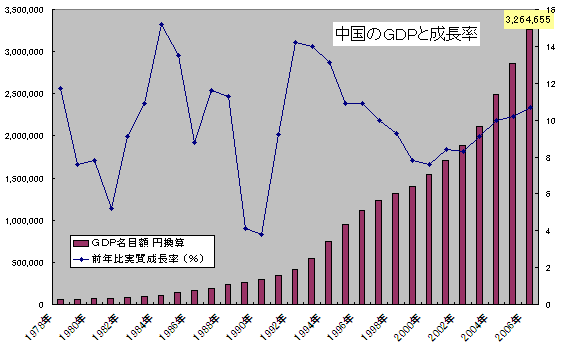外交力と日本(2007年05月03日)
最近の目覚しい中国の躍進振りを見て考えさせられることが多い今日この頃です。毛沢東の独占支配から立ち上がる中国を今日は簡単に調べてみたいと思います。
歴代のトップは毛沢東(主席)、華国鋒(主席)、胡耀邦(主席→総書記)、趙紫陽(総書記)、江沢民(総書記)、胡錦濤(総書記)となっています。
しかし影の実力者、鄧小平はあまりにも有名で現在の中国を建設した第一人者です。大躍進政策(1958年)の失敗により毛沢東が失脚し総書記になっていた鄧小平は国家主席の劉少奇と共に経済の立て直しを図りますが、失脚していた毛沢東が権力を取り戻すために起こした文化大革命(1960年代後半から70年代前半)により、鄧小平は権力を失い農場へ労働者として追いやられ、劉少奇は毛沢東に失脚させられ監獄され殺されます(1969年)。一方、鄧小平も危うい所でしたが、「あれはまだ使える」という毛沢東の意向で完全な抹殺にまでは至らず一命を取りとめたのです。
1973年に周恩来の協力を得て復権した鄧小平は1976年に起こった第一次天安門事件の責任を取らされ失脚したが毛沢東の死亡による後継者争いで華国鋒を支持し再々復権をする。そうして1978年に日中平和友好条約締結を記念して来日して市場主義経済の素晴らしさを知り社会主義市場経済を導入する事になる。中国の躍進はこの時がスタート地点なのだろう。先に豊かになれる条件を整えたところから豊かになり、その影響で他が豊かになればよいという先富論と言うのは1985年頃に公にされたと言いますが、改革開放路線を決めた中国共産党第11期中央委員会第三回全体会議(1978年12月22日)には、既に形はあったのでしょう。
積極的に外国資本を導入し経済改革を進めていき、1980年から経済開放区を設け、開放政策を加速させていきます。1990年には上海の浦東新区の開発を決定し経済発展に繋げます。積極的に外国資本を優遇し資金導入を図り、国が成熟し始めると徐々に優遇処置を撤廃し始めている賢いやり方ですね。2013年には中国のGDPが日本を抜くと言われています。1990年代に入ると中国は積極的にアセアン諸国と友好条約を結んでいます。しかし日本はこの4日にブルネイでようやくEPA(経済連携協定)を結ぶのです。
分かりますかね? この意味が…日本の外交力がないというか…農業優先のために国内の権力争いをしているために世界競争から遅れている現実があるのをマスコミは報じようとしませんね。官が自分達の為に情報をコントロールしているから、世論は真実を知らないのです。中国のGDPが326兆円になった現実をどれくらいの人が知っているのでしょう。日本には政策のビジョンがないし、知らないから経営者も保身に走るのです。特にマスコミですね。悪の根源は…だからソフトバンクを応援し、ライブドアを擁護し、楽天を支持しているのですが…どうなるのかな?この国は…