« ケネディクス2 | 最新の記事 | 軍艦ビル売却の意味 »
バーナンキの金融政策(2013年09月22日)
今日はもう少し、今回のFRBの判断について考えてみようかと思います。メディアの論調は今回のFRBの判断が間違っており、既に景気は回復し緩和を縮小させるべきだったと言う見方のようです。しかし5月の時点ではバーナンキの発言に市場は大きく揺れたのですね。カタルは、当初、バーナンキの発言に対し好感を抱いていました。実体経済回復の背景があるからこそ、緩和を縮小できる。故に株価が大きく下がることはないと言う考え方を早くから示していました。しかし現実は、このバーナンキ発言により、新興国の通貨安まで波及し、新興国から先進国への資金回帰が進みました。欧米の景気エンジン規模に並ぶ、新興国の景気に陰りが見えてきており、この点が注目されましたね。この点を克服しての今回の株高で、この資金回収への準備が整ったかに見えた段階で、あえてバーナンキは、市場の期待に応えずに、今度は緩和縮小を見送りました。この行動が、市場を愚弄しているとして…金曜日は嫌気され、株式が下がったと解説されています。
しかし市場は本当に正しいのかどうか…。そもそもサマーズ氏に代表されるように、量的緩和そのものが、経済回復にたいして役立っていないと言う考え方もあるようです。一方、ブラード総裁のようにインフレ指標が低調なのに、慌てて緩和を縮小することはないとする意見もあります。考えてみると微妙なさじ加減です。そもそも金融規制の実施が、未だに議論されており揉めていますね。一般論として、金融機関が博打をして成功すれば自己の利益として処理するのに、失敗したらその始末を税金に押し付けるとのはおかしいと言う判断が金融規制の背景にあります。カタルが米国金融の立ち直りの目安として見ているのは、政府系住宅金融機関(GSE)の連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ) と連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック) の回復に焦点を据えています。政府の管理下にあるという事ですが、両者の株式は依然、上場が維持されており売買が可能になっています。今年、公的資金を返済し政府管理が、近々、外されると言う思惑が生まれ株価が急騰したのは、5月末の話しでした。丁度、バーナンキが緩和縮小を示唆した時と一致しますね。
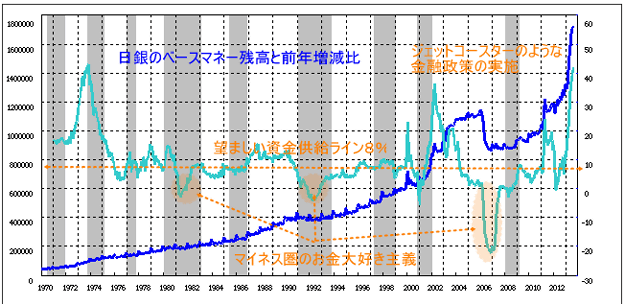
日本のケースを、ここでもう一度振り返ってみましょう。このグラフは日銀のベースマネーの残高推移と前年度比の動きを示したものです。カタルが問題にしているのは前年度比の増減比率の問題です。ベースマネーがマネーサプライに影響を与えますから、基本的に、ベースマネーのさじ加減が、世の中の通貨量をある程度コントロールしていると考えられます。(ただ近年はこの乗数係数は落ちています。)しかしようやく伸び始めた2003年から2006年に掛け、日銀は先行して資金を絞っています。残高ペースは伸びていますが、水色の前年比較ペースで見ると、良く動きが分かります。金融危機の影響もあったのでしょうが、その前に既に株式が下がる兆候があったのです。2004年4月から日銀は資金供給を絞りはじめ、6月からは5%以下にしています。そうして2006年3月にはマイナス圏にするのです。此処で考えて欲しいのは、経済成長率3%を求めるのなら、単純に考えて、それ以上の資金供給をしなくてはならない筈です。それにも拘らず、ただ増やし過ぎたからという理由だけで、日銀は2004年頃から資金を少しずつ減らします。まるでデフレの鬼ですよ。
この為に本来は、米国の金融危機の影響をそれほど受けずに済んだはずなのに…人為的な経済の低迷の背景があったと考えています。病み上がりの実体経済に、過酷な条件を試すのは、明らかに行き過ぎでしょう。福井総裁の時期ですね。この失敗の時期が、今日のFRBの状況下と、同じように感じています。日本は1998年に、ほぼバブルの後始末を終えたのですね。およそ10年掛かりました。米国は5年で、対処をほぼ終えたのでしょう。処理を終えた後の政策は、金融機関に体力がない為に、充分なケアの期間が必要なのでしょう。大恐慌の時も同じ間違いをしたのです。折角、克服したのに…人間の思い込みは、恐いですね。メディアの人はこのような事実や背景を調べて、今回の金融緩和見送りなどを総体的に見るべきでしょう。
このグラフを見ると分かりますが、当面、日本株は安泰ですね。次に訪れるのは今のFRBの立場に日銀が置かれた時ですね。カタルが何故、弱小の不動産株のケネディクスに拘りを見せているか…。このベースマネーの推移からも、理由が分かるかと思います。基本的にデフレと言う環境に陥ると希望が消えます。インフレも怖いのですが、一番怖いのは希望を奪うデフレですね。インフレは物価高に苦労しますが、代替え手段は色々あります。ベースマネーの伸び率は、基本的に10%近くが望ましいのでしょう。これから訪れる黒田緩和の着地点は、非常に難しいでしょうね。消費税8%の選択をするのは仕方ないかもしれません。ただ同時に政府資産を売却し、小さな政府の実現を考えるべきでしょうね。空港から港湾、道路に水道と…PFIやPPPの推進努力が怠れないのでしょう。未だに官主導の経済対策などと言う言葉を聞くと…ほとほと呆れる次第です。