« バーナンキの金融政策 | 最新の記事 | おわび »
軍艦ビル売却の意味(2013年09月23日)
皆さんはあまり関心がないかもしれませんが、マネタリーベースの話は、非常に大切で中長期的に経済活動に大きな影響を及ぼすと考えられます。日本では日銀のケースを昨日見ましたが、米国ではこんな感じですね。上が残高の合計で、下のグラフは前年比のグラフです。ベースマネーそのものは過去に事例がない程、今回は供給されています。合計のペースで見ても分かり辛いので、前年比率で見た方が良いのでしょう。
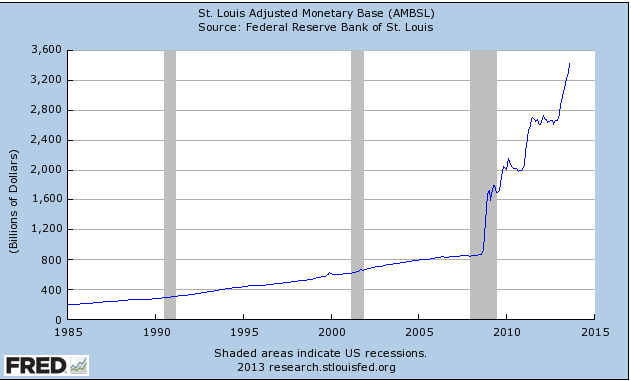
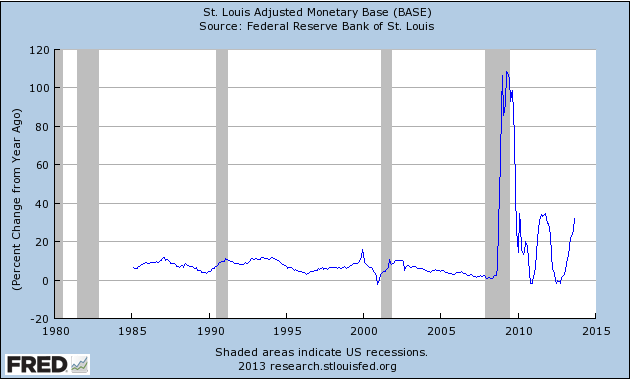
カタルが推察するに…経済全体の拡大に伴い適性な資金供給の割合があり、目指すGDPの成長率以上に、資金を供給しないとならないのです。例えば期待成長率を3%とするなら、インフレ率を2%程度として、5%では駄目で時代に合わせた糊代が必要なのでしょう。成長率3%を期待するなら、ベースマネーは8%程度の伸びを継続して増やさないと駄目じゃないかと…推察しています。事実、米国でもこの伸び率が鈍ると、必ず半年から1年程度経ってから景気の後退期に突入しています。日本でも同様の現象が見られますね。だから2006年のマイナス圏まで、資金を絞るやり方が間違っていたために、2006年から株価が崩れ、実態経済が大きく後退したわけですね。しかしこの時は米国の金融危機発生により、この失政がカムフラージュされたのでしょう。
今回、FRBはQ3では残存期間の長い国債を買い入れていましたから、仮に国債などの買い入れを縮小しても、供給はしばらく増え続けるのでしょう。…ですが当然、伸び率は落ちますね。現状の伸び率が32%となっていますから、問題はありませんが、2012年6月には一時マイナス圏になっていました。此処が問題なのでしょう。FRBも日銀と同じ過ちを繰り返してきましたね。2010年11月にはマイナス圏になりQE2を採用し、今回もマイナス圏になりQE3を採用しています。金融機能が完全に回復してない為に中央銀行が手を抜くと…、たちどころに指標が悪くなるようです。FRBはこの指標に敏感に政策を転換して反応しますが、日銀は鈍いですね。市場経済化してないのでしょう。このベースマネーの増減は、ことのほか株価にとって重要な指標のように、今の所は感じています。
ただこのベースマネーの供給量を見ると…、IT革命により情報の共有化が進み、世界が均一化と言うか、グローバル化が進みましたが、その為に通貨の大量な投入が必要だったと考えています。CDSの発達はその為に必要だったのです。新興国は信用がない為に保険が必要だったのですね。故に天文学的な水準まで拡大したのでしょう。しかし前例がない為に、同時に将来訪れる筈のインフレにも恐怖を感じる自分が、同時に存在していることは事実です。果たしてグローバル化に伴い、これほどの資金が必要だったのかどうか…。仮に世界的なインフレが進行するにしても、一人あたりのGDPが高ければ、低い新興国よりインフレの影響度は低いですね。つまり新興国から先進国への投資の流れは正解なのでしょう。
意外に、ベースマネーの考え方は、奥が深いのですね。自分でFRBの政策を調べ、日銀の政策を調べてみると良いですね。資料はそれぞれ、FRBは此方から、日銀は此方からです。さて今日はこの資金供給に絡み、日銀が異次元緩和を実施しているので、日本の不動産市況も回復してきたと言う話を展開します。カタルがよく引き合いに出す銘柄のダヴィンチが金融庁の指導により減損会計を強要され、上場廃止に追い込まれた事を述べています。その原因の一つのビルが、この度、売れたのですね。その関連記事が、金曜日の日経産業新聞一面に載っていました。
ミニ不動産バブルとも呼べる2006年に、ダヴィンチは、秀和が1982年に港区芝に建てた軍艦ビル(芝パークビル)を1430億円で買収しました。国内最大級規模の買収です。しかし金融庁の査定により、このビルの減損会計を余儀なくされ、利回り採算はあったのでしょうが、ダヴィンチが消えることになった原因の一つが、この軍艦ビルです。この軍艦ビルが1170億円で、8月にアブダビ投資評議会等のファンドが買収したと言います。このクラスの大きさは充分なのですが、古いのでBクラスとランキングされると言いますが、通常、先駆するSやAクラス以外にも、物件取得の輪が広がっている点が注目されます。今年2月にソニーの自社ビル1111億円が売却されて以来の最大規模の不動産取引です。
この背景を考えてください。2006年ピーク時に1430億円の物件が1170億円で売れたのですね。まだピーク時より20%程度、下の価格ですが…Bクラスの塩漬けされていた物件まで現状は動き出しているのですね。減損会計したので20%の損で売れるのです。今回の取得に絡み、エクイティーは10%と言われ、残りのメザニンローンを新生銀行やコメルツが引き受け、シニアローンをみずほが提供したと言います。カタルがこの事例を引き合いに出すのは…同じように減損会計を実施したケネディクスの持つ物件も、同様に売れる水準まで地価が戻っているのですね。つまり減損会計が含み利益に変わる瞬間に時間が位置している訳です。更に150億円の公募原資は、1500億円の不動産に変わるほど、金融機能が回復しているのですね。
つまりケネディクスの株価が2006年に4000円でしたが、その80%の水準で評価されても不思議ではないという事が、軍艦ビルの売却で推察できると言う事をこの事実は語っている訳です。中央銀行のベースマネー供給の話しと合わせ、軍艦ビルの売却を考えてみると、我が国が置かれている歴史的な立ち位置が分かりますね。安倍首相は海外向け投資セミナーに顔を出して、日本に投資を呼びかけているのです。ケネディクスの株価が年末から来年にかけ4ケタ以上に羽ばたく現実を、確信できる事実は、軍艦ビル同様にこれからも更に続くことでしょう。