« 人気株の検証 | 最新の記事 | ユビキタスの減額修正を考える »
新聞社により異なる見解(2013年10月27日)
先ずは…今朝の日経新聞と昨日のWSJの相違について述べねばならないでしょう。
WSJの見出しは「第3の矢の実現に慎重な見方=サードポイントのローブ氏」となっており、日経新聞は「日本に積極投資 2000億円」となり、どちらも投資家に送った書簡が元になり、記事が作成されています。
カタルはWSJの記事と読み、昨日は厚生労働省人事を絡め、水曜日からの市場の動きをみて、カタルなりに市場の動きを推察した原稿を掲げました。しかし今朝の日経新聞を読むと取り扱い方が、まったく違いますね。皆さんもWSJの記事と日経新聞の記事を読み、比較してみると良いのでしょう。同じ書簡を元に書かれた原稿ですが…、捉え方がずいぶん違うものです。
冒頭の見出しは、WSJのKana Inagakiと言う記者のレポートですが、そのレポートには『サードポイントは「安倍首相は、日本を前進させる改革を実現する数十年ぶりの絶好の機会を手にしていると思う。彼が成長戦略を実施に移すならば、我々は日本株を積極的に買い増すつもりだ」と述べた。ローブ氏をはじめ多くの外国人投資家は日本に対し、企業が雇用・解雇をもっと容易に出来るように労働規制を緩和することともに、先進国で最高水準である現在38%の法人税の引き下げを求めている。」となっています。
サードポイントは、ソニー株に投資して株価を押し上げた「ものを言う株主」です。映画や音楽部門などのスピンアウトを求めた経営改革を迫り、ソニーの平井さんは真摯に株主の意向を検討し棄却しました。株主総会が近づき日本を代表する企業としてのソニーの今後は、世界の投資家に向けた株価全体の判断材料にもなる訳です。
市場経済には様々な見方が存在し、投資家それぞれが独自行動をとり市場価格が決められていきます。どれが正しいという事ではないのですね。株価は皆の総意なのでしょう。ただクーツのガリー・ドゥーガン氏の見方に広がりが生まれているから、水曜日以降も海外市場は崩れてないのに、日本株だけが崩れた訳です。ただ日本株は、年金ファンドなどの保守的な機関投資家が不在ですし、ネット・トレーダーが増殖していますから、どうしても値動きが荒くなりますね。既得権力者は、目先に動くネット・トレーダーを批判しますが、これも新しい流れでこの動きを否定するのではなく、活用すべきだろうとカタルは考えます。このような目先の動きは、どんどん広がるものではありません。おそらく一時的なポジション整理で、その勢力は限られたものでしょう。故に日経平均株価の三角保ち合いが続いているのでしょう。
問題は…企業業績の通期増額が、最近の為替動向で慎重になることは否めません。100円を超えない壁を見て、経営者は本来なら通期増額を打ち出すタイミングですが、この増額修正が3Qまでに留まるのでしょう。この辺りまでは、既に為替予約をしてあり確実だからです。しかし1―3月の4Qは、まだ予約は進んでいませんからね。100円越えなら、いざ知らず、96円を見ると通期の増額意欲は大きく後退します。この変化をどう捉えるか…。市場には様々な見方が存在し、中国の短期金利の動向で日本株が大きく動くのは筋違いなのです。それだけアベノミクスへの信頼感が後退しているのでしょう。故にカタルは長期金利の動向を掲げたのです。そうして黒田さんに対し、消極的な政策ではなく積極的な政策を期待したのですね。それが昨日のレポートです。金利を下げれば融資が伸びると考える、時代遅れの解釈が「失われた時代」を長引かせました。むしろ金融庁の時価会計の厳格姿勢が、減損会計を生み、折角、努力した空洞化への対処の為のリストラを無駄にしています。シャープやソニー、パナソニックを見れば分かりますね。本来、カローラなどの大衆車の生産は仕方がないにしても…最近では高級車まで海外生産に移行しているのはおかしいのでしょう。空洞化の行き過ぎです。
一度はカタル銘柄に採用したアークの選択は、円安修正により日本に生産が戻るとの考えがあり、行き過ぎた空洞化が是正されるとも考えたのです。しかし現実は更なる輸出基地の移転を押さえた効果しかありませんせした。そうして3Dプリンターの技術革新が不安材料になりましたね。国内回帰の動きは生まれずに、アークの相場は腰折れしたのでしょう。カタルが期待するデフレ脱却の最重要のシナリオは「信用創造」です。すでに厳格な金融庁検査の結果で生まれた簿価価格(帳簿価格)から、アベノミクスの進展で20%程度の含み利益が、発生していると思われます。これが、この度のケネディクスの増額修正からも分かるのですね。順調に信用創造は進んでいるものと思われます。銀行の貸し出し動向推移のグラフを日銀から持ってきたので、その動きを見て下さい。このグラフと日経平均株価を、同時にイメージさせてほしいのです。面倒だからグラフを作るのを止めました。その代りに、ほぼ同じ期間のグラフを掲載しておきます。
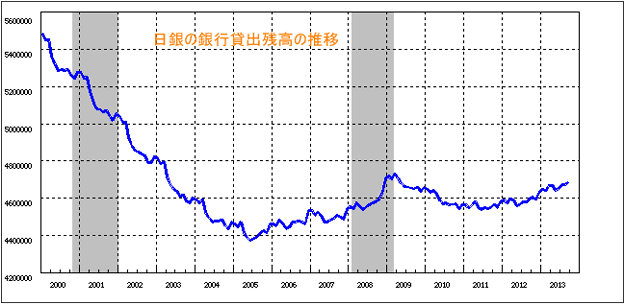
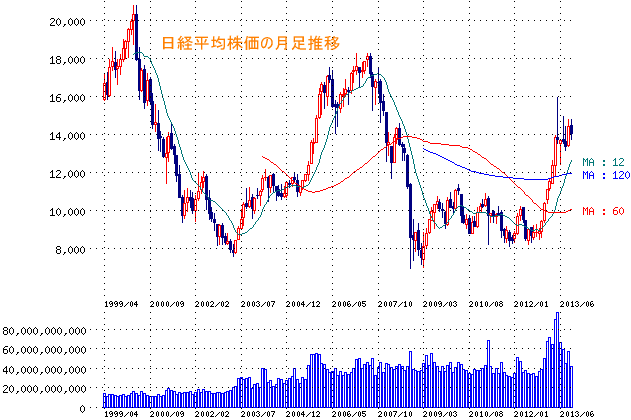
1年で一番儲かる年末年始を迎え、ネゲティブな心境に変化する必要はないと思われます。水面下では脱デフレ派の勢力は依然、強いのですね。何故なら既得権勢力も今の時代の流れを、これまでの闘争過程で理解しているからです。じり貧になると言う現実を分かっているから「TPP」などの交渉も進んでいるのですね。一番、力強い変化はソフトバンクの米国進出やファーストリテイリングの世界進出の成果です。その為に、本日の日経新聞、一面にも講談社のグローバル化戦略が報道されていますね。1億人より72億人の市場です。世界に目を向ければ、70倍の市場があるのです。先日はニトリの米国進出がニュースになっていました。最近では食文化の輸出がテーマになっています。粉ミルクの明治の中国市場放棄は残念です。しかしピジョンは中国でも市場を獲得したのです。経営者の感覚が何処に向いているのか? 味の素やニチレイ、水産業の冷凍分野は、経営の仕方でいくらでも、成長企業に変化する芽があるとも考えています。キーワードはグローバル化です。
少し焦点はずれてきましたが…、三角保ち合いを続けている日経平均株価に見えますが、先月の月足陽線は、間もなく始まる二段上げ相場が、確定しているようにも思えます。新しいステージに移行するときに、相場が弾みをつける為に、一度、しゃがみ込む動きは、人間がジャンプする行動と原理も似ています。おそらく先週の下げは、良い切っ掛けになり、ファンドのリスクヘッジ行動は必要ないのでしょう。先週の動きは弱小投資家の心理が反映されたものです。まるでカタルが、高値を買っては投げている行動と似ているのでしょう。ルビコン川を渡った認識を、黒田さんも共有しているものと考えています。日銀のETF買いは、もう直ぐ市場に変化を与える水準まで来るのでしょう。9月26日現在、現在は2兆2603億円で、毎週176億円を買い続けています。相場が急落した25日は131億円を買い入れたと日経新聞は報じています。短期筋のヘッジは、今週は更なる拡大せずに峠を越えると推察しています。
何しろ、ヘッジファンドの動向をカタルが臨むように日経新聞が記事にしましたからね。まぁ、捉え方は違いますが…公開することは重要なアイテムです。本当は、相場の動きと合わせた観測記事の方が、もっと市場の流れが分かりやすかったと思っています。通常、時価総額の2%を超えると、株価の値動きに変化が生まれます。現在の時価総額は400兆円レベルなので、8兆程買えば浮動株の吸い上げは終了します。まだ4倍もありますね。それだけ健全とも言えますが…信用創造には、いろんな手法があるという事ですね。