« 第二波動に突入できるか? | 最新の記事 | リベンジ »
株の選択(2013年11月24日)
今日は長く読んで頂いている読者の方の為に、株を選択するための基本概念を述べます。株価の決定要因は、企業業績が絶対的な目安になります。基本的に企業業績が伸びて、その成長率が高ければ、株価は高くなります。グローバル基準下での会社の評価は、株式時価総額です。どうやって株式の時価総額を高めるか? そのゲームのようなものです。小さな町工場から出発して、世界的な会社に育てるのが市場経済のゲームですね。
国家の力を高める事が、昔は基準でした。
豊臣秀吉が日本国統一の為に、織田信長の後を継ぎ、徳川家康に橋渡しをした時代は武力による統一でした。その後にポルトガル、スペインの植民地支配から、その後イギリス、アメリカの覇権主義と言う概念が生まれ、社会主義や資本主義と言う方法論の違う東西冷戦下のアプローチがなされてきましたが、目的は人類が豊かになる争いですね。現代では情報がグローバル化され、国境と言う壁がなくなり、自由に生産活動の場を選べるようになりました。
カタルがプラザ合意以降、日本は国家戦略を間違っていると述べているのは、日本村論理を捨て去り、グローバル基準の導入に抵抗したために進化が遅れたのです。その象徴的な現象としてNECから出発したエルピーダを何度か採り上げました。しかし世界ではテキサス・インスツルメントに入社したモリス・チャン氏は、プラザ合意の2年後に台湾で「TSMC」を設立し、受託生産の専門会社の「ファンドリー」を設立します。人件費の上昇や、法人税、電力料金など…様々な条件をクリアして、世界で一番生産に適した条件下で生産すると言う「ファブレス」社会に対応する会社を興しました。この時代選択にエルピーダは敗れたのでしょう。
日本は「もの作り」に拘り、諸条件が悪化しているにも拘らず、非合理な奉加帳方式で官民総出の日本村に拘りましたね。サムソンはNECから技術者を招き技術を習得し、韓国は税金も電力料金も安くして企業支援をしました。その結果、日本は競争に敗れました。中途半端な対応が、産業の競争力を奪ったのです。時代の選択の境目はプラザ合意なのでしょう。ここで国策を変更すべきだったのです。時代の流れはざっとこんな感じですが、今日は企業業績と株価と言う話で、業績は景気循環が影響します。その話を少し解説します。
先ずは、景気の上昇期と下降期に於いて企業の業績はぶれます。どうしても景気が悪くなれば消費は鈍り、全体のパイ(GDP)は失われます。景気が良くなると消費活動は盛んになり、生産は拡大し成長を遂げますね。この景気を左右するのが、金融政策や財政政策などの基本的な国策です。しかし日本はこれまで決定的な争いを避け、折衷案を採用し妥協して日本村論理を推し進めてきました。代表事例である「減反政策」などは、コメの内外価格差を維持する苦肉の策ですね。このようにして内外価格差は、至る所に存在していました。しかし…プラザ合意の時期がこの内外価格差を維持する限界点だったのでしょう。その時に国策を転換すべきだったのですが…国民は納得しなかったでしょう。その為に円高対策で、金利を低くし金融政策の失敗からバブルが発生し崩壊したのです。
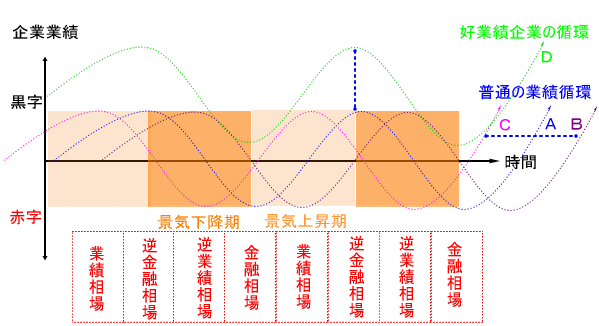
この景気循環と企業業績の流れを示したのが、上のグラフです。通常は、政策が失敗してなければ、多くの企業は緑色の好業績企業の循環Dに推移します。しかし近年は下のグラフのように資産価格が下落しバランスシート不況も併発しています。これが失われた時代です。宮澤喜一などが、年収の5倍で家が買えるようにと土地税制を変え、地価を強引に下げた結果、バランスシート不況も併発したのですね。ノーパンしゃぶしゃぶ事件から発生した大蔵省解体が金融庁の誕生を生み、このバランスシート不況を増長しました。
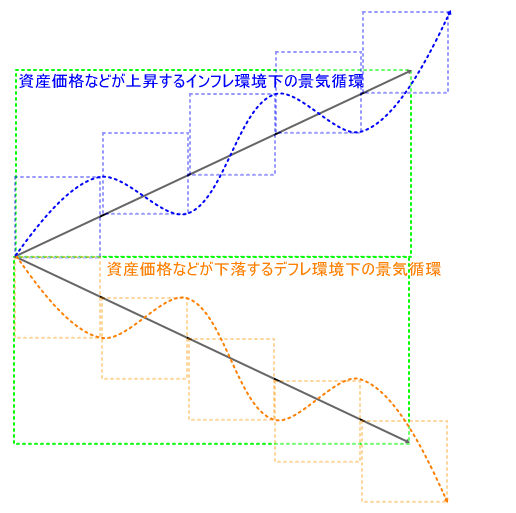
この含み利益の損失が1300兆円ですね。毎年60兆円ほど、期間利益や含み利益でこの損失を埋めてきました。その為に社会にユトリがなくなり、ブラック企業が誕生し、うつ病患者が増加し、自殺者が増えたのですね。この構造調整の中で、上手く時代の変化を取り入れたのが、ユニクロのファーストリテイリングや、家具のニトリなどが代表的な企業ですね。昔の衣料品価格は、日本独自基準で高かったのです。この上のグラフで、Aが通常の景気循環での企業業績のパターンですが、業種によりBに属する企業やCに属する産業があります。不景気の時期には食品や衣料品、景気の上昇期には設備投資の工作機械などの加工産業と銘柄の選別が変わります。更に同じ産業内でも経営者の力量によりAは、CにもBにも成りえます。トヨタなどは業績循環の位置が、他社より高いDの循環企業の代表事例でしょう。昔は東洋紡などの紡績だった時期もありますね。石炭の三井松島などが最優良企業だった時代もあります。時代の変遷により、リーダーは変化します。
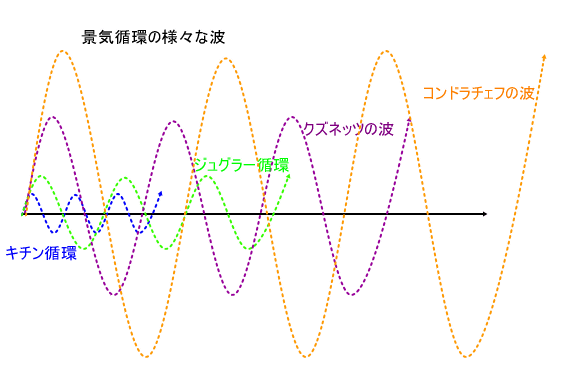
さて、その景気循環の波は色んな波動に分かれます。企業の在庫循環から発生するキチン循環は40か月程度の循環波動だと学者先生は述べています。しかしサプライチェーマネジメントの導入により、この在庫循環による景気の波は薄まっています。一方、設備投資による景気循環のジュグラー循環と言うものがあります。普通の旋盤やプレス機などは、通常10年程度は使い続けますからね。この景気波動は設備投資循環と捉えて良いのでしょう。半導体設備はこの寿命が短く、3年から5年程度でしょう。
また住宅投資などの街づくりや、工業団地や商業施設などの更新需要のクズネッツの波と言う期間20年前後の景気の波が存在すると言う学者の人も居ます。確かに戦後、大和ハウスなどは大相場を演じたことが過去にありました。昭和40年ごろから建設された多摩ニュータウンなどは代表的な事例でしょう。その多摩ニュータウンは65歳以上の人口割合が多いところと言われ、最近では限界集落とも呼ばれています。そうして再開発の動きもありますね。このような景気循環の波をクズネッツの波と言います。そうしてカタルが注目している007の時代革命を、コンドラチェフの波と言います。産業革命以来、スマートフォンの普及は代表的な事例でしょう。アップルは見事に、この景気循環を捉えた企業と言えます。
日本は日本村社会からの脱皮を果たし、様々な景気循環が好転する立ち位置に居ます。TPP交渉などは、代表的な事例の一つでしょう。カタルは資産価格の上昇が、力強い経済成長のためには不可欠なので、その正しい政策が実行されるなら、ケネディクスが一番潤う企業として選択している理由も、背景を考えると選択の趣旨がお分かり頂けると思うし、007はユビキタス社会にマッチした企業として、これから活躍期を迎えるとして成長企業の範疇で、会社を見守っている理由も分かるかと思います。ITS(高度道路交通システム)の利用は、これからです。現在は実験の最中でIVIが標準化され、カーナビとスマフォが一体化する未来技術という事は、皆さんにもお分かり頂けると思います。
株の選択は、この時代背景なのですね。昨日、土曜日の日経新聞3面には、長引く金融緩和、「欧米、上がらぬ物価」となっています。企業は業績が回復しても、なかなか設備投資を踏み切りません。この現象は新興国の生産活動が、先進国の需要より活発だからでしょう。間もなく新興国の購買力が、もう一段上がります。中国の労働賃金が上がり、最近の日本企業は、中国からベトナム、ミャンマーに生産基地が移転され、変化の動きがあります。更に最近は、最先端企業のファーストリテイリングは、バングラディッシュに進出しました。最低賃金国家での販売で成功できれば、世界何処でも通用すると言う発想でしょう。この時代の流れが、間もなく先進国にも波が回帰します。米国ではシェールガス効果があり、生産活動が戻りつつあります。要するに1985年から始まった時代の終焉が近づいているのでしょう。世界中の中央銀行が超金融緩和を実施しお金をばら撒き、先進国と新興国のギャップを埋めてきました。中国を事例にみると分かりやすいですね。沿岸部から内陸部に自動車販売の主戦エリアは変わり、先進国との賃金差は縮小しています。PM2.5の環境汚染問題は、ある意味で象徴的な峠の転機でしょう。シャドーバンキング問題も同じ土壌下で生まれた現象です。市場金利の導入は、あと2年から3年と言われていますね。時代の変遷期が訪れていますね。
株式の選択とは、このような世界の時代の流れを捉え、その環境下でもっとも潤う会社を選択して投資する事ですね。スマフォの誕生から発展でアップルが選択され、国家の概念がなくなり、企業価値を高めることが国民の目的になってきました。安倍さんは自ら企業団を引き連れ、積極的にアジア外交を展開しています。だから社会インフレ整備企業の日立であり、重工が選択肢の一つになります。本日、報道されている日米共同の半導体研究などもその一環でしょう。ボーイングがエンジンをIHIに依頼し、東レが翼などを製作する国際協調体制も生まれています。グローバル時代は、国より企業価値が優先される社会になるのかもしれませんね。習近平主席の新しい考え方は、的確にグローバル社会を捉えているのかもしれませんね。