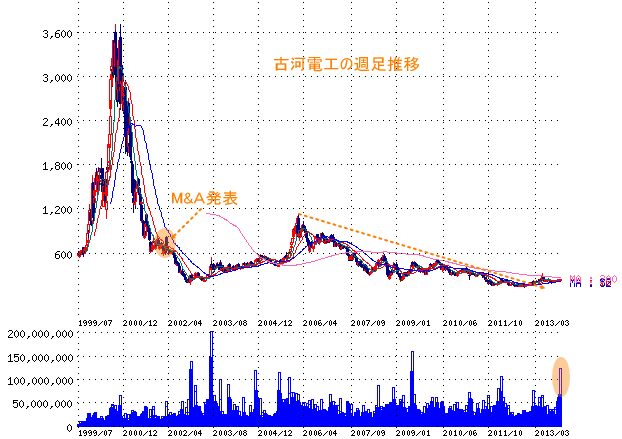リベンジ(2013年12月01日)
今日のテーマは「グローバル化」と言う話に触れたいと思います。昨日も話したように…日本企業はようやく目覚めたようにも感じるのです。1985年のプラザ合意の辺りから、時代はファブレス化(生産設備を持たない)している訳です。つまり新興国の躍進ですね。先進国から新興国への技術移転の始まりです。アップルなどは代表事例でしょう。この時期1987年に台湾のTSMCが設立され、1984年にサムスン電子は米国マイクロンより技術支援を受け、その後、1986年の東芝に始まり1991年のバブル崩壊で日本企業がリストラするのを受け、韓国政府の支援を受けながらサムスンは日本人技術者のヘッドハンティングに乗り出しました。日本の曲がり角は、このプラザ合意の時代変化に、官僚組織が中央集権型の日本村論理に拘る余り、政策の主眼を見誤ったことに「失われた時代」は起因しているのでしょう。
最近の相場を観ていて、日本を脱出している企業の活躍が目立つように感じています。日経平均先物指数先行の動きから、指数への寄与率の高い銘柄が物色される背景もあるのでしょうが、海外展開を加速している企業の物色にも見えるのですね。そこで昨日かな? LIXILGや日本板硝子の話を掲げましたし、最近、海外展開を加速し始めたニトリなども関心を抱かせる銘柄です。このシナリオの延長線を探る思考パターン下に、カタルは置かれている訳です。こんな心理状態のところで、先週の人気株を調べていたら「古河電工」が登場していたのですね。実はこの銘柄は、色んな思い入れがあるのです。隣の浜ちゃんが、大ヤラレする銘柄なのですね。ITバブルの時に一緒に上昇した人気株ですが、光通信やソフトバンクは2月に崩れましたが、古河電工も一旦は同じように連れ安しますが、その後株価は戻し高値を更新したのです。その年の夏に付けた高値の動きは凄かったですね。それで隣の浜ちゃんが値惚れで、1000円割れ辺りからだったか…買い始めたのかな?それがなかなか止まらずに、下がる、下がる。最終的には200円台ですからね。
丁度、この時期の2001年11月に古河電工は、ルーセント・テクノロジーの光ファイバー部門(OFS)を買収するのです。当時、27億5000万ドルでしたかね。日本円で3400億とか…。この馬鹿高値での買収が後々尾を引き古河電工は苦しみ続け、もう直ぐ構造改革が終了するのでしょう。来年の注目企業の一つとなるのでしょう。日本板硝子と共に、何故か、気になる存在なので決算書などを眺めていたのです。
日本企業はM&Aに於いて、過去、数々の失敗を経験しています。松下(パナソニック)などは良い事例でしょう。今回は三洋電機の電池部門に着目した狙いもあるのでしょうが、明らかに、この買収は失敗のように見えます。過去にMCA(ユニバーサル・スタジオ)と言う映画の会社を買って多額の損失を計上していますね。この時はソニーと競っていました。タブレット端末が低価格で一般化され、やはり映画や音楽のソフト資産の活用をソニーが中心になり、アマゾンなんかと共に協業すれば…まだ覇権を握るチャンスはあると思いますが、なかなかソニーは、このソフト資産の再構築に動きませんね。水面下では色んな動きはあるのでしょうが、アジアの通信インフラを手にする企業は何処になるのでしょう。もしソフトバンクが早期に米国市場で成果を上げる事が出来るなら…更に期待できますね。カタルは米国より人口の多いアジアを優先すると考えていましたが、孫さんの考え方は違いましたね。トップ争いの王道に進んだ印象です。
今日はヒントだけなので原稿は簡単にしますが、第一三共のランバクシー・ラボラトリーズ社の買収を始め、野村証券のリーマンや日本板硝子のピルキントン、古くはこの古河電工のルーセント・テクノロジーの子会社であるOFSの買収など…失敗が続くM&Aですが…グローバル化の推進と言う観点から、一度は失敗した投資が、再び輝きを取り戻る可能性はないのでしょうか? 先週の人気株リストの登場した古河電工の姿は、何故か、新鮮に感じるのですね。あれから10年以上が経過し失敗も完全に消化したのでしょう。