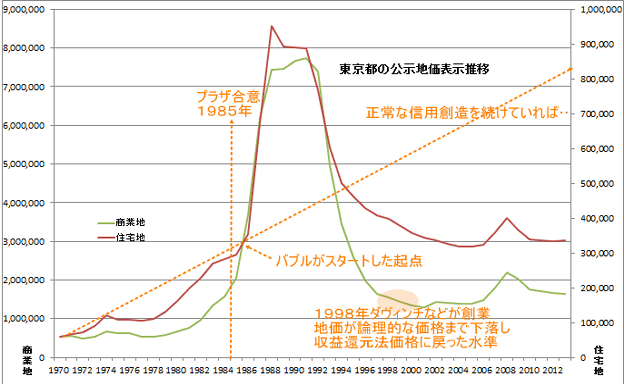« 理想買いと現実買い | 最新の記事 | 2013年を振り返り… »
村論理の矛盾(2013年12月29日)
市場における2013年の総括は、あとで振り返ってみたいと思いますが、ニュースを見ると、日本の実情が、浮かび上がるように感じます。貧乏をすると心も貧しくなるのでしょう。戦後の復興から日本は世界的にも類を見ない高度成長を続け、オイルショックも克服し成長を続けてきました。しかし昭和30年代のノスタルジーは、何を懐かしむのでしょう。バブル期の思い出より、何故か、心に響く映像が、体の中で流れています。物質的には現代の方が、ずっと豊かになっている筈なのですが…。人間的な心の豊かさは、やはり昭和30年代ですね。隣近所の子供たちが、陽が沈むまで缶蹴りや鬼ごっこ、縄跳びにビー玉、メンコなど…と、一緒に遊んだ楽しい思い出が、何時までも心に残っています。
先ほど読売新聞を見ていたら、JR北海道の乗務員が、乗務室で勤務中にパンを食べていたことを問題視され、厳重注意を受けたと報道されていました。この国は、やはり狂い始めている…と感じる次第です。些細な事を通報する乗客の倫理観は、まるで戦前の特高警察、中国の文化大革命やイランの現状に似てきたようですね。直木賞に選ばれた「ホテルローヤル」には、供養のために開いた法要に来なかった坊さんへの浮いたお布施をホテル代に充て、楽しむ夫婦の田舎の姿が描写されており、何故か地方経済の現状を描いている様で…悲しく感じました。経済面でも軽乗用車の生産台数が過去最高だそうです。レクサスなどが売れるなら分かりますが、長いデフレが生んだ結果なのでしょう。やはり高級車は乗り心地は、安い車と全然、違いますからね。そのレクサスは中東でも売れているようです。原油価格が高値で安定しており、日本の失われた時代と相反して豊かになったはずの中東ですから、イスラム過激派は勢力を失っている筈です。しかしシリアなどを見ると…未だに貧乏だから、食えないから革命などが起こる訳ですね。
ソフトバンクの孫さんが日本のお金を海外投資し、利に適った行動ですが…同時に野村監督がマー君の移籍を見て嘆いたように、ガラガラポンのリスクに備えた動きは、至る所で起こっている訳です。三菱商事も金属部門だけですが、稼ぎ頭の本社機能をシンガポールに移している訳ですね。節税ですね。この動きは日産自動車のマーチの生産をタイに移管したのと同様に影響力の大きな話です。グローバル化と言えば聞こえは良いですが…優秀な企業は、既にガラガラポンに備え、手を打ち始めているとも言えます。果たして政策担当者の人々は、この現象の意味を正確に理解しているかどうか…。たかが5400万株の信用買い残の壁を前に、怯んでいる市場のパワーレベルを考えると、清貧思想を続けた弊害を、日本の指揮官たちは認識しているのかどうか…。高級管理職の年収は2000万ほどです。多くはありませんが、少なくもなく生活に不安はありませんからね。
ただ東芝を始め、一流と呼ばれた企業は、挙ってリストラを敢行しています。あの松下銀行と言われたパナソニックも遂に追い込まれました。やはりかなり追い込まれたことは事実ですね。今は、半導体技術者は大変ですね。エルピーダに、ルネサスと食えない時代を迎え、NECなどがリストラした時は、まだ余裕がありましたが、今はあとがありません。ニートの語源は(Not in Education、Employment or Training NEET)だそうですが、若者のフリーターも多く生まれている日本では、まともに就職できれば良し…と言う社会環境ですからね。ブラジルなどへ移民をした時代に逆戻りしているようにも感じます。
日本村論理を維持する力もなく、だんだん追い込まれています。ベースマネーの存在が、かたるの株高根拠を支えていますが、同時に、みずほのやくざ融資を過大に問題視する清貧思想も、依然、存在し続けるわけです。折角の緩和力が抑えられています。米国はボルガーにEUも似た動きにあります。この感覚の綱引きが続いているのです。
さて最後になりました。カタルは正常な経済運営をする為には、民間資本による投資活動が活発にならないと正常とは言えないと思っています。現在は日本を始め、米国もEUも金融システムが崩壊し、その回復途上にあります。しかし日本がいち早くバブルを経験し、そのバブルを過剰に清算し続けてきたと言えるでしょう。りそなの公的資金返済をよく本文で引き合いに出すのは、そのためですね。米国ではフレディーマックやファニーメイなどのGSEを象徴的な現象としてカタルは考えており、時々、その話をします。
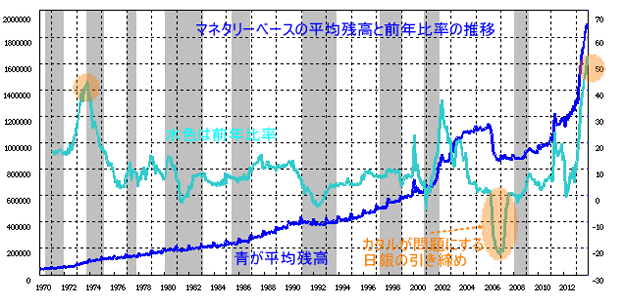
通常、これだけマネタリーベースを増大させれば、必ず、通貨と相対する資産価格は上がる訳です。だから株と土地は、絶対に上昇する筈ですね。故にソフトバンクの孫さんは銀座のティファニービルを、現状では馬鹿高値で購入したのですね。そうして日本で借り入れを起し海外に投資するのです。カタルが「ケネディクス」に拘っている理由が分かるかと思います。その様子を、上のマネタリーベースの推移と、下の東京都の地価推移を見て、自分なりに考えてください。本当は自分でカタルのようにグラフを作ればいいのですね。縦割り行政が、色濃く反映されていると感じるはずです。地価の価格評価には、路線価や基準地価、公示価格など…たくさんの算出方法が存在する矛盾も同時に感じると良いでしょう。何故、このような二重や三重の無駄な仕組みが、存在するのでしょう。地価価格はあくまでも一つの筈です。これは日本村論理の一つの表れでもあります。コメの減反政策と同じ土壌に存在する日本の矛盾ですね。司馬遼太郎が嘆いている根拠は、この辺りにもある訳です。