« 2013年を振り返り… | 最新の記事 | 市場に流れている川 »
営業キャッシュフロー(2014年01月05日)
さて新春第二弾のレポートです。昨日は企業理念の重要性を考えました。通常、PERなどの企業業績向上の視点から、株価を観察することが多いのですが、実際の株価は様々な評価が入り混じっています。目に見えづらい企業理念は利益の継続性の観点から見ても重要で、社内モチベーションの増大は企業家として、もっとも重視しなくてはならない発想です。M&Aなどの成否を握るのは、この理念でしょう。日本板硝子のようにM&Aをしてからのリストラ着手はいただけません。JVCケンウッドが苦戦しているのも、この辺りが影響しているのでしょう。単に合理性を追求しても人間は感情のある動物ですからね。人間一人一人の力が増大して競争に向かうのか? それとも減退するかは非常に重要です。株価を見ていれば分かります。楽天の三木谷氏を、あまり評価しなかったのは「押し付け」が強すぎますね。例えば社内英語の採用ですが…通常はTOEICの向上に奨励金を出すとか、部長職以上の管理職には750点以上が必要だとか…と、言うようなものでしょう。この辺りの考え方は難しいのですが、カタルはそう考えます。
さてカタルが思うに、皆さんの多くが、「株」と言うものを知りませんね。それは知識がないからでしょう。だから株価が下がると、不安になるので安値を買えないのです。通常、売り出されている本だけでは、なかなか、本質が書かれていません。何故、カタルが自分で資料を集め、それを独自に検証するのか? 昔は資料集めが大変でした。例えば興銀に、晩年招かれた浦上さんは、専属の女性秘書を常に移籍するたびに引き連れていました。日興から移る時もそうです。おそらく彼女に頼むと…必要な資料を作成してくれるからです。昔は資料集めが大変だったのです。今のようにインターネットが普及していませんから、官報など集める為に、わざわざ各省庁に出向いたのでしょう。カタルも、むかし一度、大手町だったかな? 官報などを取りそろえた本屋さんのようなところがあり、行ったことがあります。今ではインターネットで大概の資料は手に入ります。そうすると…メディアの眉唾報道に気付きます。
例えば日経新聞の昨日の夕刊では、米国の新車販売が、2013年は7.6%増との見出しが躍っています。今日の朝刊は一面に世界販売8300万台の文字が躍っており、如何にも有望な産業のような印象を持つでしょうが…実際は米国の12月は、伸びが1%未満だったとか…。11月の販売奨励金の反動があると解説されていましたが、GMは前年同期比で6.3%減、トヨタは1.7%減と言う有様ですね。ただ日経新聞も印象度の低い5面には「米国の鈍化」の話を持ってきています。因みにホンダは1.9%増で、日産はなんと10.5%増となっていました。カタルがマツダに対して上昇確度が鈍ると指摘したのは、この辺りの背景も考慮されています。北米で一番影響を受けるのは、恩恵が強かったスバル(富士重工)ですが…。しかし今では最も重要なのは中国なのです。年末に来て、安倍さんの靖国参拝は、春節とぶつかり、どういう影響を与えるでしょう。加えて消費税引き上げで駆け込み需要はあるので、最初の数字は良いでしょうが…春以降の懸念は、やはり拭えません。
グラフの描き方もそうですよ。採用する期間のより読者の印象は大きく変わるものです。昨日も、貿易統計を理解するために、比較的、期間を長く採用しています。全体論を把握するためには、時間軸を伸ばすのですね。株価チャートの分析でも同じことです。時間軸の短いものを、普段は多くの人が採用していると思いますが、基本的に企業業績は、3年、5年と言うスパンで動きます。一度、改善し動き出せば最低3年ぐらいは続くものです。問題は企業のターニングポイントと、株価の動きが一致しないことがあるのですね。だから時間軸が伸びたり縮んだりします。株と言うのは、会社それぞれで浮動株比率が違い、安定株主の度合いも違うので、株価の動きが銘柄により違います。「仕手性」と言葉に表すと簡単ですが、実に様々な要素が、その「仕手性」の中に盛り込まれています。株価の癖があるのですね。こればかりは経験がものをいう世界です。年初ですから、いくつかのエキスを盛り込んでいます。株価チャートで未来の予測に迷ったら、時間軸を引き伸ばし日足から週足へ、週足から月足へ変化させ検討するのです。更に1年を3年に、3年を5年、10年へと時間軸を伸ばしてみることは、全体の動きを把握することで非常に大切ですね。
さて利益の質も、そうなのですね。ネクシィーズと言う会社が、後半には株価が上がっていました。この会社の株価は軽く良く動きます。仕手性があると言うか…浮動株比率が低いと言うか、カタルも好きな株です。実はカタルも少し関係があり10月だったかな?経営幹部に会う機会がありました。彼はようやく改善してきた業績に喜んでいましたね。特に最近始めたLEDの事業が儲かるようで…後半は伸びると言っていました。でもカタルは、この利益は参入障壁が低く、利益の継続性に疑いを持ちました。誰でも参入できる分野で、営業力がものをいう世界ですからね。誰もが真似を出来る利益と、独占的な利益では「利益の質」が違います。だから特許と言うものがあり、利権が守られるのですね。ホトニクスの利益とトヨタの利益では、同じ利益でも利益の質が違います。
景気循環による循環型の利益と、景気循環に関係なく安定的に得られる利益と、どちらの質が良いかと言えば、継続性がある食品や薬品などの利益の方が、工作機械などの一時的な利益より、やはり質は高いのでしょう。ただ工作機械は変化率が高いから人気になりやすいですね。同じ継続性でも、電力や通信の利益は大きく伸ばすと、儲け過ぎの批判を浴び料金を引き下げられます。公共的な利益の質は、民間企業より割り引いて考えるのが妥当でしょう。カタルは、日本の携帯料金体制に批判的です。設備投資負担は一巡しており、料金を引き下げる指導を政府はするべきでしょう。此処に昨日話した内外価格差の二重価格制度問題があります。ガラパゴスと言われる日本基準が存在しますね。この内外障壁を長い時間をかけ解消してきたのです。その為に空洞化が生まれました。丁度、農業の政策に似ていますね。携帯料金も国際比較がされ、何れ統一されるべきです。今回の買収に成功したら、孫さんは、是非、世界で一番安い通信料金へのチャレンジをして欲しいと願っています。
さて前文が、今日も長くなりましたね。「利益の質」を考えています。昨日の企業理念も実はその話ですね。継続性の利益で、しかも独創的な利益、未来を切り開く利益は、一般化された参入障壁が低い、誰もが真似が出来る利益より、評価を高くすべきなのですね。人類の生活に豊かさをもたらす利益は、同じ利益でも評価を高くすべきですね。007に高評価を与えている理由も、この点が理解されれば背景が分かるかと思います。皆さんの多くが、株が下がると動揺されるのは、時代背景をしっかり掴んでない為です。時代背景や知識のバックボーンがないと自分の行動に自信が持てませんからね。
いよいよ今日の本題です。営業キャッシュフロー(営業CF)を見て、株価を読むと言う方法もあります。企業業績に先行して営業CFが先行して改善するのが、通常のパターンです。設備投資などの減価償却費がプラスされ、自由に使えるお金が未来の企業活動にプラスに働くからですね。営業キャッシュフローが悪く企業業績が良い時は、売上が伸びていても売掛金などの増加による見せかけの業績改善のケースもあり注意が必要です。本来、強い企業は売掛金の回収期間を短くして、強い企業体質を作ります。売り上げを重視する目標ばかり追うと掛け売りなどが増え、入ってくる筈の現金が入らずに損失に繋がるリスクも生まれます。故に企業業績と営業キャッシュフローの推移は、重要なのでしょう。この発想を発展させ、現預金残だけの推移を見て、株価の将来を予測すると言う方法もあるかもしれませんね。ただこのアイディアにも問題がありますね。季節性の問題や経営陣の意図的な変更があり、単に数字を比較するだけでは、簡単に使えない可能性もあります。
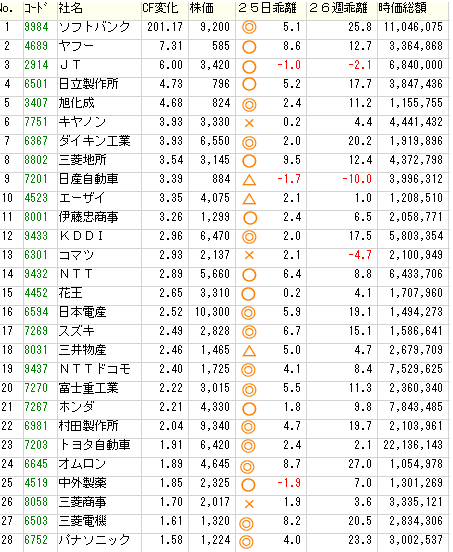
今日のテーマでもある営業キャッシュフローの改善度を調べたリストを掲げておきます。時価総額を検索条件に加えましたが、なかなかの成果ですね。チャートとリストを比べてみると分かります。(◎などの印はチャートの動きが良かったもので、チャートの違いを表しています。)◎が多いですね。28銘柄中13銘柄もあります。×や△は少なく、このリストは使えそうですね。まぁ株全体が上がり、当たり前なのですが…。今年、カタルが注目する伊藤忠もキャノンも花王は…昨年は、あまり芳しい成績ではないようです。このリストは3月決算に合わせており、12月決算銘柄は本来、出てこない筈ですが、キャノンや花王は12月決算にも拘らず登場しています。リストは第二四半期と第一四半期の営業CFを比較しています。日産は株主構成が悪いから、毎年、不人気なのです。日本村の影響なのでしょう。ハイブリッド開発に遅れましたが、その分、新興国開発では先行していますね。だから中国でのシェアは他の日本車に比べ、マズマズなのです。物産に、商事も印が悪いですね。利益の質が問題にされたからでしょう。資源価格の変動は大きく、いつも不人気です。しかし今年辺り、企業経営者の視点が変わり大量の自社株買いをしても不思議ではありません。これは株主も要求すべきですね。
昨日、本日と…この二日間は少し高度な話題で皆さんには難しかったでしょうか?
カタルが同じ銘柄を追い続けるのは、確りしたバックボーンが存在し、推奨銘柄には、それぞれの「狙い」が存在するからですね。007しかり、ケネディクスもそうなのです。ベースマネーの増大が、マネーサプライに影響を及ぼし、銀行貸し出しが増え始めるまで「タイムラグ」があります。それから不動産価格などが上昇していくのですが…、上昇初期は、これまでストックされた物件があり、それが消化される時間がありますね。軍艦ビルを話題に出すのは…不良債権物件の象徴的な物件であり、しかもアラブ系のファンドがエクイティーを出し、メザニンローンが使われている点ですね。何が言いたいか分かりますか?
株でもそうですよ。最初は浮動株の吸い上げが起こるのです。しかし市場に売り買いされている浮動株を、ある程度吸い上げると…、浮動株比率は減り続け、株価の動きがあるポイントを超えると、加速度的に変わるのですね。ケネディクスの話をしているのです。この瞬間と人間の感情のミスマッチが、「空売り」になるのです。強弱感の対立が、何故、相場を大きくするために必要か? 007もそうですね。今年は、その変化ポイントがやってくるのでしょう。今日はヒントだけに留めましたが、勘のいい人は、カタルの狙いが分かるでしょう。
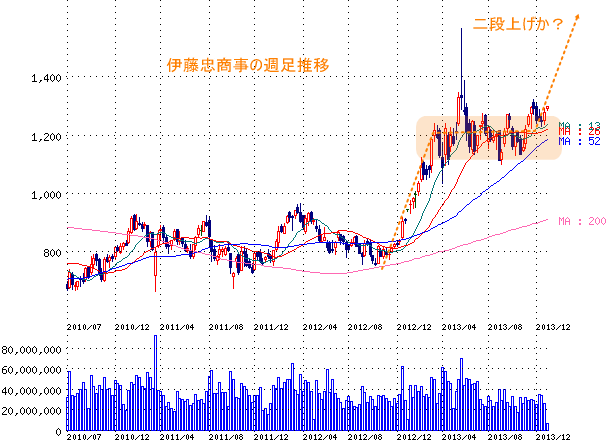
今年は、「年金基金」であるGPIFの動きが焦点にもなります。このリストを見ると分かりますが、配当利回りも重要な要素で…例えば商社ですね。商社は利益の半数は海外子会社からの配当収入です。つまり円安はプラス要因になりますね。資本収支が増えるのですね。円安は当初、Jカーブ効果などもあり貿易収支はマイナス要因になりますが、海外で稼ぐ資本収支はプラス要因に働きます。しかしFRBが資金の削減を急ぎ過ぎると、新興国の開発に影響を与え、商社の収益源である資源会社の利益、鉄鉱石から石炭など…の子会社群の利益が大きく減ります。この辺りは中国経済が大きく影響を与えますね。此処でバルチック海運指数の問題も浮上してきます。年末には商船三井なども買われていました。中国のシャドーバンキング問題なども影響を与えますが、いくらなんでも商社は割安過ぎますね。竹田さんが商社株を買う理由は良く分かります。一度、改善されれば、その後の上昇に割安だから妙味はなくなりますが、今年は年金ファンドの担当者が、商社株を買いに動く可能性は高いですね。伊藤忠などはチャートも素晴らしいね。今日も長くなりました。すべてを理解される必要もないですが…なんとなく、方向性を感じて貰えれば良いのでしょう。いよいよ2014年が、明日から始まります。今年は何倍に、お金を増やせるのでしょう。楽しみな年ですね。安倍さんの手腕に期待する次第です。