« ピンチはチャンス | 最新の記事 | 男子の本懐 »
農業の課題(2014年04月27日)
今日の日経新聞を読むと…問題視していた記事が登場しています。3面のTPPの記事ですね。「進む高齢化」となっていますが、問題点を指摘する視線が欠けていますね。この程度のレポートなら素人のレベルです。カタルが不思議なのは…、何故、就業年齢が65.8歳(2010年調べ)になり、5年ごとにおよそ2歳程度上昇していますから、現在はおそらく67歳程度でしょう。農林水産省も、JAもどういう仕事をしてきたか…と言う疑問ですね。確かに我々の生活でこれまで食糧難はありませんから、組織が機能しているかと言えば…合格点との評価を下す人も居るでしょうが…、やはりTPP交渉などを見ると納得できませんね。基本的に関税などをなくし、自由な貿易で勝てる強い組織を創り上げるべきです。調べてみると、24年度の農林水産関係予算は、復興予算を含め2兆3284億円だと言います。復興予算を除くと2兆1727億円ですね。
農地改良などの公共事業関係費が4896億円使われ、非公共事業が1兆6831億円、この非公共事業で食料安定供給関係費が1兆1041億円で、一般農政費は5790億円です。この内訳を別の視点で見ると、農業関係は1兆7190億円で、林業は2608億円、水産業は林業より少なく1832億円なのですね。林業の方が水産業より多いのは感覚的に不思議です。あとは農山漁村活性化交付金で96億円です。
ここで興味深いのは、就業年齢を意識して若者を雇用すると、補助金が年間一人150万円支給されることです。だいたい一月辺り10万円が、政府から補助されます。現状は利用者が1万人程度いる模様です。農林水産省は45歳以下と要求しましたが、財務省は39歳を主張しており、結局、折衝過程で45歳に落ち着いたようです。もし株式会社の農業参入への規制が完全に撤廃されると、カゴメや山崎パンなど、多くの食品企業が参入し効率化されるはずです。ワタミなどは熱心な企業です。
カタルが理解できないのは…何故、気候や立地に恵まれた日本で、グローバル競争をして一人あたりのGDP水準が高い米国に、競争で負けるのでしょう。大規模化のスケールメリットがよく弊害として指摘されます。戦後、GEQによる農地解放が、歪なひずみを生んだ原因なのかどうか…。兎も角、廃れ往く農業を見れば、予算の使い方や農地法などの法律がおかしいのでしょう。オランダのような小国でも、EUでは競争に勝ち残っていますね。オランダはハイテク農業の先進国です。日本は準天頂衛星を打ち上げる能力も予算もあります。もしこれを4機体制にし、コマツやクボタなどの技術を応用すれば、24時間体制で、機械が農地を整備し、気象衛星の活用など…情報のクラウド化を進めれば、一気に効率的な世界最先端の農業に移行できますね。カタルが述べているスマート・コミュニティーへの移行です。
007がスカイリーネットワークス社と業務提携を発表したことは、経産省の政策に乗るもので…過去に補助金を受けている実績からして、おそらく恩恵を受けますね。東電は既にスマートメーターを活用し始めています。更に新築マンションには目玉が必要でスマートグリッドの導入は、購買意欲を刺激ますね。エナリスなども関連企業です。HEMSの活用は不可欠なのですね。スマート・コミュニティーの事になると、直ぐに007を連想しちゃいます。折角だから、最近のテクニカル分析のグラフの載せておきましょう。いくつかの指標は変化を示しています。5ABと言うのは新しく開発した指標でアポロバーと命名しました。基本は陽線比率です。寄り付きより引けが高いと陽線になりますね。その割合が高くなるとプラスに変化します。
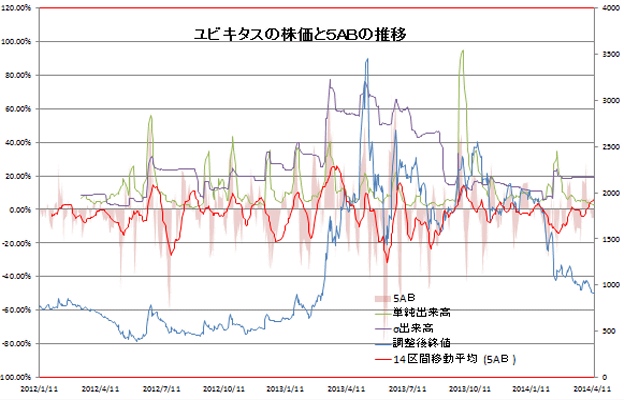
単純出来高推移とσ出来高が載っていますが、σ出来高は以前開発しボツになりそうなのですが…基本的に単純出来高推移だけでは比較が出来ないので、標準偏差の概念を出来高変化に組み込んだものですね。つまりご覧のように水面下では、14日間移動平均、つまり5日間ABの変化を、14日間の移動平均にした赤い線は、緩やかな投資家心理の改善を示しています。調整が一巡し始めていますね。最近はプラス圏です。ここで重要なのはタイミングなので、出来高の変化に目を向けます。だからσ出来高の上昇は面白い変化です。しかし実際の株価は下げていますから、このエネルギーが潜在的に貯まっているのでしょう。類似するかどうかわかりませんが…最近、株価が急上昇したアイフルの3月下旬の動向に007の最近の動向は、何故か似ています。ケネディクスは、よりハッキリと変化が感じられますね。まぁ、まだデータを集めている最中で検証も不十分ですが…。馬鹿は馬鹿なりに努力をしている訳です。