« 景気循環と相場展開 | 最新の記事 | 業績相場 »
景気循環と金融相場(2005年12月10日)
景気循環と経済政策を中心に、過去3回にわたり勉強してきました。そのなかで、前回は企業収益と言う観点から、売上に対する必要な経費と利益の関係にも若干触れました。基本的に景気動向と言うのは、人間の感情なのですが、僕らは名目の世界に生きているのです。よく実質金利とか、実質成長率と言う言葉を聞くと思います。その言葉に対応するのが名目金利、名目成長率です。この違いは一言で言えば、物価の動向を加味しているものと、しないものと言う解釈で良いと思います。
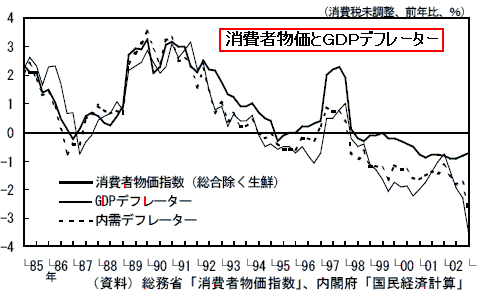 しかし消費者物価(CPI)の推移とDGPデフレーターなどの推移を見ると、DGPデフレーターの方が大きいのです。この原因は統計方法によるといわれています。
しかし消費者物価(CPI)の推移とDGPデフレーターなどの推移を見ると、DGPデフレーターの方が大きいのです。この原因は統計方法によるといわれています。
例えば、20万円のパソコンの性能が上がると、デフレーターは性能比の価格で見るために、処理速度が2倍になれば、価格は半値になるわけです。更に、最近の薄型テレビの激しい値下がり要因なども影響されます。
CPIは個人を対象にしているのに、GDPデフレーターは企業・政府を含めているからと言う見方もあるようです。
この名目GDPの数字が少なくなれば、景気は悪くなったと感じ、名目GDPが増えれば、景気は良くなったと思うのですね。名目GDPは、皆さんがもらう給料だと思えば良いでしょう。物価が下がっても、もらう給料が下がれば、やはり人間ですから、実質的な購買力は増えても、儲かった感じはしませんからね。この考え方で思い出されるのが、池田勇人の「国民所得倍増計画」です。政府の重要な使命に国民の財産と生命を守る義務があります。つまり平均寿命を延ばし、一人当たりのGDPを増やさなくてはならないのです。これは基本的な使命です。
その為に、景気変動に合わせ、金融政策や財政政策を実施し、景気をコントロールし、適正な成長を成し遂げねばなりません。景気が悪くなると金利を下げますね。社会全般にかかわる金融コストを下げるのです。景気の浮上は簡単です。お金をばらまけば良いのです。景気が悪くなればお金の供給を増やすのです。それでも景気が刺激されなければ、公共事業投資などを通じ、財政出動します。政府自らが投資をしてお金を循環させます。
やがて景気は刺激され、民需に火が付き、民間の設備投資が始まり、忙しくなると残業が増え、それでも賄えないと、工業を建てたり、人員を増やしたりして、労働コストが高くなります。もらった給料が増えれば、消費が増えます。不景気で我慢していた買い物をするようになります。今年の冬のボーナスでは薄型テレビなどのデジタル家電が売れることでしょう。景気が過熱すると、人経費が上がったり、原材料費が上がります。そうするとインフレ警戒から金利が上がります。やがて費用が増加し、原材料費の製品への転嫁が出来なくなると業績は悪化し、景気が悪くなり始めます。
中央政府がインフレを恐れるのは原因があるのです。極端に貨幣価値が悪化すると、リヤカー一杯のお金で、パンを買うようになってしまうのです。過去のドイツに、そう言う例がありましたね。通貨の信用は一番大切なことです。だから偽札つくりなどの刑事罰は重いのです。金利を上げると、物価は抑制されますが、当然、経済活動は阻害されるようになります。株高は良いことなのです。景気を刺激していますね。私のお客さんはマンションを買ったり、投資用の不動産を買ったり、車を買ったりして景気を刺激しています。株の儲けは使いなさい。どんどん使えば良いのです。お金は天下の回りものです。貯蓄は美徳ではありません。消費が美徳なのです。
さて金融相場です。季節感で言えば春ですね。世間はまだ春の訪れを知りません。株と同じで、下がらない株を買えば儲かるのです。春も大寒を過ぎれば、いずれ春が来るのですが、この時期の投資は非常に難しい。記憶に新しい所では、2003年の春です。既に金融政策は目一杯の緩和状態です。量的緩和と言う方法で、金融機関に食わせるほど、お金を無理やり突っ込んでいる状態です。しかし世間では倒産が相次ぎます。暗~い社会環境ですね。あの時は「みずほ」は倒産するといわれていたのです。おまけにシステム障害まで起こり…大変な環境でしたね。
「強気相場は悲観のなかで生まれ、懐疑のなかで育ち、楽観の中で成熟し、幸福感と共に消えていく。」と言う有名なウォール街の言葉があります。この言葉は、景気循環と相場の真髄が凝縮されています。更に金融相場では伝説の相場師、本間宗久は「人も我も同じ見込みの節、海中に飛び入る心もちの事」と述べています。厳寒の冬に、つめたい海に飛び込む心持でなければ、底値は買えないと、いっているのです。更に、古い格言では「耳に弱変を聞いて、心に弱変の淵に沈むことなかれ。ただただ心に買いを含むべし」と伝わっています。
金融相場は買いにくいのです。業績動向は悪く、更に悪化する見込みなのです。人々は売りだ売りだというし…そんな環境下で買い始めるのです。多くの場合、この時期は出来高膨らみます。どのスタート地点でもそうですが、強弱感が対立するのです。理論的には先回述べた業種が主役になります。銀行、その他金融などが中心ですが、通常、財政出動もされますから、建設、不動産なども金融相場の銘柄になりますね。
金利は低いので消費者ローンが空前の利益ですね。信販会社などは業績がいいはずです。デフレからインフレですから、金融商品からものへの投資が膨らみます。不動産もそうでしょう。石油や金などの商品へもお金は流れます。日本は長い間、過剰生産設備の淘汰を先にして、本格的な設備投資をしてきませんでしたから、設備投資は、現在、息の長い好況状態を維持しています。小松製作などは空前の利益だからね。工作機械もそうです。
金融相場は経済の夜明けです。最初は買いにくいものです。だから大量の空売りが入ります。2003年の相場はそんな景色図ですね。過度の政策失敗を銀行に押し付けたために、銀行株は倒産価格まで売られました。そうして、これからの利上げ局面で利鞘が抜けるようになります。しかし同時にヘッジをしているとは言え、金利が上がるに従い、保有国債の評価損を抱えることになります。そろそろ景色図的には金融相場は終焉を迎えます。
現在は業績相場の前半と言う位置づけでしょうか? 勿論、日銀が未だに金利を引き上げてないので、金融相場の銘柄は、多少、率は落ちますが上がるのでしょう。設備投資が増え、賃上げの話しが聞こえるようになっています。中国の繁栄や国内の回復により、素材価格は高騰しています。
すこし、オブラートに包んだ解説になりましたが、金融相場は非常に買いにくい環境なのです。2003年はそうだったでしょう。周りのアナリストは全て弱気です。武者氏の発言を思い出して下さい。あの当時は悲観一色なのです。私は明確な金融相場の経験が二度あります。一つは1984年の初めからです。それまで500円で株価管理されていた銀行株が、突然、上げ始めたのです。あれがバブル相場のスタートです。それから5年間は上昇相場が続きましたね。
今回は、あのときより相場のスケールが大きいのです。おそらく経験はありませんが、戦後の躍進や明治維新の活況に似ているのでしょう。日本は構造改革路線を進んでいますからね。世界に先駆けIT化の推進が、唯一できる国なのです。未来型の効率化社会の構築が可能なのですね。光ファイバー化の通信設備の環境は素晴らしい発展が期待できるのです。
すこし金融相場の解説と外れましたが、概略は充分理解できたと想います。金利が安くなると、儲かる業種が中心です。さらに今回の場合はデフレからインフレへの変化も加わります。大型株の物色が期待されるわけです。なにしろ大型株には、膨大な資産がありますからね。現在は金融相場から業績相場への移行期です。当然、素材価格が上がりますから、両者の恩恵を受ける商社は、銀行などの後に続く、中心銘柄の一つの業種になりますね。
次回は業績相場です。やがて素材から加工業種にメインが移ります。それと共に大型株から中型、小型に物色動向が変化します。一流から二流銘柄に選抜は広がります。その辺りを中心に考えて見たいとおもいます。