« 東芝を考えると… | 最新の記事 | 新興株ヤフーをみる »
ROEを考える(2007年04月21日)
今日は先日の木曜日に勉強会で講義した内容の補足をやろうと思っています。株式の評価と言うか、会社の評価には様々な方法があります。その中で優れている比較方法として一般的にROE(Rate of Return on Equity)と言う指標があります。日本語では自己資本利益率です。この式を下のように分解すると収益性、効率性、安全性から分析が出来るので一般的になっているのでしょう。
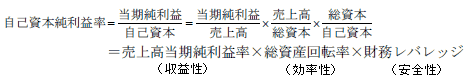
例えば松下では経営目標の一つに、ROE(株主資本利益率)10%以上と言う目標があります。現在のROEは4.1%で今期予想では5.4%になっています。このように会社が自らの経営目標としてROEを掲げている所もあります。今日は自動車各社の比較をして見ましょう。

一例を示すと日産自動車のROEは現在15.6%ですね。かなり高いです。しかし、よく分析すると売上高当期純利益率「収益性」(高いほうが良い)は5.49%で総資産回転率「効率性」(高い方が良い)は0.80回、財務レバレッジ「安全性」(低い方が健全)は3.53です。(デュポンシステムによる分析)
同じようにトヨタは12.4%、0.70回、2.73で、ホンダは13.7%、6.02%、0,88、2.57となっています。日産自動車はROEこそ高いですが、財務レバレッジの数字が高く安全性は欠けていますね。借金が多く自己資本が小さいといえるのでしょう。
この考えには成長性が加味されておらず、売上成長率、総資産成長率を合わせて分析すると良いと言われていますが、何故、日産が2003年まで買われ、その後トヨタの株価の伸びが高い理由は明白になりませんでした。私は当初、総資産が伸び率が高くなった後に、売上の成長力が増し利益の変化が生まれて株価が高くなると推測し調べてみたのですが、明白な関連性が見えなかったのです。残念ですね。
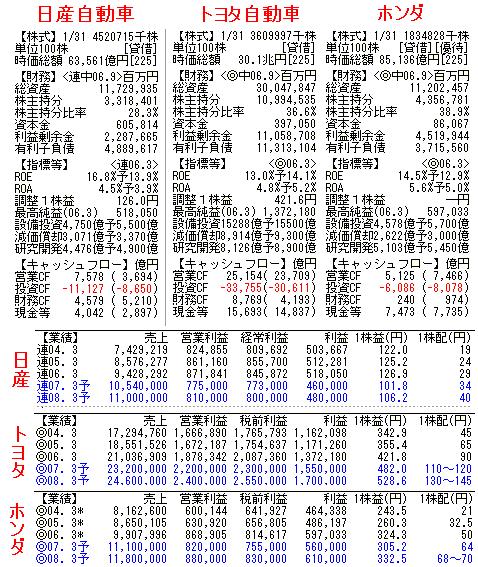
利益の成長率が高いので日産が上がったと言う理屈は分かりますが、トヨタの株高を証明できるまで至りません。やはり株は難しいというのが印象です。今回は検証に失敗しましたが、投資家一人ひとりが、株高の背景などを考え仮説と検証をすると自分の株に対する知識が深まるというものでしょう。今回は四季報数字から会社の状態を考えるというテーマで株を考えました。
