« 業績と株価(4) | 最新の記事 | 業績と株価(6) »
業績と株価(5)(2007年08月18日)
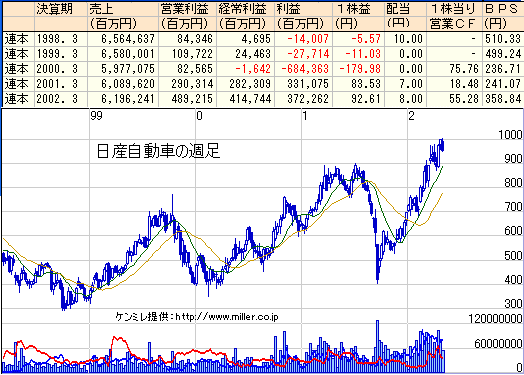
1998年の日産自動車は倒産の危機にありました。膨大な借り入れと赤字に苦しんでおり、深刻な内部崩壊が進んでいました。当時の塙社長は提携相手を模索し、フランスのルノーを選びます。(1999年3月)そうして資本を増強し改革に乗り出し、ゴーンマジックを演出して当時話題になりました。リバイバルプラン(1999年10月)を発表します。当時主力工場の一つの村山工場を売却します。
日本的な労働慣習などを打破する為には外部の強力な圧力が必要だったのです。日本人、自らがなかなか出来ない改革です。日本人の性格なのでしょうか?江戸から明治に変化する時もペリーの黒船来航と言う強烈なインパクトが背景にあったので成功したのでしょう。日産自動車は規模こそ小さいですが同じですね。カルロス・ゴーンによる強烈な改革精神が日産自動車の共産的な労働風土を変えていきます。
強烈な赤字の計上により、後戻りできない瀬戸際に追い込み、強引な手法によりコストを削減し黒字化を目指しました。この時に鉄鋼会社は大幅な値下げ要求を飲まされたのです。部品産業もしかり…系列関係が壊れ、日本的な仕組み経済の破壊により、新しいステップが開かれます。企業がマンネリから解放され、新しい企業風土が育ち変化する時に株価は大きく上がります。残念ながら日産自動車は非常に大成功とは言えません。その理由は資本政策にあるのでしょう。業績を立て直すことも当たり前ですが、株主に対し明確なメッセージを発信し、発行株式総数を減らす改革を選択しなければなりませんね。
この後も見て行きますが、オリコや日本信販の違いは明確ですね。双日と丸紅の違いに似ています。同じ条件なのに、僅かな資本政策の違いにより、大きな違いが株価に生まれるのは、やはり株式総数をどう考えるか? 日本人はサラリーマン社長のために安易な選択をしすぎですね。三菱自動車などもその例ですね。折角、立ち直ってきてもあれだけ株数を増やすと、どうにもなりません。借金は良いのですが安易に株式を発行すべきではありませんね。
加えて、かたるの本の104ページには日産自動車の例を用いて大きくお金を増やす投資術の解説が載っています。実際はこのように運びませんが考え方は大切です。この例も赤字から黒字転換する時に株価が大きく上がる様子を示しています。企業業績が不振に陥り赤字になる。そうして原因究明し改革に乗り出し黒字化する。この時に、株はねらい目なのですね。分かりますかね。確り理論武装しておれば、株価が下がっても恐がらずに買い向かえるのです。サブプライムショックで釣れ安した改革銘柄は買い場なのです。