« 2010年06月 | メイン | 2010年08月 »
2010年07月31日
株価の評価
今週は日清製粉とパナソニックが子会社を吸収合併するTOBが発表されました。そこで買収から株式の価値について考えて見ます。
近年は50%以上の支配権を持ち、子会社をコントロールしてから最終的に吸収するケースが増えています。何故、このような形を採用するのでしょう。汚い会社なら業績の悪化時に買収を仕掛けます。今のような株価低迷期なども狙い目ですね。更にわざと業績を悪化させたあとに、完全子会社化を謀るケースがあるかもしません。そのくらい業績数字はある程度コントロールできます。一応、会計法は継続性を重んじており、簡単に償却方法などを変えられませんが出来ないわけじゃありません。
でも最近の株価は安いですね。PBR1倍を割るケースが続出しています。土地や設備などを、ちゃんと時価会計していて、著しくPBRの1倍を割っているなら、会社を買って資産を売却すれば良いですね。配当をしている健全な黒字企業が、PBR1倍を割れるのはどうしても納得できませんね。企業買収でもめたブルドックソースのような過去の経緯があり、海外から買収する資金が入ってきません。途中でルールを勝手に変える日本は市場主義から遠く離れていると思われているのかもしれません。
更に一般的には株式はPERと言う毎年、生み出す1株利益の何倍まで買うか?と言う評価をされます。昔、日経新聞は企業の寿命を調べたそうです。一般的には30年と思われているとか…つまりPER30倍は30年分の利益を買った株価と言うわけで、近年はPER10倍程度で10年分の利益で会社を評価している事になります。100%株主還元する会社なら10年で投下資本を回収できます。単純に考えれば年利10%の債券を買っているようなものでしょう。
更に国により経済成長率が違います。
GDPと言う国民が生み出す付加価値の総合計の成長率です。年率3%程度が世界の標準かな? 中国は10%と高い成長をしていますから、相対的に中国企業の株価は高いPERで評価しても良い事になります。逆に日本のように1%程度の成長率では、PERの評価は当然、低くなります。業績が悪くても含み資産のある企業の株価は高い評価が与えられます。一例を掲げると松屋です。この業績内容なら普通は100円台の株価が良いところでしょうが、実際の株価は下げたとは言え600円台です。松屋は銀座の一等地に大きな土地を持って営業していますね。あの含み資産はどのくらいでしょう。
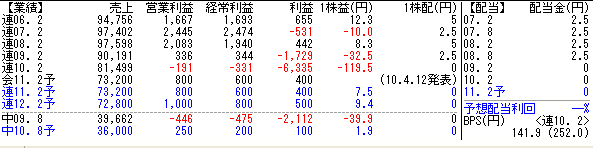
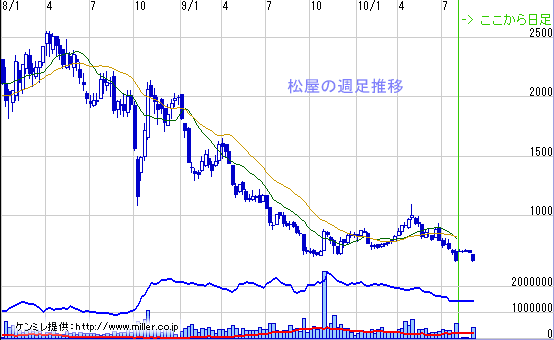
まぁ、基本はこの程度を押さえ、肝心なのは会社の業績の成長率です。
3年と言う短い期間で3億23百万円の売上げを100倍以上の325億円にしたグリーと言う会社が存在します。売上げが100倍は驚異的な成長率ですね。このような会社の評価はPERよりPSRと言う評価が正しいのかもしれません。30%の成長する会社が存在するなら9年で10倍になり、18年で112倍を超えます。高い成長率を示す会社ならPERの評価は10倍ではなく、20倍、30倍と高い評価をすべきですね。ITバブル時代はPER100倍を越えていた株はゴロゴロしていました。
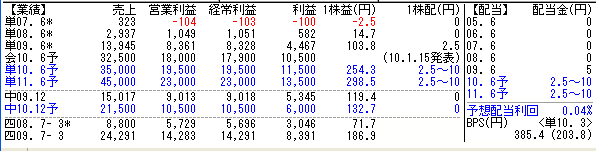
2010年07月24日
ヤングレポート
経団連の米倉会長は日本版の「ヤングレポート」を纏めていると言います。
このレポート作成時期、米国は双子の赤字に苦しみ経済が停滞していたそうです。しかしヤングレポートなどの提言により、米国経済は活力を取り戻し株価も上がってきました。基本的に米国はGDPの成長率を重視しています。1985年の話です。丁度、円高を容認したプラザ合意の時期ですね。当時の株価を見ると1986年にかけて上がり始めています。このレポートの内容は此方を参照してください。
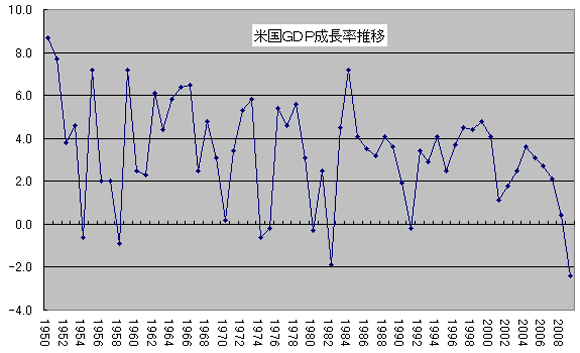
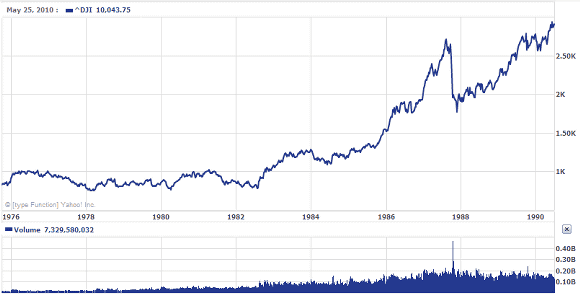
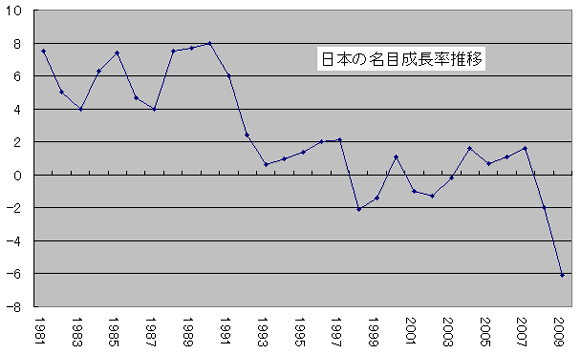
一方、1990年から1993年、そうして2007年から2009年と日本は二段下げを演じています。内外価格差の是正や構造改革の失敗が永遠と続いています。しかし昨年、民主党政権が誕生し、経団連を中心とする産業界は意識改革を推進しているようです。2003年からの日本経済の浮上は、小泉・竹中改革の期待で外国金融による浮上でした。しかし今回はこの外的な力は期待できません。日本独自で自力による変革をせねばなりません。
今期の決算のスタートは好調です。
ツガミの成功を真似する企業が続々と現れています。残念ながら、既に製造業の雄と称えられたトヨタも3流企業の仲間入りです。車を売るために多額の販売奨励金を使うようじゃ、嘗ての勢いはありません。自動車産業ではホンダの構造改革は進んでいるようですが、此方も技術力を誇っていたのに先行開発したHVでトヨタの後塵に拝するようでは負け組みの仲間入りのイメージですね。辛うじて日産が戦略的な動きをしているように感じられます。
自動車産業は巨額のお金が動きますから、関連企業が続々と生産基地を移転させている現象は、日本全体が移動しているような状況ですね。先日のタイヤメーカーの増産投資などを見ればわかります。だからアジア経済の失速はありません。さらにインフラ整備が未了な中国経済を心配するのも過剰反応でしょう。このような状況下で、なかなか日本独自の産業が育ちませんが、ここに来て元気が良いのがグリーやDENAと言う携帯コンテンツ産業ですね。両社はTVコマーシャルの利用率1位、2位が示すように足元景気が絶好調なのでしょう。ノキアが沈みアップルが浮上する背景にはスマートフォンの活用があり、3Gが進んでいる日本はこの分野で世界トップです。
もう一つ注目されている産業があります。
ただ残念ながら日本は辛うじてトップグループに属する程度で、首位争いは熾烈です。それは組み立てソフトの分野です。三菱電機の誇るIGBTモジュールは世界首位です。皆さんにはパワー半導体と言う表現の方が、馴染みは良いでしょう。カスタムICと言うか、組み込みソフトはDRAMなどと違い、長年の技術蓄積がものをいう分野です。サムソンにDRAMやフラシュは負けるのですから、そんな汎用品で勝負をしないでインテルのような分野を育てるべきでしょう。しかしこの分野でも東芝が英ARMに敗退し、残念ながら競争に敗れています。統合に追い込まれたルネサンス・エレクが辛うじてトップグループに位置していますが…、不要な汎用品開発を捨てて、世界トップの車の半導体などに特化すれば良いのですが、どうでしょうか?
東芝は追い込まれて構造改革を先行させましたが、その後の状況は楽観できませんね。西室、岡村、西田、佐々木と、佐藤氏が提言した改革を次いでいます。劇的な改革を実行した西田氏の偉業でしたが構造改革途上で今回の金融危機で遭遇し、集中投資した半導体部門が大きく痛手を受けました。しかし東芝に限らず、確実に日本企業は総合力から分野別の特化を始めています。要するに総合的に開発する余裕がなくなったので、仕方なく追い込まれているのが日立などの現状でしょう。野村證券も営業キャッシュフローが毎年赤字のように、追い込まれて投資銀行業務に進んでいる現状です。
今、新しく起こっている流れは、もう少し改善されない株価に変化として現れません。2012年にソフトバンクは借金の呪縛から抜け出せます。既に格付けも上がり金利負担が軽減し始めましたが、お金がなくて設備投資を怠ったために顧客満足度では最下位です。少し金利負担が軽減し始めたので、今は一所懸命に改善しているようです。残念ながら東アジアのグローバル競争を推進する経営者は、日本では孫さんぐらいでしょう。NTTは資金力を持っていますが肝心な意欲がありません。情報網を整備し活用すれば日本はアジアで中国の覇権を阻止し躍進できるチャンスがあります。
中・長期構想はこんなイメージです。
だんだん懸念された景気の2番底懸念は薄れていくでしょう。ただ日本企業全体が構造改革途上で、株価が大きく反応するのはまだ先の話です。しかし米国でも見られたように、まもなく単純平均株価がどんどん下がり続けるような株価の最悪期は脱出するでしょう。まぁ、横這いからステージを上げられるかどうか…。ここからの民主党政権に期待する次第です。
2010年07月17日
GSの和解
4月からの下げの理由を、ギリシャ危機を代表とする欧州市場の通貨体制の不備による下げと言う理由で語られてきました。しかし…私には疑問でした。
当然、ユーロ体制の不備なら、混乱を受ける当事者のドイツの株価は影響を受けていません。理由はユーロ安による輸出の回復と言うことですが、日本株の影響度は輸出企業だけでなく全般に及んでいます。どうしても日本株の動向を自国問題とせずに、為替とか世界景気の影響で語られる傾向があります。確かにわが国の株式は世界景気に対して、景気敏感株として反応していました。おそらく、理由は外人投資家がそのような目で日本株を見ているためでしょう。しかし近年は空洞化が進んでいます。輸出企業の生産設備は現地生産化され大きな構造転換に時間を掛けて完成させています。
2003年は小泉・竹中改革への構造改革への期待感で外人投資家が資金を投入し日本が浮上しました。しかしこのチャンスを自らの手でつぶしたのが日本の選択です。2006年は曲がり門でした。ライブドア、ブルドック、金融商品取引法、個人情報保護法案、建設基準改正法など…多くの規制が強化され、不動産取引にも総量規制が設けられました。折角、起こった浮上のチャンスを自らつぶしました。再び、清貧思想の蔓延化が進みます。振興銀行の検査はその出来事の象徴的な現象でしょう。基本はサラ金法改正などが発端になっています。
ただ12月から非常にマイルドですが、日銀はデフレ対策へ若干基軸を動かしています。役不足なのですが…。(やれる事はたくさんあるのですが、役割分担の責任をまっとうしていません。)みんなの党の躍進でデフレ対策がどうなるか見ものです。菅総理も主張は同じでしょう。基本はわが国の固有問題が負の連鎖に拍車を掛けているのでしょう。株価低迷の原因は沢山あり過ぎて…。さて目先の相場は4月から始まっています。日本の基本的要因は変わっていません。この下げを誘導したのは外人投資家の動向です。何故、日本株を売ったのか? 私の認識では、一番の原因はポジション調整だと考えています。ユーロ問題は補助的な要因です。
そのポジション調整の発端は金融規制法案の成立で、この駆け引きにゴールドマンサックス(GS)をSECが訴えました。4月16日の出来事です。7月16日、両社は和解し制裁金をGSは払います。GSの勝利と言われています。金融規制法案も民主党の主張をかなり取り入れましたが、細部は時間をかけながら検討するような内容のようで、目先、直ぐに規制が強化されるということではないと言われています。仮に指摘どおりなら、まもなくキャッシュ・ポジション化した資金が再び動く事になります。
果たして、この予測が正しいのかどうか?
現在はこのシナリオに沿って行動を開始したところです。

2010年07月10日
NY市場の反騰は本物か?
先週末に推測したような値戻しの動きが始まったようです。
NY市場は4連騰になり25日線を越えてきました。ただ2日の9614ドルの安値は6月8日の9757ドルを下回り、下値の確認作業はまだですね。先ずは200日線の10365ドルを抜けるかどうか…更に6月21日の10594ドルの高値を抜けるかが当面の焦点なのでしょう。一方、欧州のストレステスト発表を控え、その後の対策不安などの弱気材料が存在するなら株は上がってきており、金融規制からの4月~6月のポジション調整を終了し、7月から新規の運用期間で新しい金融規制に対応した動きと言う見方もあります。それなら、これから本格反騰もありますね。昨年の米国ストレステスト実施は2009年2月に発表され5月に結果が報告されました。そうして株価は3月から上がり始めたのです。
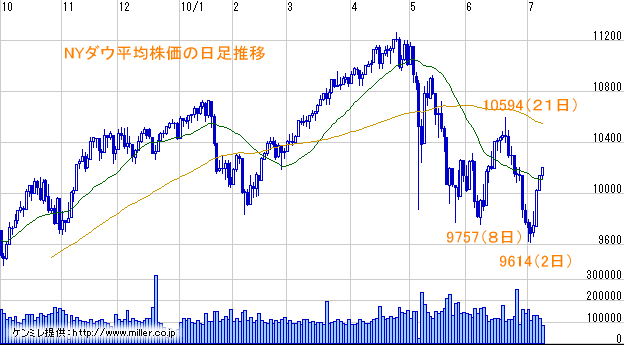
企業業績は非常に微妙な心理状態ですね。
機械受注が大きく落ち込み、景気ウォッチャーも下落しています。もっとも気になる動きは外人投資家の動向です。金融規制の影響がどの程度なのか? 今の段階では定かではありません。加えて欧州の財政規律政策は景気にマイナスとされています。先進国はデフレ、新興国はインフレと…富の平準化の時代を迎えているのでしょう。兎に角、日本が韓国や中国に技術指導をしていたのは、既に過去の話です。現在では3割程度価格競争力で負けていると言われています。本日の日経新聞かな? 日本を代表する製造業のトヨタやホンダは生産率を維持するために販売奨励金を増やしているとは…米国でも競争力劣化が指摘されているようです。
参議院選挙では「一番が溢れる国を創りたいと…」と自民党はアピールしていますが、現実は大きく水をあけられています。リストラクチャリングが叫ばれた鉄鋼不況から経営者の意識は変化できず、市場は低迷しきっていますね。デフレ社会が続くと考えているから日本株は黒字で配当をしていてもPBR1倍以下なのでしょう。ただ政策次第なのですよ。債務超過状態のダヴィンチの支配権を手にした米国ファンドの狙いは政策転換です。あれだけの不動産を支配できます。地価が上がり出してから集めるのは大変でしょう。株価の低迷は株主になっても経営権を支配できないブルドックの判決が響いているのでしょう。フジテレビ、TBSと、資本原理が通じない世界が日本にあります。
この状況の打開策に向けスタートを切った、多くの企業は初めての挑戦の為か、野村證券をはじめ結果はどうも芳しくないようです。仮に2番底に向かい先進国のデフレが続くなら、大きな投資を始めた野村は怪しい存在になります。金融規制の動きもマイナスです。逆に欧州のストレステストを無難に消化し、米国のデフレ回避が出来れば(この状況はFRBの総資産の圧縮で判断できます。)薔薇色の日本株の投資環境が実現される可能性もあります。現政府はアジア重視の政策展開をしており、日本には長年培った水道事業などの社会基盤作りの実績がありアジアの成長に貢献できます。
最近、地方自治体がノウハウを提供したり、高校生が起業活動をしたり、日本にも新しい息吹きがないわけじゃありません。ツガミなどは良い成功例の一つでしょう。ホンダや日産の海外生産移転の動きは、ある意味で革新的なのです。10年も遅れましたが…。どちらにしても、もう直ぐ方向性がハッキリします。今回は日銀が頑張っており、政府もまだまだ不満ですが、一応プラス方向の政策を採用しています。
踏ん張れるか?ニッポン! 明日は、是非、選挙に行ってくださいね。
2010年07月03日
お金が回らない
最近、かたる君は幾つかの点で光明を感じていますが、なかなか政策に反映されません。一つは日銀の金融緩和策、もう一つは会社法の改正により株式対価のTOB、そうして仕分け作業の特別会計へのメス。更に消費税の引き上げです。
株価を見ていると奇妙な事に気付きます。
本来なら在りえない株価が、至るところで理論価格以上に売られる現象です。つまり株式の価値が低下しています。お金の価値は上がり株式などの資産価格が理論以上に低下する。完全なデフレ状態です。地価は下がり株価も下がる。資産デフレが実体価値を蝕んでいるのです。国際会計基準では時価会計が原則なので、これらの下落は収益に反映され実態景気を揺さぶります。ダヴィンチが、何故、上場廃止になり倒産の危機にあるのか? 簡単です。土地と言う資産価格が売られているからです。つまり政策により国民の財産が失われています。
ダヴィンチなら許されると一般的に思われていますが、日本を代表するトヨタも日立も三菱UFJ銀行も同じ土壌です。時価会計などで、毎年のキャッシュフローで稼いでも、その利益は資産価格の下落に消えます。経済の仕組みが簿価会計なら問題ありませんが、時価会計なのでデフレ政策なら永遠とこの状態が続きます。何故、このような閉塞感のある政策を続けるのでしょう。
簡単なのですね。政治の貧困です。毎年上昇する社会保障費を補う為に国債が受け皿になっています。しかし…そろそろ限界点が近付いています。国債をこれ以上発行して先延ばしできなくなっています。銀行は貸出先がないと言っていますが、実際は預金で国債を買っているから実体経済にお金が流れません。全ての元凶は国債残高の水準にあります。外国人はデフォルト危機にある日本国債を絶対に買いません。しかし日本の金融機関だけが買うように仕向けられていますね。
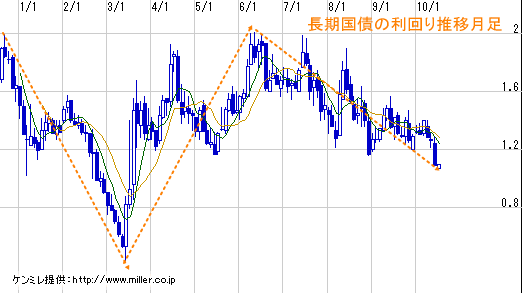
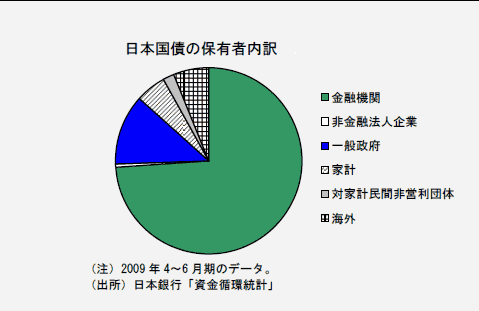
つまり閉塞感のないインフラ型の成長路線に復活する為には民間資金を国債以外に振り向ける政策が不可欠なのです。消費税を引き上げて毎年国債残高を減らし、預金を貸し出しに向ける政策が正常な経済状態に欠かせませんね。正常な経済状態になれば理論価格以上に売られている株価は上がり始めます。おかしいでしょう。三菱UFJの支店は都心の一等地の駅前にあります。日立の工場などは茨城の田舎の水戸にあるのです。日立は土地を売れませんが、三菱UFJは駅前の土地を売り、効率経営をすれば簡単に株価は上がりますね。しかし規制があります。三菱UFJは全ての売れる土地を有効活用して賃貸にしてそれにより得た資金で自社株買いをして、価値の上がった株券を使って海外の金融機関に対し、株式TOBを実現すれば良いのです。簡単に株は上がりますね。三菱UFJの純資産は621円ですが、株価は現在400円。
日本には二つの道があります。即刻、消費税を引き上げて国債を償還し、インフレ型に向わせて正常な経済を築く方法。もう一つは残念ながら決断できない政治家の弱腰が日本を破綻させ、円安、物価高のジンバブエ型の超インフレ型により収拾する方法です。何れにしても時間は限られています。増え続ける社会保障費をこれ以上、続ける事が出来ないからです。下のグラフは誰にでも分かる為に日銀統計から持ち込んでグラフを作成しました。日本を信じ永遠に買い続けた証券マンの末路は悲惨だなぁ~。民主党、頑張れ!
