« ようやく調整か… | 最新の記事 | 好業績1 »
決算と相場論(2011年02月05日)
重要なイベントの一つである決算シーズンを迎えているので…。
そのことについて考えてみます。我々は普段は需給予想による罫線〈チャート〉分析を主に行動をとりますが、実際は、会社に投資しているわけで、その会社が世界に羽ばたくような世界的な企業に成長すれば株主も儲かります。嘗てソニーやトヨタは小さな町工場だった時期があります。松下幸之助も今では経営の神様など崇められていますが、町工場の親父さんで博打好きだったようです。何しろ、先輩の話では松下幸之助の口座に追証が発生していたと言いますからね。チャートは業績〈会社〉の実態を表した形であくまで従の存在で、主の存在になることはありません。
今では過剰な信用規制が実施され仕手株などは育たなくなりましたが、むかしは兼松日産農林が業績も良くないのに5310円まで買われたことがあります。でも兼松は売りませんでしたね。馬鹿ですね。僕が親会社の兼松の社長なら兼松日産農林を売り、新しい会社を作りますね。日本的な非効率な面があったわけですが…。日本には独特の「村社会」から「会社社会」に移行した文化があったために、効率的な面が失われているのでしょう。まぁ、例外は兎も角、普通は実態以上に買われないものです。最大の評価がPER100倍ぐらいでしょう。この場合のPERの評価は、現状維持で100年分の利益を買うと言うことですからね。常識的には企業の存続は30年程度と言う認識がありますから、最大評価はPER30倍程度なのでしょう。
しかし企業には成長力が存在します。
利益が毎年5割づつ増える企業があれば…下の表のように成長力が加味されるとPERの評価が変わることが分かると思います。先ほど最大でPER100倍程度と述べた理由は5割増ペースで利益が伸びた場合に限られますね。A社の10年間の利益合計は100ですが、業績が5割増ペースで伸びると、C社の利益の合計は1000を超えるので、A社がPER10倍なら、C社がPER100倍で評価されることになります。毎年、30%増益でもすごい数字ですね。B社のケースはPER42倍の評価が妥当だと言うことになります。このような考え方で株価は一般的に評価されています。
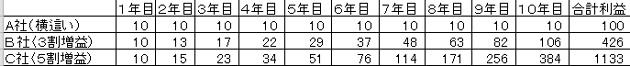
さて、話を戻しますが業績の数字は中長期的な株価の方向性を決めます。今は決算が行われその方向性が発表されています。私は東レを買い、帝人を売りとの短期的な評価を下していましたが東レの株価が上がったことにより、あと僅かな余地で東レも間もなく下落すると考えていますが、中長期的な評価は全然違います。東レは4ケタ銘柄の素質を秘めていますね。帝人の評価が低いですが、ほかの企業から比べれば良い決算数字でした。決して悪いわけではありません。しかし空売りしたのは、既にこの数字を充分に評価したと思っているわけです。所謂、「材料出尽くし」と言う段階だろうと考えているわけですが、時間的な経過により評価内容は変わります。この辺が分かりにくいところですね。
帝人もかなりいい決算には違いなく、決算数字を先取りする形で上がってきたわけです。故に買っているファンドがロングのポジションで、更に買い意向があり、資金的な余裕があれば、株価は、今は上がれないでも横ばいを維持し、いずれ時間的な調整を経て、業績数字がさらに上向けば、上がる段階を迎えるわけです。逆にファンドの資金量が豊富で帝人を更に買い進める力があり、尚且つ帝人が予想以上の業績結果を残せればファンドの大儲けで大勝利になりますね。こんなことは誰にも分かりません。少なくともカタルは、決算数字を見て、東レは買えるが、帝人は一杯だな…と言う現状評価を下しているわけです。
個別株はこの段階ですが、市場全体の評価があります。システマティック・リスクと言う部分ですが、日経平均株価は上がり続け、二番底を過度に織り込んだので、その反動で歴史的な上昇相場が続いています。騰落レシオ、かい離率、上昇期間など…どれもテクニカル的では、かなりの過熱を示す指標が出ています。過熱感とは…強い相場の裏腹の言葉で、過熱感が強いと言うことは、相当、強い相場に突入している可能性がある訳です。カタルが今日の市況で述べている「スーパー成長サイクル論」ですね。
この考え方の背景は、世界経済が新たな段階に突入したと言う可能性を示唆しています。EUの人口はおよそ5億人、米国は3億、日本は1億です。だいたい9億人ですね。他の先進諸国を入れても10億人程度でしょう。しかし世界の人口は69億人だそうです。この内、半数がグローバル化により市場経済に参入してくると言う読みが背景にありますね。ゴールドマンが指摘したBRICsと言う言葉は有名です。BRICsのCと呼ばれる中国は13億人、Iのインドは12億人、Rのロシアは1億5千程度、Bのブラジルはだいたい2億人です。この人達はだけで30億人近い人が市場経済圏に参入します。だからスーパー成長サイクルなのですね。
でも…バーナンキは否定していますが、QE2政策によりワールドマネーがばら撒かれ、市場経済が加速成長するので資源が不足します。中国は非効率な資源の使い方をしていますね。日本もどちらかと言えば、リサイクル社会の確立は今一です。先日、諏訪市の豊田で汚泥灰の入札がありましたね。1年分の泥が2265万円の価値を生むのだそうです。まぁ、金が取れるから高く売れるのですが…。早く現政権はこのリサイクル社会の確立に取り組まねばなりません。せっかく作ったペットボトルも経済効率概念がないために、頓挫し貴重な資源は中国に向かいました。まぁ、話がそれてきたので…ここで話を戻しますが、人口の多い新興国の人たちが文化的な生活になればなるほど、資源は貴重になります。
日本は国土が狭いために公害問題で苦しみましたから、環境関連の技術は世界一なのです。ここでも活躍余地がありますね。要するにQE2の弊害は必ず起こります。スーパー成長サイクル入りする前にその弊害のリスクを市場が感じるかどうか? 今の相場の焦点は既に米国が立ち上がるとか…どうかではなく、QE2の弊害と言うか資源コストの方向性に向いているとカタルは判断しているわけです。だから雇用統計がどうのこうのと…騒いでいる場合ではないのです。
昨年カタルは自動車だと述べてきました。しかも既に製品メーカーではなく部品メーカーの時代だとも述べています。この現象は日韓貿易をみると分かりやすいでしょう。韓国はサムソン電子をはじめ現代自工やLG化学などは世界トップ水準です。ですが中小企業の育成がないために部材は日本からの輸入に頼っています。サムソンのスマートフォンが売れれば、村田が伸びますね。こんな関係です。だから日本はまだまだ捨てたものではなく大きく伸びますね。司令塔がしっかりしていれば、コマツのような会社がたくさん誕生し日経平均株価10万円も…まぁ、最高価格38915円の奪還も夢ではありません。
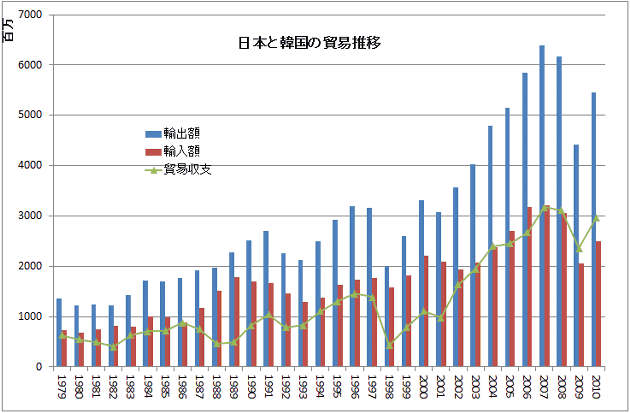
でも…ね。チュニジアの一人あたりのGDPは3500ドルですね。中国と同じ程度です。良い国だそうですね。その国で革命です。エジプト、アルジェリア、イエメン、ヨルダン…このインフレの壁をどう処理するのでしょう。このあたりが難しい読みになりますね。予想されるインフレ・リスクとスーパー成長サイクルの関係で、銘柄選択がガラリと変わります。加えて相場は伸びきっていますね。アクションがあれば、いくらでも叩けます。EUのユーロの不備を突く材料に加え、新たなリスクが忍び寄りますね。ここの読みは難しいのです。今の時間は簡単じゃないですね。
ざっと決算から相場論を述べました。皆さんの参考になれば幸いです。