« 2011年07月 | メイン | 2011年09月 »
2011年08月27日
推論
米国のGDP統計が発表され、いくつか気付いたことは、ドル安にもかかわらず輸出は7.9の伸びから3.1%に大きくペースダウンしたこと。そうして意外にも民間国内総投資が3.8%から6.4%に伸びていたので、まんざら「流動性の罠」に嵌ってお金が動いていないわけではなく、QE2の効果はある程度あったと言うことを示しているような数字でしたね。やはり個人消費の影響が大きいのでしょう。2.1%から0.4%に大きくペースダウンしています。もう少しなのに…と言うイメージです。株高の資産効果は続かなかった。株価が異常に強かった昨年末の環境の景色を、GDP統計は物語っているようです。
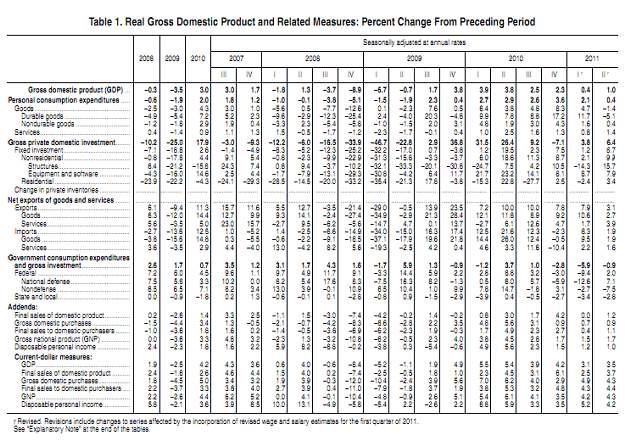
ここで分かるのは、私の推測であるアップルのようなファブレス企業が米国には多く、基本的にドル安による輸出増で、米国の雇用が確保されるか?…と言う疑問を、問題提起していましたが、GDP統計からも輸出が大きく減っており、オバマ大統領の政策運営が正しいかどうか…と言う、私の疑問を裏付ける統計値結果のような気がします。

さて昨日の宿題と言うか…。一つは米国の賃金上昇率の推移ですが、ここ数年間は伸び率が大きく減っていますが、米国はITバブル以降も消費が落ちずに元気でした。賃金が上昇しないのに消費が増えていたのは金融機能の影響ですね。住宅ローンの返済で余った枠が融資され、米国人はその借金で消費をしていた過剰消費〈ゾンビ消費〉の修正が必要だと言うのが分かると思います。40年と言う期間は長く、米国の労働者賃金の成長がなくなった原因の一つが、先進国から新興国に流れた産業移動の構図でしょう。所謂、空洞化問題ですね。別に日本だけでなく先進国すべてに共通している問題です。
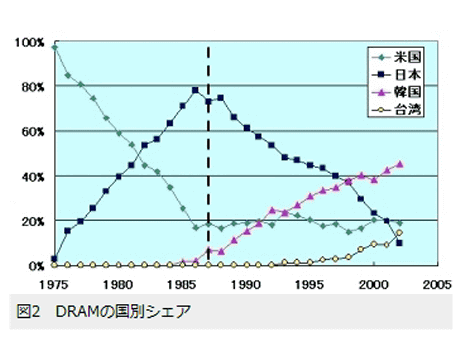
もう一つが1987年にピークを迎えたDRAM生産量の推移のグラフですね。私は日本の曲がり角をは1985年のプラザ合意だと思っています。DRAM生産の推移は、その考えを裏付ける資料の一つでしょう。もしあの時に産業構造を大きく変える挑戦をしていれば、失われた時代もなかったと考えています。「鉄は国家なり」『半導体は産業の米粒だ』と言う視野の狭い考え方がグローバル化に遅らせ、失った時代が続いている元凶だと推測しているわけです。
産業は軽工業から重工業に移ったように、生産性の高い分野へ常にチャレンジしなくてはならないのです。今日の日経新聞にはセラミックコンデンサーの記事が掲載されていました。半導体と同じ構図です。NECなどの社員がサムソンに行き、日本は諸条件〈電力料金や税制、TPPなどの経済政策〉の不利さで競争に勝てず産業構造が崩壊しました。セラミックコンデンサーも同じことですね。TDKはサムソンに敗れ…変化を迫られます。
このような現象を見て常に新しいチャレンジが、高いGDPを維持することに欠かせません。先進国から新興国の流れを米国の賃金上昇率のグラフやDRAM生産量のグラフから感じることが出来ますね。でも失望することはありませんね。ソフトバンクのパラソル戦略により日本は世界で一番、インターネット言う情報手段が整備されている国で、物流システム構築されています。ITS(高度道路交通システム)の整備は進んでいます。これらの情報化の社会基盤設備を利用した産業が興るのです。インターネットは産業革命と同じなのですね。
米国の賃金上昇率のグラフを見て…世界は産業革命の位置にいるのだろうと考えています。今は時代の激戦地帯で、大きく変化しています。日本はスマートフォンの普及率でも世界で先端を行っているでしょう。GPS衛星の予算が付いたそうですが、早く24時間体制にすることが必要ですね。産業構造が一巡し震災を切っ掛けにスマートシティー構想を大きく推進させれば、人類の情報化と言う産業革命競争の先端を走れます。電力・ガス・水道の見える化は、人間の意識変化で新しい産業が乱立して、物から情報などへ価値観が大きく移行する時代が幕開けするのでしょう。
さて昨日掲げた二つのグラフから、カタルはこのように考え方を発展させてきました。バックボーンがここにあるから、銘柄選抜はその流れから選ばれることになりますね。バーナンキは昨日QE3に言及はしなかったが、含みを持たせ市場を先導することに成功したようです。「言葉の魔術」、人間の感情って、面白いものですね。
2011年08月20日
技術革新を促す規制強化
市場には「効率的市場仮説」と言う命題があります。
市場は全てを知っており、未来の経済状態を反映したものが現在株価だと言うのです。しかし…株式相場の投資とは、その市場価格と現実的な企業価値との価格差を見つけ、その価格差が将来修正され事を念頭に置いて投資して、そのギャップが修正され利益になることを狙うものです。未来の企業価値を予測し市場価格が修正されることを狙う訳です。カタル銘柄はいくつかの仮説が用意されており、その仮説通りなら株価が上昇すると言う狙いがあります。
ただ、この判断を難しくしているには、個別企業の分析だけではなく、市場全体のリスク判断が拘わるからですね。現在の世界経済は金融相場が終了し、業績相場から逆金融相場に移っている過程ですが、中国はこの段階から既に逆業績相場に入っており、間もなく再び金融相場に向かう段階かと思われますが…問題は欧米ですね。
欧州は利上げを実施しており、緩い業績相場から逆金融の段階ですが、米国は期待感が先行し、折角、好業績になっても失業率が改善されず、過大な期待が金融政策を歪めているのでしょう。本来なら逆金融へ移行すべきだったのですが、移行するチャンスを失いました。故に政策手段が乏しく難しいかじ取りを迫られます。この原因は過剰な金融経済の発展が実体経済を押し上げた為に、その調整に手間取っているのでしょう。失業率も住宅価格問題もしかり…。既に米国は日本と同じ道を歩み始めています。メロン銀行のマイナス金利は日本でも同様の現象が起きました。格下げにも拘らず米国債は買われ金利が下がっていますね。一番怖いのは通貨安ですね。日本は馬鹿ですね。外貨準備の多くが米国債です。1ドル100円が75円と言うことは25%も損をしていますね。100兆円なら25兆円ですよ。
FRBの政策手段として、期待インフレ率を高めねばなりませんが、既に十分に通貨は供給されていますが動かないのですね。先行き不安の為に動かないのです。今までのように住宅関連の債券や国債を買っても、現金を持っている人たちが行動に移らなければ仕方ありませんね。ドル安政策で輸出を伸ばし雇用を伸ばそうと言う経済政策は明らかに間違っています。米国の多くはアップルのようなファブレス企業で、安い労働力を求め生産基地を海外に移転しています。一人あたりのGDP水準は高く価格競争力に勝てる道理がありません。
技術革新による社会の構造転換が必要です。一例を掲げるとスマートシティーをはじめとする未来社会の創設などですね。情報を駆使した効率的な社会基盤を整備し、今までの価値観を大きく変えることです。自動車の燃費規制はある意味でこの技術革新に沿った行動ですね。CO2対策の環境問題の枠組みを実施し、企業に革新を迫るにも一つの方法でしょう。京都議定書の行動は先進国だから出来る一歩先に進む技術革新です。壁を超えるのは大変ですが一旦壁を超えれば、他国より一歩リードできます。このような技術的進歩を誘う規制は先進国には必要ですね。
それをワールドマネーになっているドルなのに、通貨安によって生産性の優位を狙い雇用を確保すると言う手段は負け犬の姿でしょうね。オバマ大統領は再考すべきでしょう。スタッフを入れ替える必要性がありそうです。今日の株式相場の混迷の最大の課題は、市場全体のリスクが進み、世界で「流動性の罠」の状態が進み始めていますね。新興国からの資金の引き上げが、新興国通貨安を生み活性化を奪っているようです。
対策は設備投資減税を実施して、技術革新を促す投資活動を支援し、FRBは日本のように直接、株式や土地を買う行動も良いでしょう。本当は投資活動を支援する金利負担などが効果的に思えます。米国は日本と違い仕事ができる人が、上に行く仕組みです。そうして行動しなければポストを外される効率社会の市場原理の国だから、ここで書いた「流動性の罠」の問題への対策は、他の方法も含め議論されているでしょう。何しろ、一流の経済人が政策スタッフになっているから心配はしていません。市場原理主義の国です。1万ドルを割れれば、対策は待ったなしでしょうが…そこまで下がるかどうか…。
早晩、対策が発表されるでしょう。今回は日本の問題ではありませんね。コア30が下がっている所を見れば、相当、現金化は進んでいますね。つまりそろそろ売り物も切れると言うことです。切っ掛けは金融規制によるヘッジファンドの撤退などが引き金でしょうが、10年債などが買われており待機資金は豊富に貯まっています。方向性がハッキリすれば資金は新たに動きだすのでしょう。9月かな? フィラデルフィア連銀製造業景況指数の低下を見れば分かるように、株安による消費減少の逆資産効果現象が現れており、待ったなしの局面になっているようです。
需要なことは…現時点では人間の心理面だけの現象なのです。実態社会は多少落ち込んだ程度なのですね。天気が変われば人間の心はガラッと変わりますね。丁度、東京の気候のように…猛暑だった夏が何処かに飛んで、いきなり秋ですからね。金木犀が香る季節の到来です。実体経済は新興国の好調さが続いています。ファナックの稲葉発言は、当初は違和感を覚えましたが、ある意味で正しいのでしょう。どうもバイデン副大統領の訪中は、布石じゃないかな? 一般的には米国債の継続買いの要請と思われていますが、既に次の金融政策は決まっており、その事前準備と見るのが妥当でしょう。
何度も言いますが…日本はデフレ先進国で、空洞化問題を引き起こした先進国と新興国の産業移転問題で最も被害に遭ったと言うか…経験を積んだ国なのですね。だから日産のマーチがタイに生産基地を移し逆輸入しています。本来このような通貨高はマーチの価格引き下げで日本の消費者の利益になっている筈ですね。カローラとマーチの価格競争力は広がり、経営手腕を問われてもおかしくない状況の筈です。日産は値下げと共に、全面比較広告を出し、一挙に日本の低価格車のシェア拡大戦略を実行してもおかしくありません。
為替介入して輸出企業を擁護し雇用を守ろうとする旧態依然の行動は改めるべきでしょうね。どうせやるなら、一時的な期間指定(3か月から半年程度)を宣言し1ドル80円を維持し、その介入資金で金利の高いギリシャ国債やイタリア国債を買い、場合によれば、金利の低い米国債を売るべきでしょう。日本の金保有率は低いですね。その代りに介入外貨を使い農業や資源開発を進めればいいし、東アジアのインフラ整備を民間主導の補助金形式で促進すればいいのです。いくらでも日本が優位になれる行動があるのに…情けないな。円高は多くの手段を残しチャンスなのでしょう。
2011年08月06日
失われた理念
まずは皆さんが気にしているのはNY市場の動向ですね。
株価下落の背景は様々な要因が重なったのでしょうが、基本的に私はドルと言う基軸通貨を人質にしたことが、大きな要因の一つだろうと考えています。米国の連邦債務問題は前からあり、ティーパーティーは何も政府に求めない。ただ何もしてくれるな。…との要望で共和党を扇動したようです。しかしWSJなどの報道によれば、最後は敵対する筈の金融界が共和党議員を説得して妥協させたと報道されています。オバマ政権と米国金融界は敵対関係ですが、今回の事では流石に、金融界も妥協の動いたのですね。本文で書いたかどうか…ドルと言う基軸通貨が信任されない影響はこんなものではないですね。先ずはNY市場1万ドル割れ、と先週の何処かで述べています。だってリーマンなんて比じゃないですよ。金融危機どころではありません。世界中の金融機関が大きな損失を抱え、戦争か超インフレか何かで清算するのでしょう。それこそ1ドルが1円になっても…おかしくありません。
まぁ、前哨戦のような話です。市場はスペイン、イタリア問題まで発展していますが、両国ともギリシャとは違う意味合いがありますね。GDPの規模が違います。ユーロと言う準基軸通貨の存在価値が問われているのです。米国債の海外保有比率は40%程度、FRBが米国債を大量に買うと言うことはドルの信認が揺らぐわけですね。まぁ深く考えても状況は読めません。ただ言えることは、米国は日本と違い市場原理で動いている国だと言うことです。市場原理で動く国と言うことは、どういう事か? 常に市場により方向性を変化させる柔軟性があります。
日本の「失われた時代」が生まれた根拠は国民教育の歪みですね。自立できない国民を大量に作り出している教育制度やマスコミの報道姿勢です。最初、僕も官僚批判に明け暮れました。しかし長い時間を経て自分自身に問題があると考えたわけですね。既に株式営業などと言う市場原理を、制度も仕組みも放棄しているから、どんなに努力をしても食えないのです。食えないと言うは語弊があるかな? 辞める前の年収は940万だから、まぁ一般のレベルと比較すればソコソコですが希望がないのですね。辞めた理由の一つですが…市場の仕組みから自立したいと願ったわけです。
まぁ、この辺りは長くなるので省きますが、要するにここで言いたい事は、米国は市場が悪くなれば、必ず政策を修正します。だから心配ないのです。日本のような泥沼の傾向になっても、対策を打つのが米国経済で、フェアな基準があり優秀な人間が必要なポストに就いています。ガイドナーは失敗と言うか…結果的には事を急ぎすぎますね。金融を苛めるから経済がなかなか加速しませんね。車の両輪です。右だけを動かそうとしても左のタイヤが回らなければ、ぐるぐる同じところを旋回するだけです。日本のように…日本は過剰な金融規制の実施で金融機能が失われました。大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶから金融庁が分離され、竹中の強引な手法で内部が歪みましたね。だから先日の「規制から振興へ」の方向転換の行方が注目されます。
要するに米国は市場原理で動くので心配ありませんし、日本はバブル崩壊後の過剰規制によりもっとも清貧思想が進んだ国なのです。だから今回の立ち上がりは、理屈上、新興国でも、欧米でもなく日本から起こるのが資源の原理でしょう。テクニカルを多くの読者は好きですからね。おそらく昨晩のNY市場の上下400ドルのブレは、底入れの可能性が非常に高いでしょう。ただ出来高が物足りないが…この下げは昨日書いた金融規制からファンドが撤退する実弾の売りなので動揺しているだけの話。しかしこの動きは一時的で返還された資金は、またどこかで運用されます。マネーは溢れているのです。
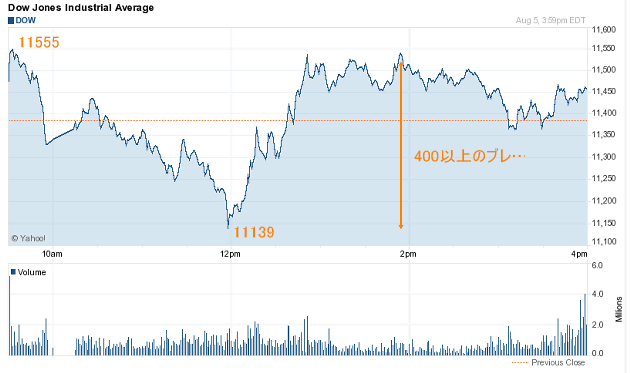
さて前置きが長くなりましたが…ここで理念の話をしたいと思います。
民主党が法案を通すために次々に妥協しています。本来、僕らは社会保障の配分転換を求め、民主党に投票しました。働く若者が20万円の中から5万円を払っています。ところが何も生産性のない年金生活者に、いや言葉が過ぎるかな? これまで貢献された人たちは、働かずに20万円をもらい、少ないとぼやきます。理屈上、4人に一人しか養えませんが、現状は3人も欠ける有様で、間もなく2人に一人の時代ですね。年金を減らし子育てに充てるのは当然でしょう。
先日、自民党の石破茂政務調査会長がテレビに出ていました。次期総理の呼び声がかかる政治家ですが、子ども手当の所得制限で年収の額の説明をしていましたが小粒ですね。政治家の器量が小粒です。960万とか細かい額の話をしていました。この発想は官僚的でみんなの意見を集約するために妥協を迫る考え方ですね。自民党時代、永遠と負の遺産の借金を積み重ねてきた妥協政治の延長線です。
岡田幹事長はまじめな人らしいですね。気持ちは分かりますが、理念がありません。民主党の子ども手当は日本の国の方向性を問う主眼ですね。妥協すべきものと違います。例え選挙で負けようが何をしようが、自分達の理念は曲げてはなりません。死んでも守らなくてはならない筋論ですよ。年金を削り子ども手当に充てるのが筋でしょう。だから国民総背番号制にして所得条件などを管理すれば、正当な運営を実現できます。本当に困っている人は生活保護とか別の制度がある訳で、年金生活を優雅に暮らしている人もいるわけだから、若者が20万円から5万円払っている苦労を思えば我慢は出来るでしょう。
所得の高い人は正義感も強く、多くの人は寄付もするでしょう。所得制限など設けずに子ども手当を出すべきですね。それが正論です。細かい手法に拘る石破さんは政治家じゃないですね。官僚的ですね。高額所得者に子ども手当が行くと言うのがおかしいなら、所得税で対処すべきですね。子ども手当は、子ども手当です。平等な筈ですね。民主党も政権を担い、いろいろ経験して分かったことでしょう。社会党や共産党の主張など子供の発想ですね。大企業や金持ちから税金を取れと言っていますが、その人たちが世の中を作り支えているわけで、その人たちが海外に逃げれば、日本はクレイマーだけの集まりですね。
先ず、理念を掲げる。その理念に向かい、目標を決め行動計画を立てて実際に行動する。上手く行かないなら改善し、常にチャレンジするわけですね。投資の世界も一緒ですね。私は証券マン根性が抜けないと嘆いています。上手く行かずに辞めた訳で、新しいチャレンジを始めましたが、なかなか確立されません。常に方向性を模索しながら闇を彷徨っている感じですね。ただ理念は曲げない。日本には正しい投資家精神が根付いて欲しい。だから無駄な努力を何年もしているわけです。