« 技術革新を促す規制強化 | 最新の記事 | 世代交代 »
推論(2011年08月27日)
米国のGDP統計が発表され、いくつか気付いたことは、ドル安にもかかわらず輸出は7.9の伸びから3.1%に大きくペースダウンしたこと。そうして意外にも民間国内総投資が3.8%から6.4%に伸びていたので、まんざら「流動性の罠」に嵌ってお金が動いていないわけではなく、QE2の効果はある程度あったと言うことを示しているような数字でしたね。やはり個人消費の影響が大きいのでしょう。2.1%から0.4%に大きくペースダウンしています。もう少しなのに…と言うイメージです。株高の資産効果は続かなかった。株価が異常に強かった昨年末の環境の景色を、GDP統計は物語っているようです。
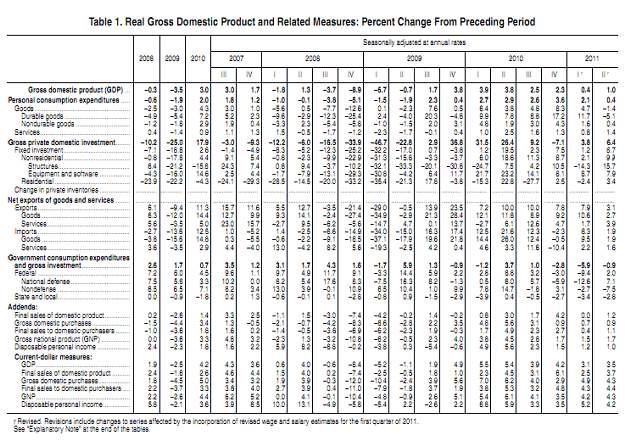
ここで分かるのは、私の推測であるアップルのようなファブレス企業が米国には多く、基本的にドル安による輸出増で、米国の雇用が確保されるか?…と言う疑問を、問題提起していましたが、GDP統計からも輸出が大きく減っており、オバマ大統領の政策運営が正しいかどうか…と言う、私の疑問を裏付ける統計値結果のような気がします。

さて昨日の宿題と言うか…。一つは米国の賃金上昇率の推移ですが、ここ数年間は伸び率が大きく減っていますが、米国はITバブル以降も消費が落ちずに元気でした。賃金が上昇しないのに消費が増えていたのは金融機能の影響ですね。住宅ローンの返済で余った枠が融資され、米国人はその借金で消費をしていた過剰消費〈ゾンビ消費〉の修正が必要だと言うのが分かると思います。40年と言う期間は長く、米国の労働者賃金の成長がなくなった原因の一つが、先進国から新興国に流れた産業移動の構図でしょう。所謂、空洞化問題ですね。別に日本だけでなく先進国すべてに共通している問題です。
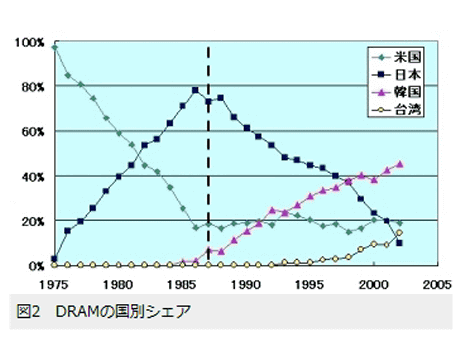
もう一つが1987年にピークを迎えたDRAM生産量の推移のグラフですね。私は日本の曲がり角をは1985年のプラザ合意だと思っています。DRAM生産の推移は、その考えを裏付ける資料の一つでしょう。もしあの時に産業構造を大きく変える挑戦をしていれば、失われた時代もなかったと考えています。「鉄は国家なり」『半導体は産業の米粒だ』と言う視野の狭い考え方がグローバル化に遅らせ、失った時代が続いている元凶だと推測しているわけです。
産業は軽工業から重工業に移ったように、生産性の高い分野へ常にチャレンジしなくてはならないのです。今日の日経新聞にはセラミックコンデンサーの記事が掲載されていました。半導体と同じ構図です。NECなどの社員がサムソンに行き、日本は諸条件〈電力料金や税制、TPPなどの経済政策〉の不利さで競争に勝てず産業構造が崩壊しました。セラミックコンデンサーも同じことですね。TDKはサムソンに敗れ…変化を迫られます。
このような現象を見て常に新しいチャレンジが、高いGDPを維持することに欠かせません。先進国から新興国の流れを米国の賃金上昇率のグラフやDRAM生産量のグラフから感じることが出来ますね。でも失望することはありませんね。ソフトバンクのパラソル戦略により日本は世界で一番、インターネット言う情報手段が整備されている国で、物流システム構築されています。ITS(高度道路交通システム)の整備は進んでいます。これらの情報化の社会基盤設備を利用した産業が興るのです。インターネットは産業革命と同じなのですね。
米国の賃金上昇率のグラフを見て…世界は産業革命の位置にいるのだろうと考えています。今は時代の激戦地帯で、大きく変化しています。日本はスマートフォンの普及率でも世界で先端を行っているでしょう。GPS衛星の予算が付いたそうですが、早く24時間体制にすることが必要ですね。産業構造が一巡し震災を切っ掛けにスマートシティー構想を大きく推進させれば、人類の情報化と言う産業革命競争の先端を走れます。電力・ガス・水道の見える化は、人間の意識変化で新しい産業が乱立して、物から情報などへ価値観が大きく移行する時代が幕開けするのでしょう。
さて昨日掲げた二つのグラフから、カタルはこのように考え方を発展させてきました。バックボーンがここにあるから、銘柄選抜はその流れから選ばれることになりますね。バーナンキは昨日QE3に言及はしなかったが、含みを持たせ市場を先導することに成功したようです。「言葉の魔術」、人間の感情って、面白いものですね。