« 2011年09月 | メイン | 2011年11月 »
2011年10月29日
金融はアイディア次第
残念ながら、日本には人がいないなぁ~。政策担当者に能力主義を取り入れていないから実行能力が乏しいのでしょう。復興法案を見るとなかなかうまくできていると思います。ただ昨日、NHKニュースで1兆数千億円の予算が高台移転などに充てられるが、その予算の使い道は限定されており造成費などにしか使えず、個人用地の買収価格に充てられず、しかもその海抜の低い土地は地価が下がっており、この形態では思うように移転が進まないと報じられていました。ニュースの対象は南三陸町でしたね。
しかし未来都市建設をすれば海抜の低い地価も高く買い入れることが出来ますね。大手デベッロッパーに相談されればいいでしょう。また高台の用地が足りないと言われていますが、高層ビルを建てて低いところは5Fぐらいまでは商業地域にして高層階を住宅にすれば津波にも耐えられますね。5年間の税制免除の特例が付けられ大手企業も参入しやすく、漁業権の問題もクリアしているようです。
この機会に世界中の水産会社が競うような大規模の漁業会社の設立を考えればいいですね。雇用も水産加工で賄えるし…GDPも増大されますね。商社と組んでアジア各国への水産物の輸出基地にして、マグロの養殖なども盛んにすればいいのです。問題は民間企業をまとめる総合力です。こればかりは大手デベロッパーと行政がイニシアチブをとらないと纏まらないでしょう。なんでもかんでも国に頼るやり方ではなく、自ら、努力して事態を打開しなくてはなりません。お金など腐るほどあります。要するに民間企業の資金を出しやすくして上げればいいのです。年金基金は1%にしかならない国債を大量に買っているのです。収益5%を約束すれば、いくらでもお金は集まります。我が国の食物自給率を引き上げるチャンスでもありますね。野菜工場を含め農業革命を興せばいいのです。塩害に強い作物もあるでしょう。何も米に拘らなくても良いですね。関係者はぜひ頑張って努力してほしいものです。
さて株式です。金融と言うのはアイディアなのでしょう。要するに市場の歪みを見つけその歪みを修正させることで、復元力を使い儲けるのでしょうね。一例を掲げましょう。どんなに悪い企業業績が予想されても、一度、株価に織り込めば必ず株価は修正波動に動きますね。現在の局面はそうですね。ここではエレクトロンを材料に(今日の市況で使っていますから、)この事例を元に解説しますが、全ての銘柄で同じことが言えます。一番底は8月26日、二番底は10月4日でしたね。現状は25日線と75日線がゴールデンクロスしており高い乖離の状態ですから、株価はどうしても調整を欲していると思いますね。
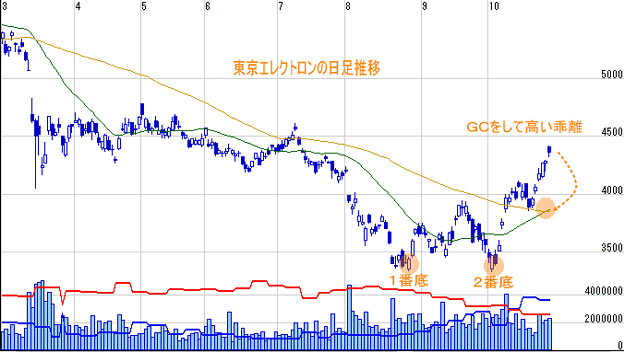
代わって、相場はおそらく出遅れ修正に向かうでしょうね。225銘柄で、未だにマイナス乖離の大きな銘柄はたくさんあるでしょう。そのリストは下ですね。オリンパスは除外です。これらの業績に不安を抱える銘柄も株価が修正されることでしょう。ただし今は戻ったところだから、あわてて買ってはダメですが…押し目を狙えば良いでしょうね。例えば商事かな? 資源関連の銘柄は良いと思いますね。昭和シェルなども挙がっていますね。下の方の安川やTDKは最近人気になりましたね。もう少し早く原稿を書けばよかったかな? 帝人なんかも挙がっていますね。まぁ、基本的に僅かですが戻るでしょうね。
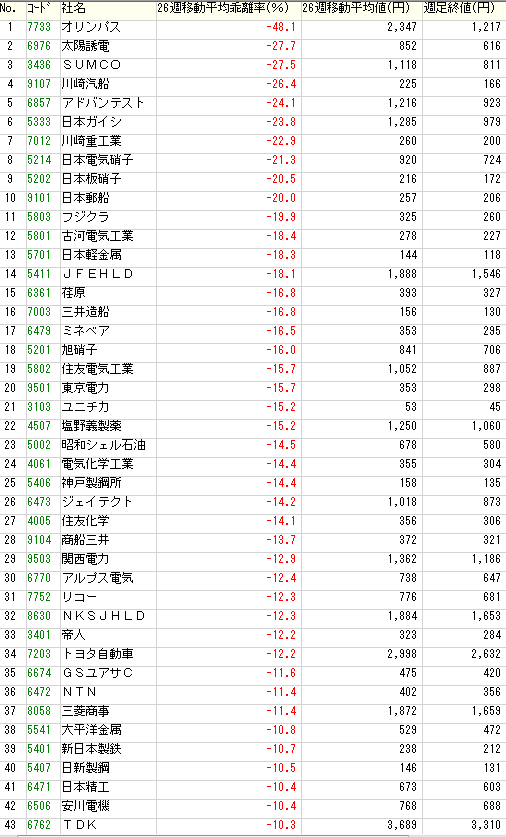
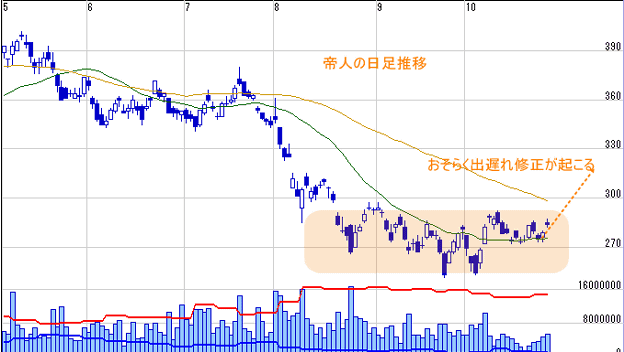
ここで言いたかったことを、要するに金融はアイディアが勝負だと言うことです。それも独創的な考え方が利益をもたらすのでしょう。どう考えても8月の9月の段階でエレクトロンなど考えませんね。半導体市況は最悪の状態だし…でもエレクは裁定などの銘柄に広く採用されているコア銘柄なのでしょうね。だから日銀がEFTを買うと必ず組み込まれ外人が先物をヘッジするから取り組みが改善し仕手化しているのでしょう。この理屈に早く気付いた人が儲かるわけです。この考え方は今日の市況の何処かで僕は述べていましたね。多くの銘柄で空売りが増えていると…。
本当は日銀が5兆円ではなく50兆円単位でリートやETFを買えば良いのですね。リートは発行量が限られるので、高くなれば利回りが低下し、新規のファンドが設定され実際に地価が動きますね。理屈上はそうなのです。ETFも同じで株価がドンドン上がると個人消費が伸びますよ。日銀の資産デフレ対策は正しいが、500兆円以上のGDPの国で1%の増額では政策効果はほとんどありませんね。それも国債購入で過去に使ったお金に費やされます。国債を購入することは死に金ですね。復興債への新規購入なら分かりますよ。それも償還間際の残存期間の短い国債の購入です。
日本の輸出依存率は、既に14%程度だったかな?…それぐらいなんだから、国際批判なんか関係ないですね。ドイツはたしか34%程度の筈。ガンガン円売り介入をしてその外資で日銀が資源の鉱山会社や、食料の食物会社を買い占めれば(例えばカーギルを…)円を買うのは、日本人に有利になるから止めようと言うことになりますね。だから規模は小さいが…「円高対応の金融ファシリティー」は有効なのです。でも規模が小さすぎます。日本のGDPは520兆円ほどありますから、最低でも1割程度は実行しないと世界は変わりませんね。政策とは驚きがないと駄目です。そうして行き過ぎたら、また修正させればいいのです。それを…やる前から副作用を考え行動をしない。TPPも同じですね。
2011年10月22日
アルゴリズムについて考える
今日は僕自身の知らない「アルゴリズム投資」について考えてみます。
ディトレをやってみると分かりますが、板状況が見えるようになり、株価が動くと途端に買いが入ったり逆に売りが増えたり、板状況の注文は株価が動くと瞬時に気配値が変わることがよくあります。人間心理とは面白いもので、売り板、買い板が厚いと流動性があるから安心するのですね。しかしその多くは見せ玉の可能性があります。所謂、買う意思がなくても買い注文が入ったり、売る意思がなくても売り注文が入ったりするのでしょう。
どうも株価が急激に動く背景には、この自動化された売買システムが株価変動に大きな影響を与えているようです。現在の法律ではこの投資方法は規制されておらず、米国でも度々問題が表面化しています。2010年5月6日、NY市場は前日の10868ドルから急落し一時は1000ドルを超える下げになり9787ドルまで下落し、引けは348ドル安の10520ドルとなりました。その時にターゲットにされたのが、P&Gと言う大企業でした。前日の株価は62ドル16セント、ところが、翌日は一時、株価は39ドル37セントまで売られます。結果、引けには買い直され60ドルと75セントになった現実があります。この背景にはこのアルゴリズム投資が影響したと言われています。
しかし、調べましたが実態は分からない事として発表されています。最近ではドイツでも同様の事例がありました。このような売り買いが、世界で何度も問題を誘発しています。日本の場合も、最近では東京電力にこのアルゴリズム投資が関与したのではないかと疑われていますし、最近人気になっているオリンパスも同様の疑いがあります。それではこのアルゴリズムとは何か? 少し考えてみます。
株価は業績数字を基準に算定されています。しかし最近では長いデフレの影響もあり、更にブルドック事件などの企業統治の問題から、グリーメラーの否定などの影響もあり、M&Aの概念が働きづらくなっています。本来、PBR1倍割れは、会社の解散価値の筈ですが、黒字で配当もしているのにこの基準値を大きく割れこんでいる企業が多数存在します。それならばTOBを掛けて会社を解散させ、資産を売却すれば儲かりますね。ところがブルドック事件や、日本の風土がこの動きをけん制しています。だから株価は需給により上下する紙くずのような存在になっています。すこし極端な表現ですが…。
このような背景環境があり、色んな条件を過去のパターンから探し出し、売り買いを自動的にするコンピュータの存在が出てきます。25日線のかい離率がプラスの銘柄を選び、尚且つ出来高が増えている銘柄とか…最近では様々なテクニカル指標が開発されており、スロースキャスティクスやPSI、RCI、DMIなど数え上げればきりはありませんが、そのようなものと連動したり、板状況を把握し発注株式数を調整したり高度化されて動いているようです。しかし多くのアルゴリズム投資は順張り投資ですね。基本的に現状の流れを追認し、流れを加速させる方向性にあります。
だから寄り付きの動向が重要になります。概ね、大幅高する株は寄り付きに買い気配スタートすることがよくあります。トレンドを変えるためには目先の売り玉を全部、拾う必要があります。概ね、株価の3%程度の売り玉を買ってやれば、目先のトレンドは変化しこのアルゴリズムを利用した投資が追認し始めて新しいトレンドが形成されます。先日のオリンパスはまさにそうです。午前中は保ち合いを維持し株価は比較的強かったけれど、後場から値崩し的な仕掛け売りが入ると、次々にプログラム売買が作動し、(ストップ・ロス・オーダーなども含め)瞬時に株価が崩れていきますね。
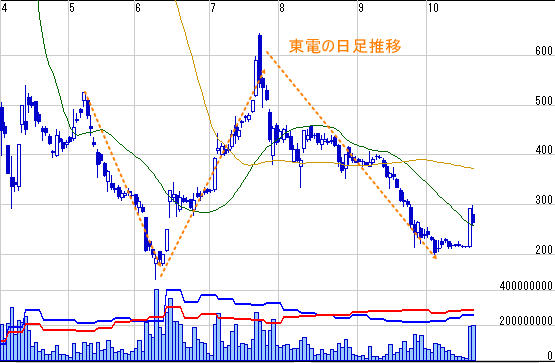
市場に流動性があるときは、不特定多数の参加があるときはこの傾向は薄れますが、今年に入ってからの東京電力などはこの動きで加速され過度に株価が崩れていきました。同じことが現在、オリンパスでも起こっているようです。僕のように会社の企業価値が変化しないのに株価が上下にぶれるのはおかしいと感じ相場に参加する人は既に少数派で、大多数が目先のトレンド売買をしているわけです。本来あるべき株式の資金調達市場としての資本市場が歪んでいる実態のように感じます。この手の売買を規制する必要があるのではないかと思われますが…市場は開かれるべきで僕は規制に反対の立場です。要するに株式市場の参加者層が極端に細っており歪んだ株価形成になっていると言う事なのでしょう。
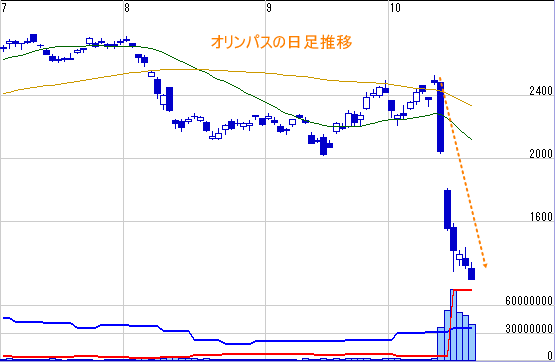
アルゴリズム投資は人気株に集中しますから、既存の株価概念が大きく変化する可能性があるのですね。東電が急落したように、市場は何が起こるか分からないから、過去の経験に基づいた考え方に固執するのは危険なのでしょうね。今頃気付いても遅いけれど、カタルも充分、失敗の反省を強いられているのです。
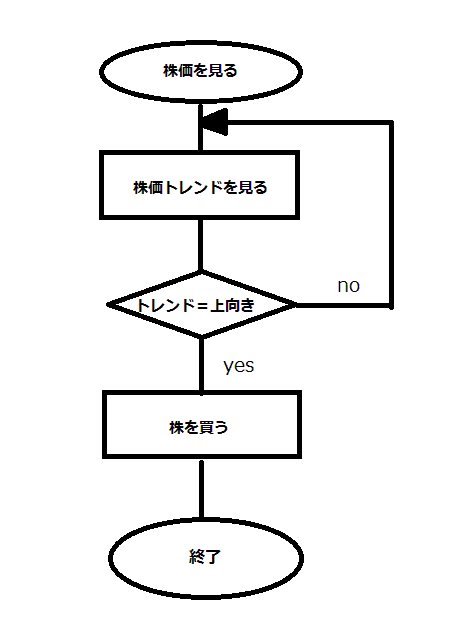
2011年10月15日
チタンを例に…
今日は少し専門的な解説をしましょう。実は僕も手探りの状態で分からないのですが…ただ僕が踏んだ手順を、皆さんは省くことが出来ますね。要するに勉強とは先人が積んだ教えで、先輩から学ぶことが出来れば、その分、試行錯誤の操作をする時間が省け、効率的な時間が使えると言うことです。
だんだん、日本も本物志向をするようになってきましたから、東大法学部なんかより経験を積んだ価値、キャリア(実績)に重きが置かれるでしょう。しかし…記憶力は、一つの能力の基準なので、馬鹿に教えるより、頭のいい一定の基準以上の人にレクチャーした方が楽だし効率が良いから、大企業は学閥を一つの選考基準として採用しているのでしょう。しかし人間で一番大切なのは「やる気」ですね。モチベーションが高い状態をどの程度、続けられるか? だから「好きこそものの上手なれ」との諺があるのでしょう。
ごたくは兎も角、かたるは金融危機以降、金融がやられると実体経済の回復が、非常に手間取ることを日本の事例で痛いほど学んでいます。加えて日本は捨てる文化を持ちません。狩猟民族ではなく、やり直す機会が仕組み上、構築されていませんね。だからなんとか頑張ろうとして無理をするから痛手が深くなります。その現象が2003年の金融危機で「みずほ」が10万円を割れ、53000円まで下がった現象ですね。この時に強引に、ミルトン・フリードマンの小さな政府の効率化論理を無理やり日本に導入したのが、小泉・竹中改革です。だから摩擦が生じ、2006年からの逆襲に遭いました。最高裁から経済界まで…すべての分野での揺り戻し政策です。
今も九州電力を巡り既得権勢力との戦いが続いていますね。東電の処理もそういう事が背景にあります。僕はどちらかと言えば、竹中改革もやり過ぎを主張し、論旨は理解できるし方向性は一緒だが、手順が違うと考えていました。同じことが、今回の枝野さんと電力業界で起こっていますね。2003年から2006年まで続き、巻き返しが起こり、そうして再び権力闘争が行われています。ただ「円高対応金融ファシリティー」の評価は低いですが、あの政策は素晴らしく…確実に企業間に定着し始めていますね。ユニクロのNYへの5番街進出など、ほんの一例です。ようやく日本企業はグローバル化に大きく動き始めています。トヨタはまだですが…だから前にトヨタと日産の比較を行ったのです。
しかし人間の感情は不思議なもので市場は大きな間違いをしています。我々は何度も、トヨタは日本、いや世界一の製造業だと言う誤った認識をインプットされたために、消去できないのですね。ルネサンスエレクもそうですね。企業経営者自らが改革できないのです。世界シェアNO1でもそうなのです。一つを解説すると…派生が長くなっていけません。
今日は最近、拘っているチタンの話です。チタンの解説は省きます。ネット上で探せばいくらでも転がっていますから…。
先ほどの話ですが、全体相場が盛り上がるためにはGDPが世界第二位の中国の政策転換が欠かせません。しかし残念ながら中国のCPIは6.1%と、予想通りの数字で下がらず、年内の転換が微妙になってきました。曇り相場の、晴れ間を狙え!と言う意味は、全体の相場は駄目だと言うことです。先ほど少し解説しましたが、日本は確実に変化しており、僕には長期波動に入ったと言う確信が育ち始めていますが、多くの人はまだ感じないでしょう。この長期軸ではなく、短期軸の注目点は、米国より中国です。米国は依然世界一のGDPを誇り、消費も世界一ですが…金融が痛んでおり完全回復まで、まだ時間がかかります。GSEの住宅関連処理の目途がつくまで、正常な歩みを続けるのは無理ですね。だからデッカプリングが世界を救うしかないが、欧州危機から新興国からの資金の引き上げがあり難しい。
故に晴れ間を狙うゲリラ相場なのですね。
そこで業績推移を考えるとチタンしかないのですね。航空機市場は受注残が非常に多く将来性も明るいし、更に増産の方向性にあります。石油価格は高止まり、WTIは指標じゃないですよ、北海ブレンドです。日本はドバイですが…海水の淡水化プラントも好調な筈ですね。ただ問題は為替だけですね。そこで10月初旬に終了したチタンの価格交渉が注目されますが、僕には調べる気もないし会社側も教えてくれるかどうか…。アナリストなら既にレポートを出している筈ですね。出てないと言うことは、証券界が3流の集まりだと言うことです。今、最も注目される業界の筈ですね。
日刊工業新聞のインタビューで東邦チタンの社長は、3月まで50%で4月から75%に上げ、下期には100%操業、来春に130%操業と増産予想を述べていましたね。あとは価格だけです。チタンの相場は金融危機の影響で低迷しており30ドル前後だったのが、7ドル台まで下げていましたが、現在は回復過程で12ドル台に上がってきています。ところが株価は既にかなり高評価していますね。東邦チタンなどは赤字表明したばかり、大阪チタンにしても株価はPER40倍近い評価です。この株価は正当な評価かどうか?
だから実験なのですね。環境は素晴らしいし業績面の裏付けも問題ないが、市場評価は割高じゃないかと言う不安が、常に存在します。だから株価が半値になるほど、今回は急落したのです。しかし多くの市況ものは現在高値圏で金も石油も高い位置ですが、これから需要期を迎えるチタンの相場は下値圏です。世界に良質のチタンを供給できるのは日本だけ。ここに外人が魅了される理由があります。何でもそうですが…製造業にとって操業率は非常に重要なファクターです。設備投資負担があり概ね80%程度の操業度を維持できないと赤字になります。加えて円高なので…。
そこで日刊鉄鋼新聞に次のような記述を見つけたので…この裏付けを取る為に調べたのですね。「スポンジチタン、輸出が急増。航空機向けが回復
財務省の貿易統計によると、今年1~7月累計のスポンジチタン輸出量は前年同期比22・2%増の6276トンとなった。単月では、7月に前月比36・5%増の1135トンと2カ月連続で1100トン超の高水準を持続した。直近では、06年のスポンジチタン輸出量が1万2千トン超の過去最高を記録しているが、6、7月とも年率換算でこれを上回る急増となった。」となっていました。
だから財務省の貿易統計に飛んでHSコードを調べたのです。でも数字が違うのですね。この記事と僕の調べた内容と…どうしてかな? だからHSコードを間違えたかと考え、再び詳細に見ると…この解説(http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/81r.pdf)に行き当たり、やはり僕は間違ってないのかな?と感じています。財務省の統計で調べた数字が下の表です。国別の輸出量も分かるのです。ただ価格交渉は1割より上の水準らしいですね。2割に満たないらしい。価格交渉は不満ですが、操業率が、今までは50%だったのが4―9月期は75%で、10月以降が100%とコメントされており業績の変化率は劇的な筈です。
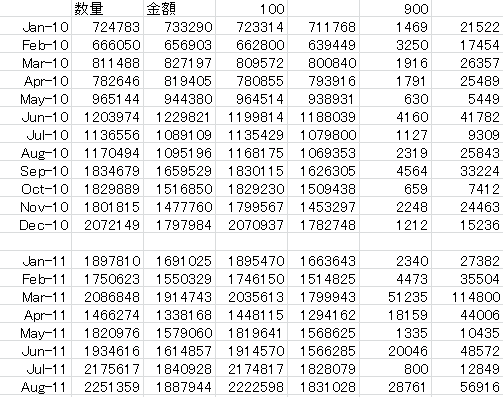
こんな事が分かっていたから、ずっとチタンを言い続け、4800円の大阪チタンを買い、そうして損をして投げていたわけです。その相場が6連騰で反転したわけです。僕がチタンに行く過程はB787の就航です。ようやく始まった生産ですね。増産投資をしてジャムコも赤字を継続していました。でも東レは他の分野も強く堅調ですね。一つの発言が他の分野に影響し、一つの記事の裏付けを取る。でも確かめられなかったので、本当は財務省に電話取材し、メーカーに問い合わせるのが正しいレポートを書くやり方でしょうね。
後はタイミングの問題ですね。ただ市場が「効率的市場仮説」を裏付けているのかどうか明らかではありません。つまり方向性が株価に反応するとは考えられないのです。欧州危機でギリシャ問題が再熱し発火する。全体のシステマチックリスクが増大し、どんなに個別の材料があっても半値に水準訂正を強いられました。でもLTEのアンリツは高値を維持しています。LTEも確かに良いが、所詮、測定器の地味な分野です。この辺の評価が問題になり、加えて市場全体の物色の流れも問題になります。
中国が政策転換すれば、こんな小さな株より他が良いでしょうね。何故なら、大きなお金が動くからです。今は曇りの合い間を狙った青空相場、つまりゲリラ戦。だから007も物色の対象になると考えたのですね。そうして僕が金曜日に玉を一旦外したのは、市場がこのアイディアに気付き始めたからです。市場から評価を受けると言うことが、認知されつつある訳です。先ほどのストリーが…。故に株式教室で書いたのですね。これで充分に伝わっているかどうか分かりませんが、ヒントにはなるでしょう。しかし株は一筋縄ではいきません。ましてや変動率の高い銘柄です。DENAは素晴らしい会社だが、今は完全に調整していますね。まだ調整過程でしょう。世間から認知を受けるとフルイを入れるのが筋ですね。
ただこの筋論が最近は狂っているから見えにくいのです。お金があれば問題ないのですよ。株の世界は資金力の世界なのです。無限にある手段を持っている日銀が負けている現状はおかしいね。昨年の10月に政策転換し資産デフレ対策を実施したのですから…。相場解説は兎も角、今日は試行錯誤の一例を掲げました。
787の就航を見て、世界情勢を考えればBRICsは人口が多く交通量が増大します。当然、航空機の需要が増えることはあっても減りませんよ。しかし世界で増産できるところは日本しかない。株屋なら絶対に見逃さない現象ですね。市況を見れば(これは参考値)30ドルまで大きく届かないと言うことは…値上がりの余地が大きいと言うことですね。3倍になると考えても不思議ではない。ピーク時の話ですよ。のり代があるかどうかなのです。デッカプリングは航空機の需要に重なるのです。
サルにも分かる論理ですね。
でも上がったから売ったのですが、また下がれば買いますよ。今日はチタンで解説しましたがエレクにも同じ論理があり、エルピーダに注目しているのもデカップリングの動きに連動するのですね。スマートフォンは水晶発振器の需要を押し上げ、おそらくWIFIの技術を必要とするでしょう。故に007と村田の提携の行方も注目されるのです。でも赤字ですね。先日、僕はマツダを空売りし、持ち上げられ損切りしましたが、やはり為替問題で赤字が確定し売られています。しかしマツダは素晴らしい会社なのですね。だから条件が変われば、仕掛け人が存在しますから、大きく跳ねる可能性を秘めています。でも今は駄目かな?
9月の米国の自動車販売、同じく中国も久しぶりの164万台の数字で好調ですが、此方は駆け込み需要ですね。材料を吟味する必要性がある。この吟味と相場観とテクニックの3つが揃わないと儲かりませんね。頭の中身を書くのは難しい。どの程度、理解されたかどうか…今日は長くなりましたので、もうやめにします。株を手掛ける裏には、単にチャートだけの話しでなく、沢山の要素が存在すると言うことです。
2011年10月08日
世界競争における価値観の変化
昨日、先輩から「6日木曜日の大機小機」を読んだ?…と聞かれました。僕は読んでなかったので「いいえ、後で読みます。」と応えたが…彼女が、何故、僕にこの事を指摘してきたのでしょう?
この記事の内容は米国のHPの話で、世界最大のシェアを誇るヒューレット・パッカードが、何故、パソコン部門を分離するのか?と言う話、その理由は売上営業利益率が5%に留まるから不採算部門だと言うのです。日本の多くの製造業はこの水準に届いてないからPBRが1倍を割れていても仕方がないと言う内容です。
製造業の代表格のトヨタは7~9%の間をキープしてきましたが、ここ数年低迷し前期は2.4%で、今期予想は2.8%でしかありません。つまり世界基準から脱落しているのでしょう。円高など言い訳に過ぎません。一方、同業の日産自動車は同じ時期、7~11%で推移してきましたが、この時期やはり低迷しましたが、現在は前期6.1%で今期予想は5.2%です。下は上段がトヨタ、下段が日産です。
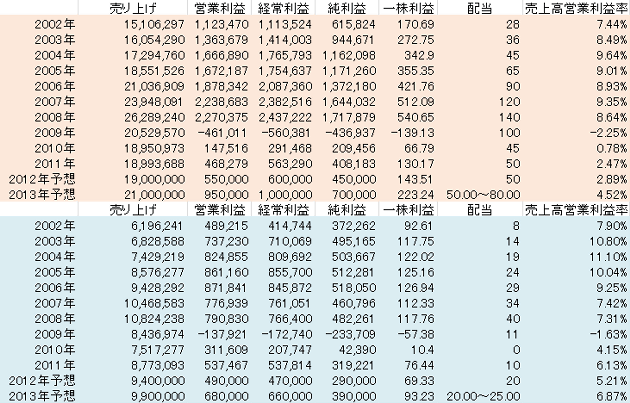
日本的なトヨタの経営者とグローバルな経営者の違いを感じています。多くの企業はトヨタの価値観を有し、国内シェアに拘ります。先日、ミスター半導体と呼ばれた日立の牧本常務の話をしました。1996年の話で、当時、日立の社長からの話で「東芝に負けるな」と国内シェアに拘った話を紹介しましたね。その後、日立は凋落し、最近、中西さんの下で変化しています。同じ日立傘下のルネサスも、世界シェアNO1の会社ですが…なんと赤字計上を続けています。
会社と言う価値観が世界基準と日本では違うのですね。私は何度もフジテレビの日枝さんや新日鉄の三村さんの話をします。上場企業を私物化していると批判しているわけです。堂々と戦えばいいのです。素晴らしい経営者なら引く手数多です。ガレージからベンチャー企業を興し、今年8月世界一の時価総額を達成したアップルのスティーブ・ジョブズ氏がこの世を去りました。ひたすら自分の感覚を信じ、途中であきらめない心が成功の秘訣だそうです。
冒頭のHPの話は、株式と言うリスクマネーで集めたお金に対し、5%程度のリターンでは経営者は失格だと言う事なのでしょう。ただ益利回りが20%を超える現在の株価水準を見ると、やはり日本株もかなり安い水準だな…と感じる次第です。益利回りはPERの逆数ですから、PER5倍と言うことは20%と言うことです。僅か5年で投下資本を回収できる企業はゴロゴロしています。下の表は日経平均採用企業のものです。
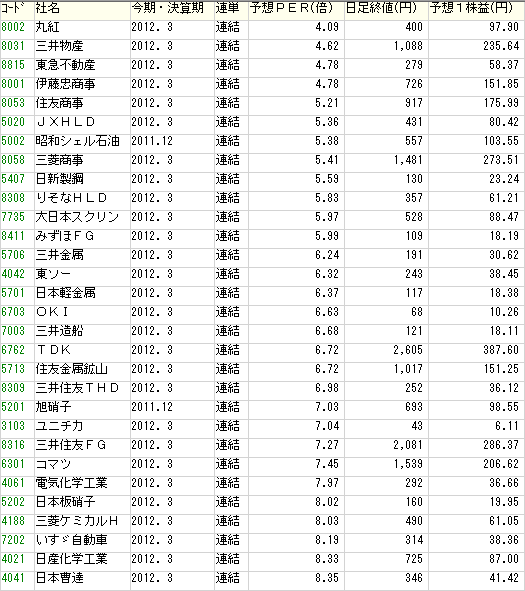
2011年10月01日
歴史的な視点
今日は少し長期的な視点で、ものを考えてみたいと思います。
1985年までのNY市場は、ほぼ横ばいの動きで日本株の1/10ぐらいの株価でウロウロしていました。つまり日本の日経平均株価が1万円だと、米国のNYダウ平均株価は1000ドルだったのです。でも1985年プラザ合意を境に上昇波動に復活します。私は当時、証券界に居ましたが、残念ながら小僧で、あまり良く経済環境を知りませんでした。ただ1984年1月から銀行株が暴騰し、金融相場に移行し5年にも及ぶバブル相場に突入しました。
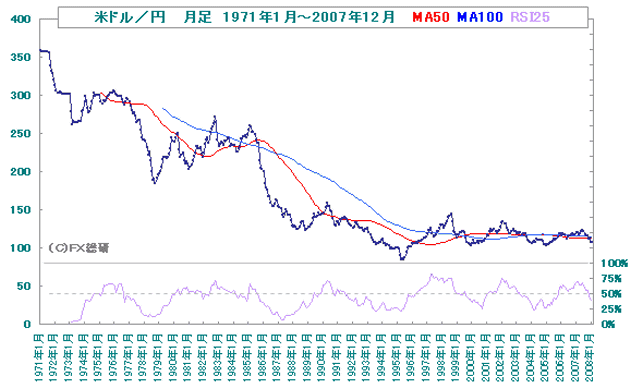
1971年8月15日にニクション・ショックと呼ばれる金本位制が崩れ、その後の為替レートを変えてスミソニアン体制に移行しましたが、僅か2年で変動相場制に移行しました。1980年12月日本の外為法改正により、資本取引が活発化しドル投資が進みドル高時代を迎えますが、米国における双子の赤字問題(財政と貿易)が切っ掛けになり、プラザ合意へ移行しました。日本の凋落は、そもそも世界の通過体制が激変したのにも拘らず、国内生産に拘った戦略の誤りが「失われた時代」を招いた元凶だと考えています。
しかし米国はこの流れを利用しグローバル体制を構築していたので、成長を続けることが出来たのでしょう。日本の低迷と相反するように、米国は金融危機が起こるまで成長を続けています。どうも歴史的な推測からすれば、そろそろ第二幕が始まっているのかもしれません。最近よく考えるのが、国際通貨体制の問題で、基本的にはグローバル化が進み、国際会計基準の進展で株式も通貨も世界統一される方向性にあると感じています。現在はドル基軸体制でユーロと円や元に分かれていますが、ギリシャ危機は、どうも通貨統一の予行練習のような気がしますね。
1985年から1989年までの4年間は円高対策に揺れ動き、日本の政策は選択の失敗を繰り返しました。まるで僕の株式投資のようです。やはり歴史観と言うのは大切ですね。1983年ごろに米国の株価が上がりだします。それまでは米国は1000ドル以下のボックス相場を20年程度も続けています。一般のチャートでは分かりにくいので、長期の対数チャートを用いると変化が分かりやすいですね。1985年からITバブルまでが米国の黄金期ですね。この時代に米国で何か起こったか?
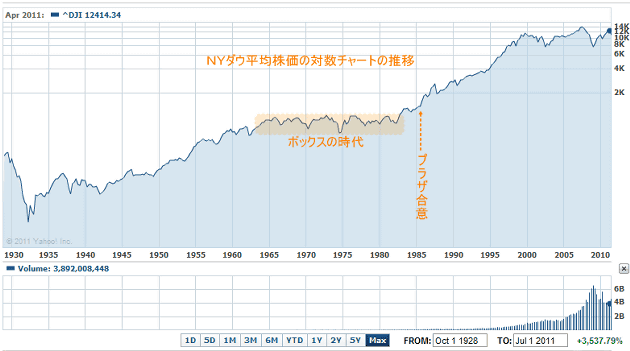
おそらく先端技術の開花です。もう少しグローバル感覚があり英語が理解しておれば、僕もひょっとしたら、アスキーと言う会社に馬鹿になっていた時、日本を超えてマイクロソフトに投資し億万長者になっていたかも知れません。当時、僕は和光証券に在籍しており米国株を買おうと思えば買えたのですね。知識とは…、情報とは…どれだけの価値があり、使い方次第で運命を大きく変えるものです。
マイクロソフトが1983年11月に「Windows」を発表し、アップルは「Macintosh」を12月に発表しています。そうです。NECが98パソコンを発売したのが1982年10月です。ここが勝負の分かれ目です。
この時代の大統領はレーガノミックスを実践したロナルド・ウィルソン・レーガン大統領です。レーガノミックスの概要は…1.減税により、労働意欲の向上と貯蓄の増加を促し投資を促進する。2.福祉予算などの非国防支出の歳出削減により、歳出配分を軍事支出に転換し強いアメリカを復活させる。3.規制を緩和し投資を促進する。4.金融政策によりマネーサプライの伸びを抑制して「通貨高」を誘導してインフレ率を低下させる。…と言う一般的な景気刺激策を実施しています。
レーガンの前政権のジミー・カーター時代はスタグフレーションに苦しんでいましたから、現在の日本とはだいぶ事情が違います。どうもコンピュータの一般化するパソコンの技術革新時代と規制緩和による投資促進が基礎を作り、プラザ合意で更に経済が加速した印象を持っています。
現在の米国株はどっちにしても横這いか、下がるかの狭間で揺れ動くのでしょう。何故なら、金融危機で金融機関が痛んでいるので、直ぐに立ち上がる体力も乏しいと思います。しかし日本は1989年から、一貫して緊縮体制を維持してきました。今では、まるで金融機関の体をなしていません。預かった資金を国債に投資するだけの金融魂が失われた抜け殻状態ですね。そろそろ変革が起こっても不思議ではありません。ここで、この20年の日米の株価を比較してください。
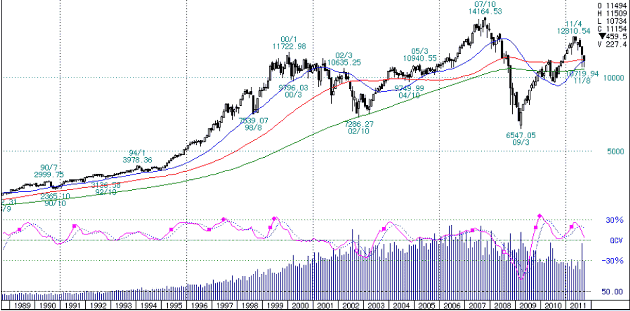
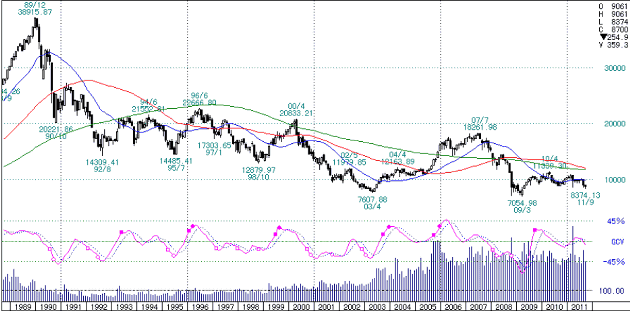
大切なのは基本理念。
産業界の技術革新と政策、環境がマッチしないと、なかなか泥沼から抜け出せませんね。でも今回の先進国と新興国の覇権争いと言うか…、時代変化は日本にとっては歴史的なチャンスに見えますね。そうして、この震災です。このワクワク感は僕だけが感じているのでしょうか? 日米の株価は相対関係にあるように見えるのは偶然でしょうか?
先日の円高対応緊急ファシリティーの創設は、後追い政策ですが優れた政策です。日本企業のグローバル化は加速進展し、今年は4-9月期に昨年比2.2倍の3兆円規模だそうで、バブル期に匹敵するそうですね。この円高を利用し日本企業が支配する市場を2倍、3倍に増やせるかどうか…。JTの株価の堅調さはある意味でM&A戦略による成果とも言えます。ただ必ず成功するわけではなく痛い目にもあっていますね。古河電工がルーセントテクノロジーを買収しましたが、これなどは失敗例でしょう。
日本と言う国の市場規模を基本とするのではなく東アジアと言うアジア圏を一つの市場として行動できるかどうか…この辺りに成否がかかっているように感じますね。日産自動車のタイへの生産移転はその流れに合っていますね。僕はタイよりベトナムの方が北米にも有利に働くように感じますが、何しろ政治の意向もありますからね。どう考えてもTPPの早期妥結は必要条件のように感じます。
どうも今日のレポートは的を得ていませんが、歴史的な出来事を振り返り現在を推察すると言う作業はなかなか価値がある視点だろうと感じています。結論は出ていませんが皆さんも一度、歴史を振り返ってみたら如何でしょう。