« NHK深夜便 | 最新の記事 | 世界競争における価値観の変化 »
歴史的な視点(2011年10月01日)
今日は少し長期的な視点で、ものを考えてみたいと思います。
1985年までのNY市場は、ほぼ横ばいの動きで日本株の1/10ぐらいの株価でウロウロしていました。つまり日本の日経平均株価が1万円だと、米国のNYダウ平均株価は1000ドルだったのです。でも1985年プラザ合意を境に上昇波動に復活します。私は当時、証券界に居ましたが、残念ながら小僧で、あまり良く経済環境を知りませんでした。ただ1984年1月から銀行株が暴騰し、金融相場に移行し5年にも及ぶバブル相場に突入しました。
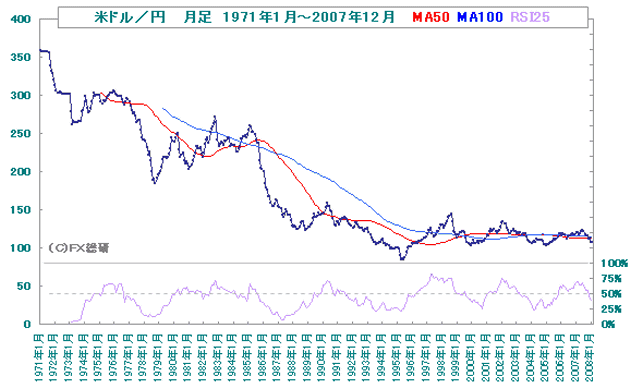
1971年8月15日にニクション・ショックと呼ばれる金本位制が崩れ、その後の為替レートを変えてスミソニアン体制に移行しましたが、僅か2年で変動相場制に移行しました。1980年12月日本の外為法改正により、資本取引が活発化しドル投資が進みドル高時代を迎えますが、米国における双子の赤字問題(財政と貿易)が切っ掛けになり、プラザ合意へ移行しました。日本の凋落は、そもそも世界の通過体制が激変したのにも拘らず、国内生産に拘った戦略の誤りが「失われた時代」を招いた元凶だと考えています。
しかし米国はこの流れを利用しグローバル体制を構築していたので、成長を続けることが出来たのでしょう。日本の低迷と相反するように、米国は金融危機が起こるまで成長を続けています。どうも歴史的な推測からすれば、そろそろ第二幕が始まっているのかもしれません。最近よく考えるのが、国際通貨体制の問題で、基本的にはグローバル化が進み、国際会計基準の進展で株式も通貨も世界統一される方向性にあると感じています。現在はドル基軸体制でユーロと円や元に分かれていますが、ギリシャ危機は、どうも通貨統一の予行練習のような気がしますね。
1985年から1989年までの4年間は円高対策に揺れ動き、日本の政策は選択の失敗を繰り返しました。まるで僕の株式投資のようです。やはり歴史観と言うのは大切ですね。1983年ごろに米国の株価が上がりだします。それまでは米国は1000ドル以下のボックス相場を20年程度も続けています。一般のチャートでは分かりにくいので、長期の対数チャートを用いると変化が分かりやすいですね。1985年からITバブルまでが米国の黄金期ですね。この時代に米国で何か起こったか?
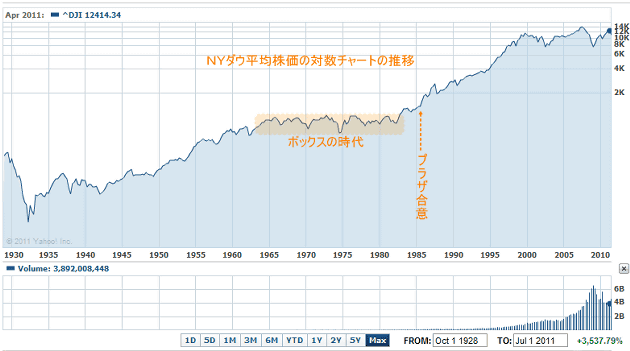
おそらく先端技術の開花です。もう少しグローバル感覚があり英語が理解しておれば、僕もひょっとしたら、アスキーと言う会社に馬鹿になっていた時、日本を超えてマイクロソフトに投資し億万長者になっていたかも知れません。当時、僕は和光証券に在籍しており米国株を買おうと思えば買えたのですね。知識とは…、情報とは…どれだけの価値があり、使い方次第で運命を大きく変えるものです。
マイクロソフトが1983年11月に「Windows」を発表し、アップルは「Macintosh」を12月に発表しています。そうです。NECが98パソコンを発売したのが1982年10月です。ここが勝負の分かれ目です。
この時代の大統領はレーガノミックスを実践したロナルド・ウィルソン・レーガン大統領です。レーガノミックスの概要は…1.減税により、労働意欲の向上と貯蓄の増加を促し投資を促進する。2.福祉予算などの非国防支出の歳出削減により、歳出配分を軍事支出に転換し強いアメリカを復活させる。3.規制を緩和し投資を促進する。4.金融政策によりマネーサプライの伸びを抑制して「通貨高」を誘導してインフレ率を低下させる。…と言う一般的な景気刺激策を実施しています。
レーガンの前政権のジミー・カーター時代はスタグフレーションに苦しんでいましたから、現在の日本とはだいぶ事情が違います。どうもコンピュータの一般化するパソコンの技術革新時代と規制緩和による投資促進が基礎を作り、プラザ合意で更に経済が加速した印象を持っています。
現在の米国株はどっちにしても横這いか、下がるかの狭間で揺れ動くのでしょう。何故なら、金融危機で金融機関が痛んでいるので、直ぐに立ち上がる体力も乏しいと思います。しかし日本は1989年から、一貫して緊縮体制を維持してきました。今では、まるで金融機関の体をなしていません。預かった資金を国債に投資するだけの金融魂が失われた抜け殻状態ですね。そろそろ変革が起こっても不思議ではありません。ここで、この20年の日米の株価を比較してください。
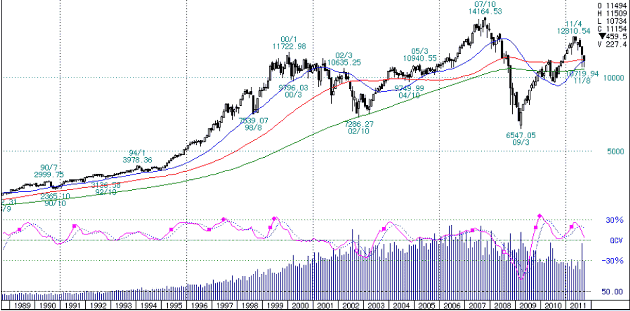
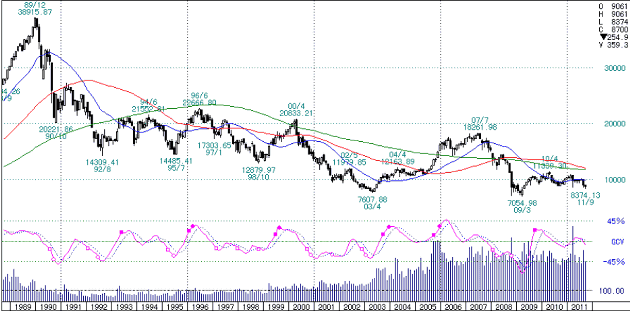
大切なのは基本理念。
産業界の技術革新と政策、環境がマッチしないと、なかなか泥沼から抜け出せませんね。でも今回の先進国と新興国の覇権争いと言うか…、時代変化は日本にとっては歴史的なチャンスに見えますね。そうして、この震災です。このワクワク感は僕だけが感じているのでしょうか? 日米の株価は相対関係にあるように見えるのは偶然でしょうか?
先日の円高対応緊急ファシリティーの創設は、後追い政策ですが優れた政策です。日本企業のグローバル化は加速進展し、今年は4-9月期に昨年比2.2倍の3兆円規模だそうで、バブル期に匹敵するそうですね。この円高を利用し日本企業が支配する市場を2倍、3倍に増やせるかどうか…。JTの株価の堅調さはある意味でM&A戦略による成果とも言えます。ただ必ず成功するわけではなく痛い目にもあっていますね。古河電工がルーセントテクノロジーを買収しましたが、これなどは失敗例でしょう。
日本と言う国の市場規模を基本とするのではなく東アジアと言うアジア圏を一つの市場として行動できるかどうか…この辺りに成否がかかっているように感じますね。日産自動車のタイへの生産移転はその流れに合っていますね。僕はタイよりベトナムの方が北米にも有利に働くように感じますが、何しろ政治の意向もありますからね。どう考えてもTPPの早期妥結は必要条件のように感じます。
どうも今日のレポートは的を得ていませんが、歴史的な出来事を振り返り現在を推察すると言う作業はなかなか価値がある視点だろうと感じています。結論は出ていませんが皆さんも一度、歴史を振り返ってみたら如何でしょう。