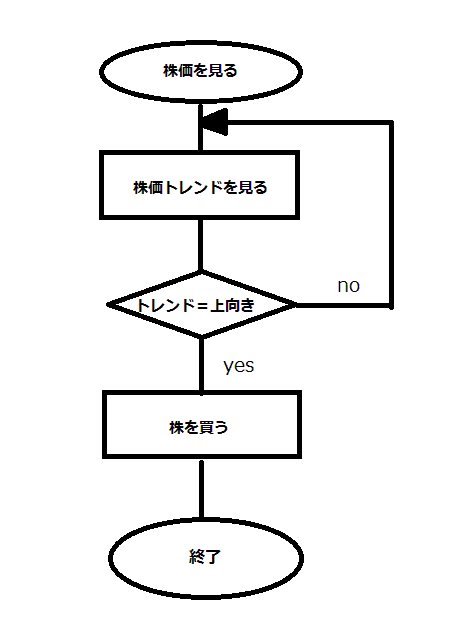« チタンを例に… | 最新の記事 | 金融はアイディア次第 »
アルゴリズムについて考える(2011年10月22日)
今日は僕自身の知らない「アルゴリズム投資」について考えてみます。
ディトレをやってみると分かりますが、板状況が見えるようになり、株価が動くと途端に買いが入ったり逆に売りが増えたり、板状況の注文は株価が動くと瞬時に気配値が変わることがよくあります。人間心理とは面白いもので、売り板、買い板が厚いと流動性があるから安心するのですね。しかしその多くは見せ玉の可能性があります。所謂、買う意思がなくても買い注文が入ったり、売る意思がなくても売り注文が入ったりするのでしょう。
どうも株価が急激に動く背景には、この自動化された売買システムが株価変動に大きな影響を与えているようです。現在の法律ではこの投資方法は規制されておらず、米国でも度々問題が表面化しています。2010年5月6日、NY市場は前日の10868ドルから急落し一時は1000ドルを超える下げになり9787ドルまで下落し、引けは348ドル安の10520ドルとなりました。その時にターゲットにされたのが、P&Gと言う大企業でした。前日の株価は62ドル16セント、ところが、翌日は一時、株価は39ドル37セントまで売られます。結果、引けには買い直され60ドルと75セントになった現実があります。この背景にはこのアルゴリズム投資が影響したと言われています。
しかし、調べましたが実態は分からない事として発表されています。最近ではドイツでも同様の事例がありました。このような売り買いが、世界で何度も問題を誘発しています。日本の場合も、最近では東京電力にこのアルゴリズム投資が関与したのではないかと疑われていますし、最近人気になっているオリンパスも同様の疑いがあります。それではこのアルゴリズムとは何か? 少し考えてみます。
株価は業績数字を基準に算定されています。しかし最近では長いデフレの影響もあり、更にブルドック事件などの企業統治の問題から、グリーメラーの否定などの影響もあり、M&Aの概念が働きづらくなっています。本来、PBR1倍割れは、会社の解散価値の筈ですが、黒字で配当もしているのにこの基準値を大きく割れこんでいる企業が多数存在します。それならばTOBを掛けて会社を解散させ、資産を売却すれば儲かりますね。ところがブルドック事件や、日本の風土がこの動きをけん制しています。だから株価は需給により上下する紙くずのような存在になっています。すこし極端な表現ですが…。
このような背景環境があり、色んな条件を過去のパターンから探し出し、売り買いを自動的にするコンピュータの存在が出てきます。25日線のかい離率がプラスの銘柄を選び、尚且つ出来高が増えている銘柄とか…最近では様々なテクニカル指標が開発されており、スロースキャスティクスやPSI、RCI、DMIなど数え上げればきりはありませんが、そのようなものと連動したり、板状況を把握し発注株式数を調整したり高度化されて動いているようです。しかし多くのアルゴリズム投資は順張り投資ですね。基本的に現状の流れを追認し、流れを加速させる方向性にあります。
だから寄り付きの動向が重要になります。概ね、大幅高する株は寄り付きに買い気配スタートすることがよくあります。トレンドを変えるためには目先の売り玉を全部、拾う必要があります。概ね、株価の3%程度の売り玉を買ってやれば、目先のトレンドは変化しこのアルゴリズムを利用した投資が追認し始めて新しいトレンドが形成されます。先日のオリンパスはまさにそうです。午前中は保ち合いを維持し株価は比較的強かったけれど、後場から値崩し的な仕掛け売りが入ると、次々にプログラム売買が作動し、(ストップ・ロス・オーダーなども含め)瞬時に株価が崩れていきますね。
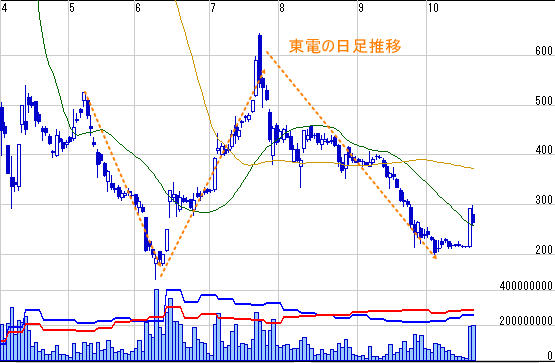
市場に流動性があるときは、不特定多数の参加があるときはこの傾向は薄れますが、今年に入ってからの東京電力などはこの動きで加速され過度に株価が崩れていきました。同じことが現在、オリンパスでも起こっているようです。僕のように会社の企業価値が変化しないのに株価が上下にぶれるのはおかしいと感じ相場に参加する人は既に少数派で、大多数が目先のトレンド売買をしているわけです。本来あるべき株式の資金調達市場としての資本市場が歪んでいる実態のように感じます。この手の売買を規制する必要があるのではないかと思われますが…市場は開かれるべきで僕は規制に反対の立場です。要するに株式市場の参加者層が極端に細っており歪んだ株価形成になっていると言う事なのでしょう。
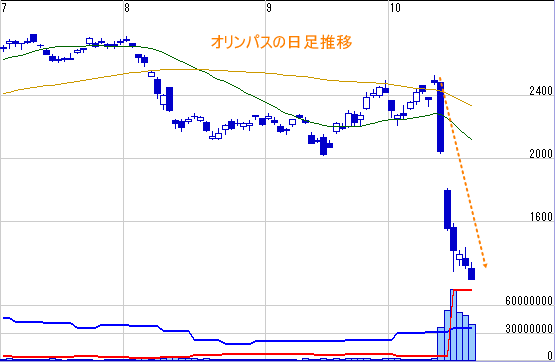
アルゴリズム投資は人気株に集中しますから、既存の株価概念が大きく変化する可能性があるのですね。東電が急落したように、市場は何が起こるか分からないから、過去の経験に基づいた考え方に固執するのは危険なのでしょうね。今頃気付いても遅いけれど、カタルも充分、失敗の反省を強いられているのです。