« 2011年10月 | メイン | 2011年12月 »
2011年11月26日
市場原理主義
本日の一面も欧州問題ですか…という事は、あの報道は偽物でしょうね。予算権への介入やユーロ共同債の話です。昨日の続きですが、「効率的市場仮説」と言うのは隠れた材料も株価に織り込まれていると言う、株価は何でも知っていると言う仮説ですね。だから市場では「材料出尽くし」と言う言葉があります。あるいは「噂で買って事実で売れ」と言う格言みたいなものも存在します。
一方、私は昨日違うアプローチをしました。資本主義が栄えた原点は、市場原理にあると言う市場原理主義の話です。効率的な資金配分を機能させるために市場が存在すると言う話です。何をするにもお金が必要で優秀な経営者に資金を預けようとする原理ですね。国債金利は安全ですが1%です。リスクはありますが企業経営者に委託すればROEが10%以上の企業がゴロゴロ存在します。
本来は裁定が働き資金が動くのですね。ところが清貧思想の跋扈でコンプライアンスの誤った見方が定着し市場活動を歪め、ブルドック問題やオリンパスのような企業統治問題が、日本の市場を殺しました。故に野村証券の株価は凋落しています。
この効率的市場仮説の市場と現実社会の情報交換が株価の変化になって現れ、今回は国債価格の変化ですが、市場と現実社会が結び付いている現象の一つです。何も現実社会だけが市場を動かすわけじゃないのですね。今回は逆のケースです。市場参加者は常に制度の歪みを探しています。その歪みである穴を見つけると、その問題点を是正させようと市場を動かします。歪められた現実は効率的な資金配分を歪めるから、それを是正させようと混乱を起こすわけです。つまり市場価格が現実を変えるのですね。常に交互に情報を交換し価格と現実が交錯し合うのが市場原理主義ですね。このような現象のお蔭で、効率的な資金配分が実現され、人類は進歩を促進させるのです。
ブラック・ショールズ以来、オプションの原理が解明され、金融デリバティブ機能が高まり効率的な資金配分を促進させるためにスピード違反を犯したのが、サブプライムからCDSの金融危機でした。しかしこのスピード違反がBRICsの躍進を側面支援し、人類の成長の幅を広げました。市場経済に新興国が参加してきましたね。その為に先進国だけでできていたルールを変える必要が出てきたので、日本の失われた時代や欧州危機が生まれています。日本はようやく福島の原発汚染地の政府による一括買い上げが話題になり始めました。だから私は東電を1兆円程度の罰則で免責にしろと述べたのです。故に東電を買ったのですね。しかし政府の選択は責任逃れでした。だから失われた時代は続き、株価は低迷しています。
正しい選択をすれば、日本株は何時でも上昇できます。既に技術も確立され国民もある程度、現実が分かり始めています。年金の3号年金問題など、予算もそうですが、政権が交代したおかげで、いろんな点で問題点が見えてきましたね。自民党は偉そうに言っていますが、みんな彼らが失敗した選択を繰り返してきたから、今の失われた時代の現実があるのです。さて話を戻しましょう。市場は現実を正しい方向に促すのです。その現象がアイルランド、イギリス、ギリシャ、イタリア、スペインと連鎖しています。冒頭で書いたように、日経新聞が報道した予算権への介入やユーロ共同債の構想が浮上したと言っていましたが、あの報道は嘘だと言ったのはイタリアの国債利回りが上がっているからです。
しかしやはり構想はあるのでしょうね。最近、イギリス国債とドイツ国債の利回りの逆転が起きています。何度も言いますが欧州問題でユーロが安くなるのは輸出競争力の強いドイツが有利なのです。故にドイツの輸出依存度は30%を大きく超えています。勝手な振舞いですね。中国は20%台の筈です。日本は11%ですよ。世界の投資家はこの歪みの解消に賭けますね。具体的にはイタリア国債を買ってドイツ国債を売ります。これが最もアクティブな市場原理に沿った投資ですね。
だって通貨だけでなく財政も一体化しないと持ちませんね。ギリシャやイタリアが離脱するか?EUの組織を維持するなら予算権などの財政問題も統一しないとなりません。だから市場にその兆候が出てきたのかもしれません。ドイツ国債の利回りが上がれば反対しているドイツはいずれ従います。2.2%前後の利回りが4%、5%と上昇しイタリアは落ち着くのでしょう。イタリアは輸出競争力がないわけじゃありません。ギリシャとは違いますね。まぁ、どのような選択をするか分かりませんが、日本のように間違いだらけの選択を繰り返せば、日本同様に失われた時代に突入しますね。
これが効率的市場仮説の市場原理主義の考え方です。市場が実体経済を動かしている現象が欧州危機なのですね。何も現実社会だけが市場を動かしている訳だけじゃありません。カタル投資はハイリスクなので、正しいと思う政策に大きく投資しますが、市場、現実社会の選択が間違っていれば、当然、投資成果は上がらず惨敗します。常にハイリスクを心がけ可能性の高い投資を心がけているつもりですが…なかなか現実社会はカタルの思うような選択をしないのですね。200円台の東電は本来なら年金ファンドが買い、長期投資しても良いですね。配当を実施しないからこの株価なのでしょうが、どの程度の損失か分かりませんが、何れ時間の経過で回復する割引債価格なのでしょう。
欧州問題も正しい選択を実施して欲しいね。さて本日は昨日の効率的市場仮説から市場原理主義をさらに考えてみました。だから皆さんもドイツ国債の利回り推移を見守っていてください。ここでの中規模なハイリスク投資なら、イタリア国債を買うことですね。7%を超える水準は10年間で2倍になる投資です。日本国債よりずっと効率的ですが、馬鹿な日本の機関投資家は逆に売っていますね。本当に市場原理が分かっているのでしょうか?日本国債を売りイタリア国債を買うなら分かりますね。いずれROEの高い日本株は上昇します。
下のグラフは一足先に緊縮財政を実施したイギリス国債とドイツ国債のチャートです。24日にドイツ国債の利回りが、イギリス国債を一時的に上回りました。昨日は再び戻っています。イタリア国債は7.26%ですね。グラフは24日現在のものです。
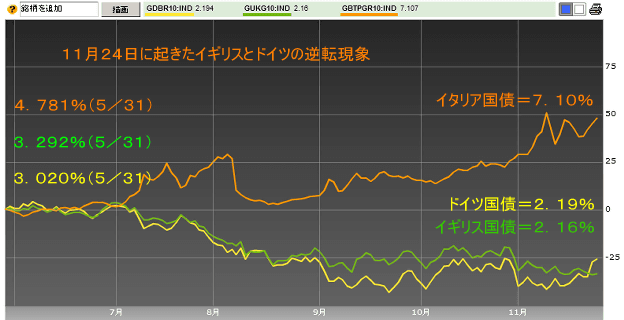
2011年11月19日
野田総理は及第点か…?
何故、みずほが再び100円の大台を割れるのでしょう。我が国を代表する会社が次々に株式市場で新安値を更新しています。一向に上向かない日本経済は根本的な政策運営が間違っているのでしょう。どうも日本国の信用問題を市場は織り込んでいるのではないでしょうか? そこで…この可能性を考える為に少し調べてみました。ここではトヨタの株価を用いましたがパナソニックを始めソニーなど…主だった企業が新安値を更新しています。
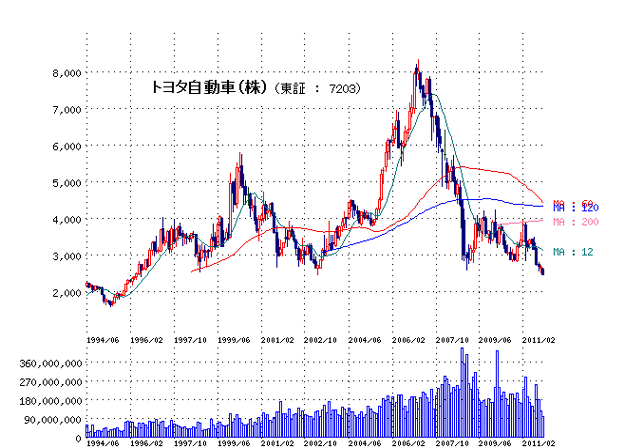
個人の金融資産は2011年6月末で1491兆円あります。(日銀の資産循環統計からの数字です。)日本全体の短期証券などを含む全体の債務残高は1151兆円と言われています。一方、国債の発行残高は901兆円(国庫短期証券、国債・財融債の合計)で、海外投資家が保有している金額は7.4%の67兆円です。つまりおよそ93%程度を国内で消化しているのです。故にギリシャやイタリアが騒がれるのに、日本がはるかに高いGDP比の債務残高状態であるのに低金利を維持しています。GDP比の債務残高の主だったグラフは財務省の作成したグラフより掲示しました。
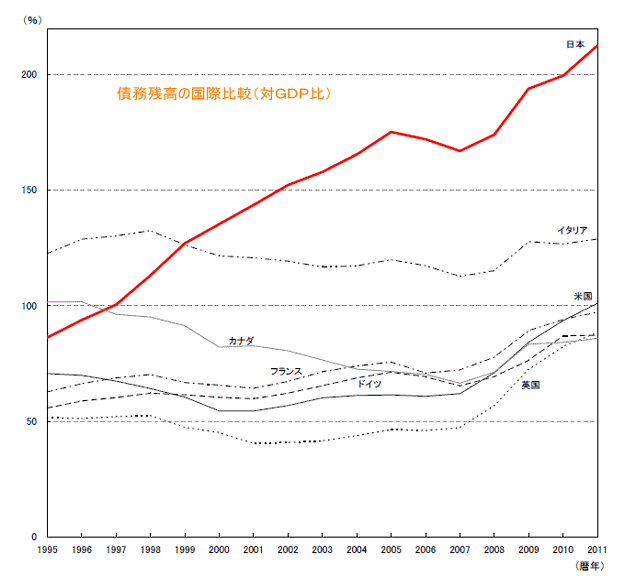
財政規律が緩んでおり、行く末、日本企業も国が沈むから買われないのではないか? 企業業績がどんな向上しても、国がダメなら株式の価値はなくなるのではないか? 一抹の不安を感じますね。逆説的に仕組み上、効率の悪い「過去の投資」(国債)に、お金を振り向ける政策を採用しているので、日本株の復活はROEの高い民間企業(効率の高い未来の投資)に流れないのではないでしょうか? 最近の僕の概念はこんなものです。日本で最も頭のいい財務官僚が、なかなか分かり切っている政策転換を実行しないのは、この辺りにポイントがあるのではないか?と考えているのです。
本来は、財務官僚の意図は間違っているのですね。財政規律が緩んでもROEの高い効率的な運用の場に資金を誘導すべきなのです。そうすれば日本国全体のGDPは上がりインフレが進みGDP比の債務比率も下がりますね。増え続ける社会保障費を上回る経済成長を実現させればいいのです。この成長投資がスマートシティーの建設ですね。日本にはごみの資源化を始め、ITS(高度道路交通システム)など幅広い沢山の未来技術が眠っていますが、総合的にプロデュースする人が居ないのですね。縦割り行政の弊害なのでしょうか?
2003年から小泉・竹中改革が認識され株価は上がり始めました。この動きは強引にROEの高い企業へ資金を移動させようと、ゾンビ企業を切り始めました。非効率な資金を
切り効率化投資に移したのです。郵政民営化は効率の悪い財政投融資資金の削減です。
強引な手法でしたが、ある意味で評価されます。しかし小泉側の支持者が少なく、改革はとん挫します。所謂、亀井静香などの既得権力者の集団ですね。年功序列、終身雇用、株式持ち合い、鎖国制度による内外価格差の維持等により、輸出依存度による加工貿易体制の維持で食べる米国庇護のもとの架空の経済成長の残像が捨てきれなかったのでしょう。
しかしこの幻想は、1985年のプラザ合意で明らかに政策の転換を要求されましたが、そのメッセージを見誤った大蔵官僚の失政が生んだ失敗が、バブル経済とその崩壊ですね。14年後に新しい出発を図り、成功し始めたところにライブドア事件の勃発です。これは、おそらく権力闘争ですね。そこに一部の国粋主義者の地検幹部が乗った話でしょう。この動きに金融危機が重なり、パラダイムショック(枠組みの転換)が起こっています。
日本がTPPに参加すると表明すると、すかさずにカナダやメキシコが参加表明し、中国がASEAN+3を主張していたのに、態度を軟化させこれまで否定していた+6を主張し始めたのも、アラブの春から欧州危機が背景にありますね。リカードの比較優位論(比較生産費説)は自由貿易を推進すれば、更に効率的な生産効果が得られると言うグローバル論からも支持されます。我が国のメディアの論調を見ていると、生産者側の論理に満ち溢れていますね。そりゃ、スポンサー契約の獲得の意味合いもあるので、あのような報道になるのでしょうが、受信料を徴収している国民放送のNHKは生産者の論理で報道を組み立てるのではなく、消費者、一般の国民の側に立って報道を組み立てる必要があります。
安くておいしいコメが自由化され、おいしい牛肉が安く食べられるなら消費者にとってラッキーですね。しかし食料の自給率が低下している現状は、安全保障上、許されるものではありません。自由化したうえで農業の保護政策は国際競争を支援する方向性でしなくてはなりません。時代遅れの三ちゃん農業を支援するものではありません。国論を二分する難しい舵取りが要求されますが、自民党的な政策運営ですが、野田政権はこれまでの所、及第点です。何故なら、南沙諸島問題からASEANを取り込んだ2兆円投資など自由貿易圏の主導権を握るものだからです。慌てている中国…の行動が、その成果を評価しています。この背景はおそらく米国のけん制がありますね。今後、消費税の問題から財政規律の方向性を見せれば、株価も上向くでしょう。
2011年11月12日
中国を…
日本株は相変わらずデフレ信者の渦の中に揉まれ、最近は僅かな数量のアルゴリズム投資に増幅され揺れています。やはり20年もデフレ政策が続けば、その流れに揺れるのも仕方ないのでしょう。
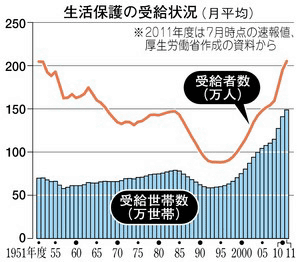
先日発表された生活保護の受給状況はショックでした。この数字に裏には生活保護受給者を狙う貧困ビジネスの影響もあるのでしょうが…それにしても少し異常な伸び率ですね。震災の影響があるとしても、ここ数年の伸び率はどう解釈したらいいのでしょう。高齢化世帯が増えているのも分かりますが、景気が悪くなると治安も悪化し世情が乱れます。ITバブル終了の頃より増え始め平成20年代に入ると急速に伸びています。
今回のTPPを巡る論争も報道関係者は、事を煽る報道ではなく、真実を分析する報道に変化させねばなりません。JA対経団連の構図は、野次馬根性の貧困なレベルの報道ですね。一体、何が論点になるのか?さっぱりわかりません。関税をセロにしてフェアな競争社会の形成は当たり前の事でしょう。半導体産業の崩壊などに象徴されるように、既に我が国の社会インフラ基盤は脆弱で競争に敗れているのです。高い税金に規制など…どんどん産業は空洞化し、いずれ社会弱者だけが残る亡霊大国になり貧困に飢えますね。リカードの比較優位論に従い企業は行動をするだけでしょう。
時間稼ぎをしてきたので、生活保護のグラフに現れるように経済が落ちぶれ、今年は東電やオリンパスが生まれたのです。1%を割れる状態の国債に投資し、過去にいつまでもお金を費やしているから経済が伸びません。ROEの高い企業へ投資を増やさねばなりません。ここに来てようやく企業は、日本に見切りをつけ海外戦略を積極化させ始めました。日産とトヨタの構図ですね。デフレ先進国の成果が、ユニクロの世界進出の加速です。今年はNYやソウルと積極的な世界展開を加速させています。残念ながら、ニトリは国内が237店舗なのに海外店舗は7店舗と勢いがありませんね。今の現状は海外が7割で国内は3割がグローバル企業の基準でしょう。
日本の勝ち組企業はドンドン海外へ進出してシェアを奪うべきでしょう。まだ日本ブランドの価値はありますね。化粧品から食品、農業もブランド化し輸出に目覚めるべきなのでしょう。中国13億の1%の高額所得層は1300万人もいますね。これらの人はベンツなどの高級車に乗り消費生活も豊かですね。魚沼産のコシヒカリの天然干しなどの希少なコメはもっと高く売れるでしょう。だって生産が限られますからね。
日本株は海外勢の影響を多く受けます。ミシガン大学の消費者信頼感指数が発表されました。一般的にはコンファレンスボードが一般的ですが、希薄な好材料に反応するようになっています。市場主義の国らしい。日本化現象が気になりますが、イタリアの法案通過などを見越し際どいタイミングで株価は上昇しクリスマス商戦を支えていますね。この1か月間の動向はクリスマスの為でしょうが…大きな支援に違いありません。中国のCPIも5.5%と減速し更に11月も下押すでしょう。やはり中国は広いと思うのは統計数字を見ていて感じられます。北京や上海など浙江省などの沿岸部は成長力が引き締めで鈍っていますが、内陸部の重慶などは依然20%程度の成長を示しています。最近、三一重工の業績悪化の記事をみましたが、他の工作機械のメーカーは増産記事の方が多いようです。
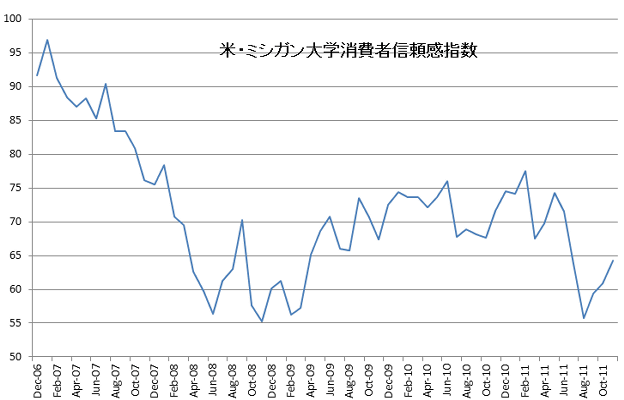
欧州危機に目が奪われ過度の悲観見通しに、市場が慣れているかもしれませんね。コマツの受注状況を見るとそんなに悪化しているように見えませんね。確かに中国はここ数か月30%程度の受注が減っています。しかし米国は意外に高い伸びを示しています。日本は復興需要から受注は好調ですね。セグメントから判断すると米国と中国は互角の売り上げですから、中国の落ち込みを米国が補っていますね。しかもアジアは高い伸びを続けています。何故、株価が大きく下がったのでしょうかね?コマツは建設機械と車両部門の他に産業機械部門がありますが売上比率が15%未満と低いために除外しています。本当は産業機械も含め検証するのが筋ですが…面倒は省きました。大枠を掴めばいいのです。
何故、建機のコマツを引き合いに出したかと言えば…BRICsの成長には社会基盤整備が欠かせず、このラインが最もBRICsの経済成長の状態が端的に出て来ると考えているからですね。むろん工作機械でも良いのですよ。減速から成長へ向かう中国が焦点になるなら象徴的な銘柄の動向を追うのが筋ですね。故にコマツを少し検証してみました。
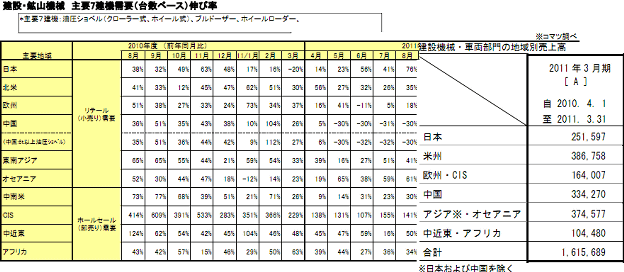
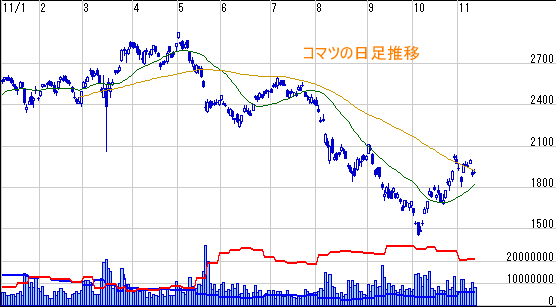
2011年11月05日
会社の注目点
前回はDENAを材料にして株価を予測することは、考えられる環境にその会社がどう立ち向かっており、その成果はどう業績に反映されるかの投資家の読みだと述べました。この読みで難しいのは、業績の推移の読みが当たっても株価が反応しないことがあります。今日の市況で登場してきたトロとの会話で、カタルの投資スタイルを批判していた時ですが、彼も僕の実力をある意味で認めているわけです。その言葉で登場した鬼ゴムですが、下のような業績推移でGSなどのファンドが関与し、300円台の株価から現在は600円台に上がっています。その業績は下のようですね。しかし…アーレスティーもカタルの読み通り業績推移は上がっていますが株価は冴えません。その業績推移は下のようなものですね。両社の業績数字と株価を比較してください。両社の違いは明らかに仕掛け人の存在があるかどうか、…などの複合的な要素で株価が形成されているからでしょう。他にも市場環境により、大きく影響を受けます。所謂、システマティック・リスクと言う市場全体の要因によるものです。今でいうなら欧州危機ですね。
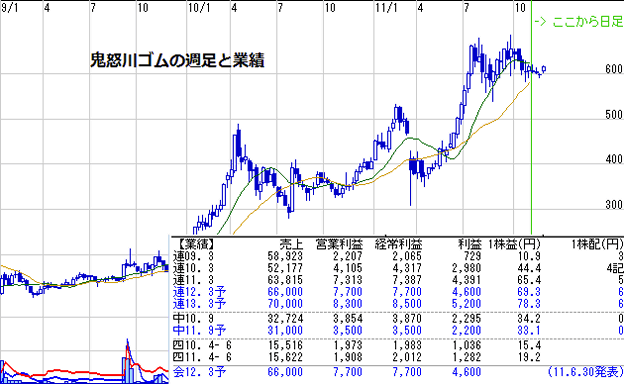
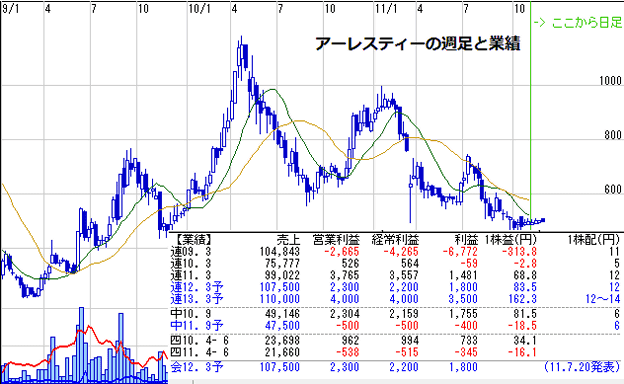
さて今日の本題は、銘柄により、その会社が現在、取り組んでいる課題があります。会社は当然、利益を上げようと計画を練り、日夜努力をしているわけです。取り組んでいる事業が成功すれば、飛躍的な変貌を迎える会社を選ぶわけです。この飛躍的と言う表現を、業績の変化率と置き換えても良いですね。先日はDENAの近年の成長は、日本の携帯コンテンツ(ゲーム)の成功によって支えられ、僅かな期間に四半期ペースで100億円だった売り上げが、一気に350億円レベルへ跳ね上がったわけですね。だから株価も大きく上がりました。今度は日本同様に、世界でも同様の現象がみられるかどうかが、DENAのポイントなのですね。だからNGモコの成果が株価を決めます。このように同等の注目点はどの会社にも存在します。
例えばカタルが最近取り組んでいたチタンは、順調に株価は回復してきましたが、この注目点はこれからのチタンの需要と価格によって業績は決まります。だからこの10月に価格交渉が行われ、原料高や円高をこなせる値上げが実行できたかどうか? 更に需要を予測するための航空機の量産具合や淡水プラントなどのチタンを多く使う製品の具合を見る為に、産油国の景気動向などが問題になるのですね。その問題点を解明するために、貿易統計からHSコードを調べ、その数量と価格の推移から、これからどの程度、10月に値上げが出来たのか? その統計値から推測できるのですね。そうすると会社側の発表前に業績数字が読めますね。航空機の需要は落ちません。しかし問題は一機辺りのチタンの使用料が減っている可能性がありますね。だからV字型の業績推移が望めないかもしれません。伸びるのですよ。しかし飛躍的な伸びがあるかどうかが問題なのです。増産投資をしているし、業績の伸びは確定しているのです。でもカタルが注目してから株価は下げましたね。この理由は市場全体のリスク、所謂、システマティック・リスクを打ち破る買い勢力が居なかったのですね。業績は良くなるのに株価が下がるから、株は下値を買っても大丈夫なのです。でも何処で反転するか分からない。
さぁ、DENAに戻してください。
日本の人口は1億25百万人、米国は3億人、英語圏の人口は? 中国圏の人口は? ところが株価は下げていますね。チタンと同じですね。頭打ちした日本の材料で売っても仕方ないですね。今年の8月から世界でサービスを始めたばかりです。だから買いなのですね。このようなケースは稀で、普通、株価は業績と相反する現象になりません。一時的な減速感でここまで株価が急落したのは、東電やオリンパスと欧州危機の影響でしょう。
ここでルネサスの焦点は何処にあるのか?
この会社は最近、大赤字を計上しても株価は上げましたね。つまり悪材料は株価に織り込まれていたわけです。カーネビのシステムLSIは世界シェアが80%です。車の半導体は40%ですね。世界シェアでトップなのですが、赤字なのですね。ここに魅力があります。経営者が効率化に目覚め、適材適所で量産化して販売すれば高収益会社に変貌できますが、残念ながら経営者が不在です。でも世界シェアトップは非常に魅力的なのです。オリンパスが高評価を受けていたのも、内視鏡はこれからの先端医療で世界トップだからですね。だからPERが通常は10倍なのに、30倍~40倍に評価されていたのです。
間もなく007(ユビキタス)の決算が発表されます。当然赤字です。現状は全くダメですね。しかしSQLも伸びてきており使用範囲が広がっていますね。デジカメからカーナビまで、どんどんSQLは広がっています。更に村田との提携はおそらくWiFi通信技術ではないのかな? 専門家ではないからわからないが…飛躍的に通信量が増大し通信各社は分散を始めていますね。その関連商品かな…と考えています。更に諦めていたQBが製品化され、いよいよ登場します。世界中に家電製品は売られネットワークで結ばれ社名のようにユビキタス社会が登場していますね。スマートフォンなどを見れば分かりますね。その分野に経営資源を絞り、しかも組立ソフトの分野は年率20%成長をしています。だからカタルの関心は赤字でも非常に高いのですね。
最近、株価が堅実になってきたAOCは原油価格が焦点でドバイ原油は100ドル台を維持しています。この会社の焦点は来年の原油生産ですね。このようにそれぞれが注目ポイントを持っているわけです。どうやって銘柄を選ぶか? 狙いは業績の変化率の度合いですね。DENAが成功すれば売り上げは3倍増以上になりますね。当然、利益も大きく膨らみます。でも日立はどんなに良い会社に変貌しても売り上げが2倍、3倍になりません。せいぜい変化率は20%が限度でしょう。ここでカタルが述べたいのは、会社にはそれぞれ注目するポイントがあるという事なのです。
2011年11月03日
DENAの急落を考える
今日は珍しく株式教室らしいテーマで勉強してみます。今週は決算数字が発表されておりその数字によって株価が大きく上下しています。なかでもカタル銘柄のDENAが決算数字を受けてストップ安を演じましたから少し解説してみます。基本的に携帯コンテンツはここ1年~2年ほど大きく伸び、上手く収益加算を演じたのがゲームの分野でしょう。カタルは早くからこの携帯コンテンツが有望だと考えていましたが、ゲームに主導権を握ったのがDENAとグリーですね。両社は今期、同じ分野なのに対照的な株式市場の反応が見られます。グリーの伸び率は続いているのにDENAは横這いなのでDENAが売られました。その周辺のカタルの考え方を述べます。
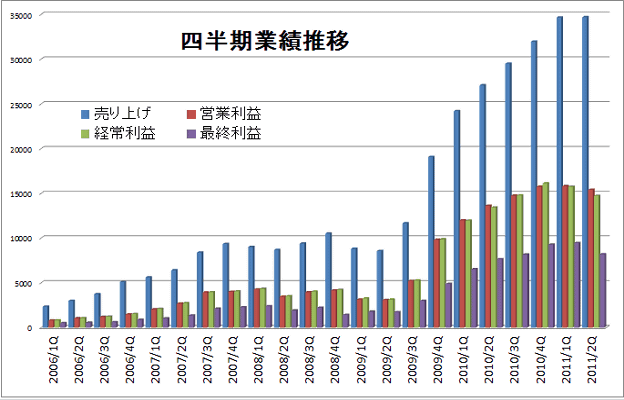
基本的に我が国の携帯コンテンツからの収益は350億円ほどなのでしょう。グリーの方が競争力が強いと思われますが、両社のユーザーはダブっているのでしょう。DENAは国内の登録会員を発表しており3000万人ほどですね。人口比から見ればどう考えても頭打ちの状態でしょう。残念ながらDENAは世界の登録会員数を発表していません。一方、グリーは発表しており世界で1億5540万人だそうです。一方、日本の会員割合は17.8%となっており2766万人ですね。だいたいDENAと変わりません。推測ではグリーの四半期売り上げは既に304億円に達しておりDENAのケースから推察すれば伸び率は鈍化するのでしょう。我が国の市場シェアはおよそ700億円前後、今後もスマートフォンの導入で伸びるにしても、せいぜい1000億円市場のパイの争いでしょう。
問題は海外ですね。両社とも海外分野に力を入れておりグローバル化に取り組んでいます。DENAは今年の8月だったと思いますが、本格的なサービスを開始しました。要するにこの出来が今後の株価を左右し、早ければ年末から来春にはその方向性が見えます。株と言うのは予測に対する賭けなのですね。DENAの減速基調と言うか伸び率の低下は昨年分かっていたことなのです。それは四半期別の推移を見れば分かります。グリーは伸びており伸び率は下がるでしょうが、DENAを超える可能性はあります。しかし市場のパイは上限が必ずあり、国内の会員数から見てDENAの350億円を大きく超えると考え辛いですね。故に国内から海外の動向が非常に注目されます。
問題は国内のような伸び率を海外でも出来るのかどうか…DENAは基礎がありました。モバゲー会員が前から存在しており下地があったのでゲームに進出しても簡単に伸びたのでしょう。しかし海外で爆発的な伸びが期待できるのかどうか?ただグリーは下地が無くても伸び率を示しましたから、案外、すんなり伸びるかもしれません。この点は分かりませんね。さらに携帯ゲームが海外でも受け入れられるか?まぁ、任天堂のケースを見れば大丈夫だろうと考えられますが…この点も焦点ですね。
DENAは球団買収に乗り出し経費が掛かりますから、市場はネガティブな反応をしましたが、ソフトバンクや楽天の例を見れば分かりますが宣伝効果の方が高いのではないでしょうか? 国内は頭打ちなのは前から分かっている既成の事実なのです。昨年の春に私は2800円前後の高値を買い、一度、2000円割れの洗礼を受けています。その後、多くの外資系ファンドの買いで4000円台に株価は上げた背景は海外部門の推移が好調なのでしょう。DENAは当初は数名の社員しか派遣しておらず、事業化の検討をしていました。既に3年ほど経過しその後、M&Aで一気に時間を買いましたね。NGモコはその代表例です。グリーの連結化は最近ですね。時間差を感じられます。DENAが早いと言っても海外の売り上げはまだ立ち上がらずこれからですね。8月から開始したばかりです。
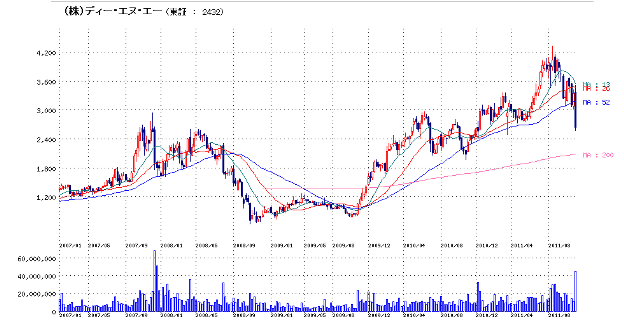
要するに国内から海外への成果が分かるのは早くて年末から来春、普通は来年の推移を見ないとならないのです。今回の下げは欧州問題とオリンパスやガイシのような環境下で起こった行き過ぎの現象だろうと考えています。すでに海外は収穫期に入ります。つまり2008年からの低迷のようにはならないと言う考え方ですね。あの時はゲームの立ち上げもなく2009年の春から夏ごろから携帯ゲームに乗り出したのでしょう。その成果が2009年末からの動きですね。世界人口は70億人で日本は…ただコンテンツを利用できるエリアは限られていますが…世界中でスマートフォンは売られ、これから海外の売り上げが寄与するのですね。だから国内の売り上げ(過去の現象)から株価が急落した今回は願ってもないチャンスと言えるとカタルは考えています。
だから今日の市況で売り上げと営業利益のグラフを用いたのですね。既に株価は一度、売り上げ鈍化の洗礼を受けているのですね。おそらく今回の急落は欧州危機などの再熱などがもたらした偽りの下げだと思います。だから短期調整で年末にも株価は戻ると思っています。本当はもう少しグリーとの比較や会社側に問い合わせ、資料を補強しなくてはなりませんが簡単にざっと見た感じでは買い場でしょう。ただし株価が1万円台に抜けるかどうかは来年にも判明する四半期別の売り上げの伸び率が問題になります。仮に四半期の数字が350億円から、450、500と言う伸びが確認されればPERの評価は20倍から30倍に変化します。日本から世界に変わりますからね。それも初動波動ですから金融相場のイメージで株価は急騰しますね。ただし海外展開がモタツキ収益が見込めないとなると…PERは10倍を割れ8倍程度の評価になるでしょうね。要するにDENAの焦点は海外収益にある訳です。国内ではありません。だから3Qの数字を見て悲観することもないし、市場の過剰反応だと考えているわけです。
今回はDENAを取り上げましたが同じような焦点がチタンにもあり、その背景をしっかり見ないと株価の推移に心が揺れ動き動揺するわけですね。企業業績の背景を知ることは重要なのですね。その会社のどこが焦点になっているか?この考え方は非常に重要です。