« 2011年11月 | メイン | 2012年01月 »
2011年12月24日
ドラギ総裁のクリスマスプレゼント
米国株は今週4連騰し年初水準の株価を完全にクリアしました。
世界経済はサブプライムからCDSによる金融デリバティブによる過剰投資の崩壊が、金融機能の急激な縮小を生み、実体経済を大きく揺さぶりました。その為に世界各国は大規模な財政出動を実施します。代表的な事例は中国の4兆元(約50兆円)にのぼる大規模な財政出動でした。この時期、米国では金融機能を補うためにQE1が発動され、AIGなどの金融機関が救済されました。金融危機による実体経済の悪化を見て、私が何度も金融経済と実体経済は鏡と同じで表裏一体の関係だと言っている意味が、この現象からお分かり頂けると思います。世界の金融危機の為に日本企業も大幅な落ち込みを示しましたね。
この第一次財政出動効果は、中国では完全に立ち直りましたが、米国のQE2の影響もありインフレを招きましたね。しかし欧米は同等規模の財政出動をしましたが、実体経済を刺激するほど財政出動効果を上げませんでした。おそらく財政出動の仕方が間違っていたのでしょう。お金の使い方が的外れだったのですね。この点は日本と同じ失敗を犯しています。時代が変わったのに旧来型の手法を踏襲したのです。社会インフラ設備が出来上がっているのに、まだ使える道路を掘り返し、再び同じものを作る無駄使いを…永遠と繰り返したのが日本の公共事業投資。その象徴的なものが「八ッ場ダム」問題が生まれた背景ですね。(ただ無駄ばかりでなく新産業支援の為に、IT産業の為に光ファイバー網の構築やITS高度道路交通システムなどの経済政策も実施しています。問題は限られた資金だから旧来型の公共事業投資を残すのではなく、切らねばならなったのですが温存しましたね。結果、国家予算が肥大化するのです)
中国は社会基盤が未整備なために、固定資本形成の比率を高めても経済の乗数効果が高いのですね。当たり前の話です。道路がないところに道路を作ったり鉄道を作ったりすれば経済効果はドンドン上がります。しかし欧米は既にそのような基礎的な社会基盤整備は出来上がっているのです。だから無駄使いになり、日本と同様の結果になりました。産業基盤の転換ができませんでした。だから財政出動が仇になり欧州問題に発展したのでしょう。金融危機からの対応で一番、成功したのは中国でした。しかし中国はここからの手法は難しいですね。ようやく金融政策は方向転換しました。この遅れた原因の一つが米国のQE2発動です。実体経済は昨年末頃から失速し始めています。車の販売台数を見ていれば分かります。それだからFRBはQE2を発動しました。国債への投資は過去の清算に使われます。だからあまり効果はありません。バーナンキ議長はQE3を住宅関連のMBSに投資すると述べていますね。この分野が遅れ資産価格が下がる資産デフレを転換するためですね。だから早くやった方が良いが、ここに来てようやくQE2効果が生まれているようですね。理想から現実へ(金融相場から業績相場)ただ大統領選を考えれば早めに手を打たねば効果は生まれません。
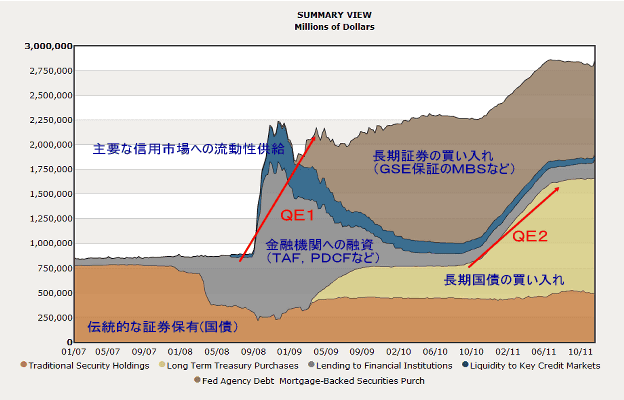
ここまでの解説で世界経済の下準備が出来ましたね。
つまりNY市場の昨年からの上昇はQE2の期待相場だったのですが、(昨年末から3月頃までの動き)実体効果が出る前に世界経済の先行きに対する疑問が生まれていたところに(今年春の動き)…ギリシャ危機を煽り欧州危機の演出で儲けようとしたのですね。(今年後半の動き)これは絶妙なタイミングで演出されていますね。僅かなタイムラグを利用した相場の演出です。日本はイワシ民族で、失われた時代の結果、アクティブな先導者が消えましたから、波間に漂う海鳥のようなものですね。しかしECBによる3年物のオペは実質的な量的緩和を引き出したことになります。よって米国経済の回復と相まって大幅な上昇に繋がり年初の水準をクリアしたのでしょう。(先週からの大幅な相場上昇、赤の部分)
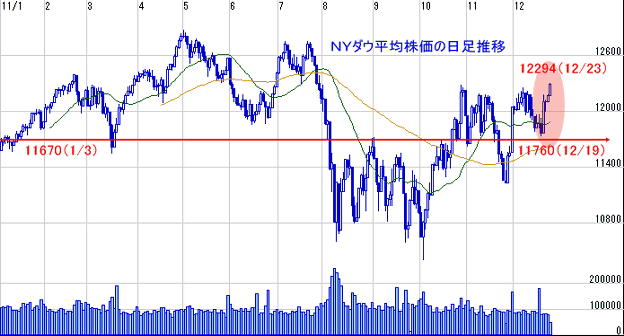
格付け会社の演出効果はECBの量的緩和を引き出しました。ドラギ総裁はECBの直接投資による流動性の供給を避けましたが、同じ量的緩和効果をもたらしますね。大量に資金が溢れるから安全資産への逃避が加速し、マイナス金利が生まれているのでしょう。あとはこの奇妙な仕掛けの解釈が安心感を呼び込むことに方向性が転換すると思いますね。新たな仕掛けが発動されるのでしょう。
2011年12月17日
市場原理主義
果たして市場原理主義の中で、信じられている時価会計主義は正しいのでしょうか?
欧州危機を考えると馬鹿な事をやっていると…いつも考えるのですね。ECBがイタリア国債などを無尽蔵に買うと言って、実際に実勢金利5%程度まで買い上がったら、市場原理主義者はフェアではないと…批判をするのでしょうか? それともユーロの価値は大きく落ち込むのでしょうか? 結局、ドラギ総裁の心中は、正義感と現在起きている現象との狭間で心が大きく揺れているのでしょう。
人間と言うのは現実と理想の狭間で常に揺れ動いていますね。
理想と現実のギャップに葛藤する人は非常に多いのです。自由で公正な競争によって勝ち得た利益は正当化されるが、不公正な社会で特権を利用した不平等な環境下での競争の勝者は称賛されず、認められないと言います。故に汚職の源の贈収賄は罪に問われますが…中国の共産党幹部の躍進は目覚ましいのですが、社会は成長しています。一方、市場原理の自由競争を掲げる米国では、本来は称えられて良いのに、公正な競争下で勝利した勝ち組1%が批判されています。
私が子供だった頃、巨人軍は強く川上巨人軍は9連覇を成し遂げました。そんな中で子どもの好きな代名詞として「巨人、大鵬、卵焼き」の言葉は生まれます。長嶋や王さんは僕らの憧れの存在でした。ビル・ゲイツやウォーレン・バフェット、スティーブ・ジョブズは称賛されますが、彼らは希少な勝ち組の1%の対象ですね。中国の華西村は高度成長の勝ち組として称賛されています。共産党幹部の呉仁宝さんの手腕によるものでしょうが…ビル・ゲイツと、どちらが評価されるのでしょう。
ベルリンの壁崩壊をみて、市場原理主義が正しく富を分配すると考えてきました。人間の欲望をコントロールする市場原理が、効率的な資金配分を成し遂げると考えてきましたが、この影で競争に敗れた人間を支える為に、生活保護や年金制度が必要だと言われ、競争に破れた弱者を支える為に財政は悪化していますが、その弱者の集まりのギリシャは、これ以上の緊縮は耐えられないと文句を述べています。
でも人間は、勝者は好きですが…弱者を称えることはしませんね。なでしこジャパンもワールドカップに予想外の躍進を続け、奇跡に近い勝利を収めたから大きく称えられるのです。富の配分は難しい課題ですね。多くの人が幸福感を得られるような社会環境を創る為に政治はあるのでしょうが…難しい選択を迫られています。「トリレンマ」の時代だそうです。どれも好ましくない三つの選択の中から、一つを選ばねばならない時代だと言うのです。
市場原理主義者から言わせれば、現在の欧州危機での安易な選択は「未来の悲劇」を生むので、今、その将来の大きな災難を軽減するために、分散し調整しているのですね。だから歪められた溝を埋めるまで、市場は要求を突き付き続けます。もういい加減にしてほしいと考えるのですが、ドイツ国民のエゴは通用するのでしょう。彼らはある意味で公正な勝者ですからね。ユーロと言う単一通貨のおかげで輸出競争力が増し経済が好調なので失業率が低下しています。アイルランドも当初は危機の先頭を走っていましたが、税制特権で得た産業の利益が、過去の過ちを修正しています。
今の欧州危機の試練は過去の過ちの修正なのですね。市場原理主義者から言わせれば、こうやって矛盾が修正され大きな戦争などが起こる事態を避けているのです。過去、日本は矛盾を抱えたまま、軍部の独走により、やけっぱちの戦争行為に向かいます。人間と言うのは目先の困難な事態を避けようと努力します。困難を避けようとすれば無理をしますから、不正行為に及ぶこともあるでしょう。オリンパスの飛ばしはその結果ですね。でも、もし菊川さんがウッドフォードさんを指名しなかったら…問題は発覚せずに時間が経過したのではないでしょうか?
オリンパスが江戸時代の大名家の世界だとすれば、菊川さんはお家の大事を救った名家老として崇められたかもしれません。これまでの所、私利私欲により利殖の為に不正をしたわけではなさそうですね。財政難の危機に陥ったお家の大事を救った名家老との評価があったかもしれませんね。時価会計主義と言う、訳の分からない基準に揺れ動く市場原理主義と言うのは本当に正しいのでしょうかね? 株価の上下は激しく、理論的な価格で評価されていないものはたくさんあります。一時的な異常値を、評価基準にして時代の流れを大きく変える考え方か…。
フェアの精神の為に企業統治の話が生まれ、その主義主張を守る為に苦労している現実も存在します。敗者には敗者の論理があるのだろうし…だから僕らは99%だと言って…成功者の1%の象徴としてウォール街の公園でデモが起こるのでしょう。でもスティーブ・ジョブズが称賛される人間社会は面白いですね。
2011年12月10日
日銀短観より
最近、日本経済の現状レポートを作成しているので、今の日本の状態をみつめ直す機会が増えています。例えば日本の失われた時代を象徴する資料の一つを掲示します。日銀短観には貸し出し態度と言うアンケート調査がありますが、大企業、中堅企業、中小企業へのアンケートを実施しています。大企業は概ね問題はありませんが、問題は中小企業です。下のグラフを見てください。
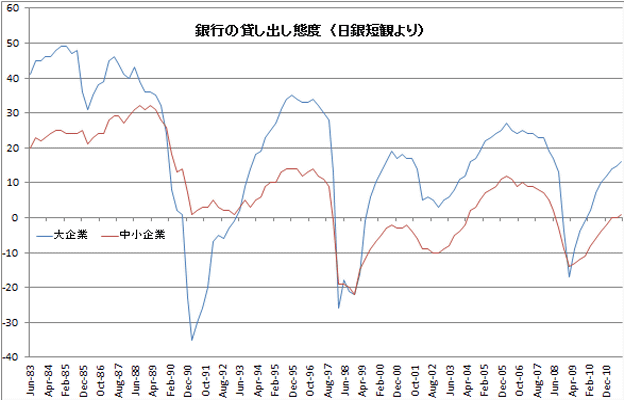
どうでしょう。一貫して中小企業への貸し出し状態は厳しいと答えている人の割合が、一貫して多いマイナス状態が定着しています。2004年から2007年は改善されています。バブル崩壊による貸し渋りや貸しはがしが問題になったのは1998年の時期ですね。しかしITバブル崩壊からの落ち込みは小さく、外国資本の力で景気は復活します。
この時は欧米の銀行は金融デリバティブ機能を拡大させ企業買収を盛んにします。その恩恵を日本も受けて景気が浮揚します。代表的な事例は2006年の3月にソフトバンクがボーダフォンを買収する事例でしょう。小が大を飲みこむ効率化経営が絶頂期を迎えます。このような背景に怯え2006年に新日鉄は銀行との間に、折角、解消した株式持ち合いを復活させるのです。何も企業統治はオリンパスだけの問題ではないのです。非効率な企業の経営を変えることで、効率化が加速すると言う金融経済が実体経済を上回る金融バブルの時期ですね。間もなく、行き過ぎた金融デリバティブの反省が起こります。米国ではサブプライム・ショックからCDSの崩壊ですね。

貸し出し態度だけ見ていると実感できませんが、同じく短観には資金繰りはどうかと言う項目があります。その中で中小企業は一貫して資金繰りは苦しいと答える人が多いですね。バブル崩壊以降、一回も改善されていません。これが「失われた時代」の現状です。昨日、掲げましたが可処分所得が増えないとこの感覚は変わりません。名目成長率の考え方がいかに大切か?資産価格の状態がいかに大切か? 日々の生活の他に潤いがないと駄目なのですね。日々の生活は給料所得で賄えますが、そんなものは消化するだけの食べ物と一緒です。
人間生活での資産とは土地や家であり株式ですね。土地と株は人間生活の二大資産なのです。資産デフレが改善されない限り潤いはないのです。「今日の市況」と合わせてみると、よく分かると思います。重視するのは名目成長率なのです。その為には資産デフレを止める政策が必要なのですよ。簡単なんですよ。株の損失を所得税から控除できる法律が生まれれば、所得のある人は冒険しますね。上手く行けば大儲けできます。合わせてキャピタルゲイン税は10%なら大儲けのチャンスが生まれますね。投資に失敗しても所得税が減りますね。チャレンジ精神が生まれますよ。合わせて日銀は毎月、理論価格までETFを継続的に買うのです。下値ではないですよ。上値でも毎月吸い上げます。土地に対する売却税も軽減させます。投機を奨励すればいい。土地担保融資を復活させればいいですね。眠っている土地資産が金融経済を拡大させ、実体経済への投資活動は増えますね。
何故、政策の変更で豊かになるか?
最初に掲げた、いや、資金繰りのグラフでも良いですね。バブル崩壊による日本経済の調整は1998年から1999年に終わっています。その後IT革命でITバブルが起こります。しかし再び二番底を入れますね。そうしてみずほは58円を付けます。この後欧米金融の力で日本経済は小泉・竹中改革の評価もあり復活しますが、ブルドックソースの問題や先ほどの新日鉄の株式持ち合いなどの揺り戻しが起こります。加えて欧米では金融危機が起こり、景気後退に陥りました。しかし中国の大規模な財政出動などで金融危機の回復が図られますが、今度はその財政出動の咎めで欧州危機に起こっています。
つまり1989年のバブル崩壊からの整理に10年かかり、ITバブルのIT革命で景気は復活しますが、行き過ぎた金融デリバティブの拡大が咎められ、金融危機が起こります。今はその金融危機の二番底である財政状態を咎めて欧州危機が起こっていますが、おそらく大きな落ち込みにならずに新しい景気浮上が起こりますね。世界人口は70億人以上に膨らみ世界は成長しているのです。今日は日銀短観の調査からみた経済状態を考えてみました。グラフの数字推移は良く景気実態を示しています。株価は最低状態ですが、資金繰りなどの実体経済を見れば恐れる事はなく、日本は意外に強いな。と実感できると思います。最後にROEの高い企業を掲げておきます。
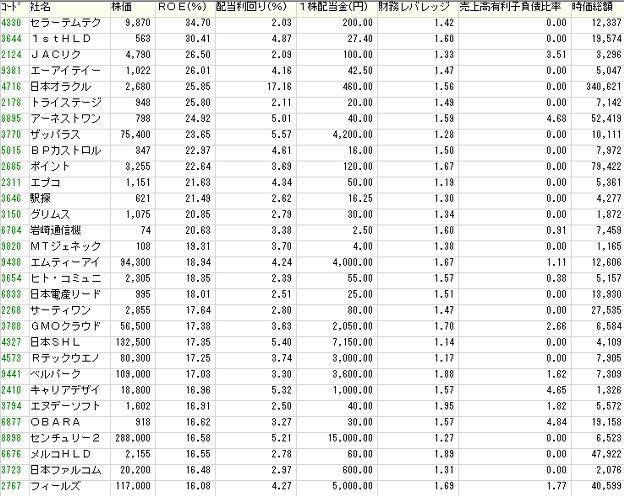
2011年12月03日
二者択一か…
今日は昨日の冒頭で書いた『情報と言うのは総合的に組み合わせていくと色んなことが見えてくる。』と言う部分を具体的に書きます。未来の株式相場、所謂、市場の流れを予測するには過去から現在に至る流れを確実に捉えておかないと延長線上の動きで進んだ場合、今後どうなるか見えてきません。
例えば日本がTPP交渉に参加の意思表示をしたら、カナダやメキシコが参加してきました。米国では増大する財政赤字削減に向けアフガニスタンからの撤退を含め軍事費の削減に動いています。一方、中国は空母の建造を含め軍事力の増強を務め、至る所で覇権の橋頭保を築いていますね。最近、北極圏に接する国アイスランドの土地300平方キロを買収してリゾートを建設する中国人富豪の計画をアイスランド政府が許可しなかった話は、軍事も膨張を続ける中国への警戒が背景にあったと言われています。南沙問題も日本の尖閣諸島と似たようなもの。アフリカを始め、至る所で反グローバル的な政府に近づきロシアと共に拒否権を連発しています。
大使館員の引き上げを決めたイギリスとイランの関係は今後の国際舞台の焦点になるでしょう。米国は確かに覇権主義とも思われますが、沖縄返還を見れば同盟関係に入ればかなり譲歩しますね。今はミャンマーとの関係が焦点になっていますね。ミャンマーの影には中国の存在があります。このミャンマーにクリントン国務大臣が訪問したのも一連の中国包囲網に対する動きでしょう。この背景は8月に米国防省に新設された「エア・シー・バトル・オフィス(Air-Sea Battle Office)」の存在があります。「エア・シー・バトル」とは、米国が「A2AD」すなわち米軍が特定地域への「接近阻止(Anti-Access)」「領域拒否(Area-Denial)」に対抗するため策定した空・海統合作戦だそうです。仮想敵国中国に対する部署ですね。
だからこそ沖縄の米軍基地の移転問題の解決は急がねばなりません。昔、米ソ冷戦があり今は米中冷戦が生まれ始めています。米国の手法はIMFやIAEAなどの国際機関をコントロールして世界の動きに統一性を持たせることなのでしょう。日本が中国に組するか、米国か? あるいはイスラムか?と選択を迫られれば、やはり沖縄返還を実現した米国でしょう。北方領土を返還しないロシアが冷戦競争に負けるのは自明の理です。コーランを拡大解釈し聖戦などとジハードを曲解するイスラム原理主義より、市場原理派の方が理に適っています。
これからは嫌でも難しい選択を迫られます。その時に迷いますが、二者択一の結果が失われた時代背景に繋がっています。橋下さんの誕生は中央政権下での改革が進まないから、地方から改革を成し遂げようとする下剋上の選択でしょう。
どの株が上がるか?を考え株式を選択するときに、世界の流れを見据えることは非常に大切ですね。GDP世界第二位になった実力者の中国は過去の歴史から見れば大国ですね。僕らの認識は清朝没落からのほんの一時に過ぎません。過去、日本は遣唐使などを派遣し文化の指導を得てきました。ある意味で親中国派の小沢氏の考え方は、ドルの基軸通貨体制が崩壊する現在の流れを捉えているとも言えますね。非常に進歩的ですね。だからこそマスコミ操作で下地を作られ、地検を米国発で動かされ力を抑えられたのでしょう。
今後、米中冷戦の始まりになるのか?
その中で日本はどんな選択をするのでしょう。残念ながら、冒頭の「情報と言うのは総合的に組み合わせていくと色んなことが見えてくる。」と言う解説を上手くできませんでしたね。…と言うことは、僕自身、まだ考え方があやふやなのですね。正直、昨年、僕は悩みましたね。証券マンでは食えないと思っていましたが、会社を辞める選択が正しいかどうか…でもベンチャリの失敗は繰り返したくないし…。パラダイムショックの時代だから選択は非常に難しいのですね。でも変化を恐れては駄目でしょう。ジリ貧より、思い切って何かにチャレンジしないとなりません。