« 2011年12月 | メイン | 2012年02月 »
2012年01月28日
RSI
今日の株式教室はテクニカル論を展開する予定です。僕にとっては屈辱ですね。本来はファンダメンタルでの判断が基本ですが…こんな事をやることは、あまり意味がありません。目先の株価の予想など、誰にでもわかるものではなく、単に過去からの確率論に過ぎないからですね。しかし不確実性が増すグローバル化への移行の中で、システム売買の運用成績が好調で、バフェットのような王道の投資が負け続けているからです。日本は特に後ろ向きのデフレ社会ですからね。企業物価と消費者物価の話が日経に載っていましたが、価格転嫁が出来ない後ろ向きなのですね。つまり勝ち組は限られる社会です。基本は総体的には沈み、部分的に活躍する場でしょう。「ゾゾタウン」のビジネスモデルは世界で通用するパターンでアジア展開を急いでいます。日本の誇るインターネット・コンテンツと実体経済の融合です。技術革新による先進国型の変化が育っています。まぁ、自民党も馬鹿ではありませんから、森政権がIT投資を進めた延長線上の成果でもあるのでしょう。代わって菅内閣の選択は、日経トップの電力会社の1兆円超えの赤字ですね。国民一人当たり1万円の損失ですね。安心・安全は必要だが、線引きは難しい問題です。貿易赤字に転落し食えなくなっても建前論を押し通すかどうか…理想と現実の狭間の選択ですね。私など何も急がなくても…浜岡原発の対応を批判しました。どちらが正しいのでしょう。
さてゴタクは兎も角、今日は最近勉強しているテクニカル論、アルゴリズムなる投資のお勉強の話です。なかなか奥が深く簡単にアイディアが見つかりません。僕の勝手な解釈ですが、アルゴリズム投資と言っても幅が広く、定まった言葉の解説はないのでしょう。最近はネットが発達し、コンピュータ機能が向上し、複雑な計算も瞬時にできますから、リアルタイムで数学を用いてイレジュラーな動きに追随するパターンから、そのオーバーした異常な動きを捉え、逆張りするパターンなど、色んな形が考えられます。株式だけでなく為替や資源価格を組み合わせた投資など…。ようするにアイディアは無限にあり、そのアイディアの実験をするのがアルゴリズム投資なのでしょう。先日の報道ではネット上の溢れる言葉の数から、特定の文句を選び、日経平均株価を予測するソフトを売り込んでいましたね。何でもありですね。要するに自分の考えるアイディアを用いて売り買いする方法を総じてアルゴリズムと呼んでいるようです。現在の比重はおそらく7割以上の売買が目先投資なのでしょうね。ディーリングをしてみると分かりますが、概ね、追随型の順張りの方が成績は良いようですね。要するに、その日、株が高ければ買いから入り、安ければ売りから入るパターンで現状を容認する投資です。トレンドを重視するわけです。
この特性に鑑み、私はオシレーター系のRSIと言う相対力係数に注目しました。広く一般化されていると言うことは多くの人が経験値で選んだと言う評価でもあるでしょうし、計算の方法がシンプルで人間心理に合っているように感じますね。人間と言うのは感情の動物で自分の持っている株が上がればうれしいし、下がれば哀しく感じますからね。要するにRSIは値上がり幅と値下がり幅の二つの割合を、0~100までを指数化した数字ですね。値上がり幅を(値上がり幅+値下がり幅)で割るわけです。あとは期間の問題で14日間が一般的ですから、この期間は経験値に基づくものでしょう。過去14日間、値上がりすれば100になり、値下がりすれば0になります。その割合ですね。
先日、日経新聞に報道されていましたが、コマツは12日間の連続値上がりで終わりました。惜しかったですね。僕は9連騰で売り始めましたね。でも損を出して踏んでいますが…。確率論の問題ですね。おそらく200日線をクリアせずに調整かな? 何度もIRNETでは先導株として東京エレクトロンを掲げています。此方が今回の欧州危機からの回復で先行した銘柄ですね。同じような展開が、TDK、ホンダ、コマツにも当て嵌まると想定しています。コマツの株価回復が遅れているのは政府系の社会基盤整備関連だからでしょうか?考えてみれば分かりますがインフレ・ターゲット論の採用は設備投資を促進させますから、エレクやファナックなどを押し上げる時代的な背景を持っていますね。一方、同じ設備投資ですが、コマツはどちらかと言えば新興国派です。政府系の社会基盤の比重が大きいから2007年のようなスケールはないのでしょう。
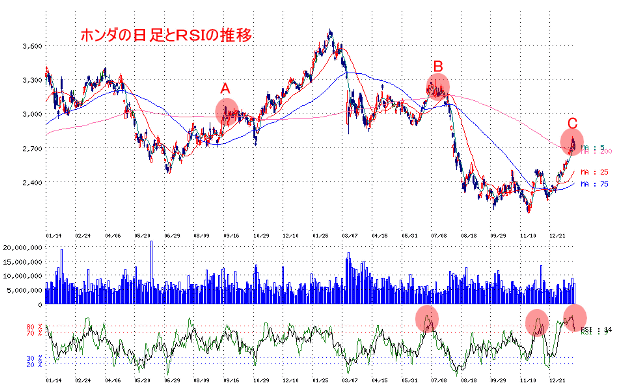
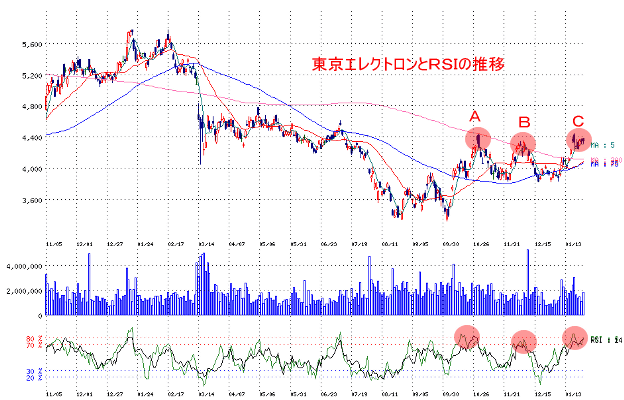
新興国開発のグローバル化を読んでいれば、2003年~2007年のコマツの大相場に乗れたわけですね。でも僕はあの時は銀行を手掛け、国内に拘りがあり、失敗を犯しています。グローバル化の概念が希薄だったのです。やはり大きなスケールのバックボーンは大切ですね。小泉・竹中改革で日本はデフレを脱して効率社会に移行すると言う想定は2006年からの既得権勢力の巻き返しにより幻想に終わりました。2番底とはよく言ったものですね。1989年から2003年、折角、巻き起こった改革の痛みが既得権勢力の巻き返しにより藻屑に消えました。2006年からの2番底は未だに続いています。まだ先が見えませんね。過去の幻想を断ち切る為に行財政改革が断行されないと時代の変化を認識できないのでしょう。消費税の引き上げと公務員改革法、こんなもんじゃ…株屋の痛みは理解できないでしょう。国債の消化難になり炎上しないと駄目なのでしょうかね?
何か、NECやパナソニック、ソニーなど…間もなくトヨタも同じようなものでしょう。ソフトバンクには期待しているのですが…どうかな?冒頭に掲げたゾゾタウンのグローバル化を応援していましたね。おそらく先進国の技術革新は情報化の支配ですよ。文化の香りが生まれ始めています。最近のユニクロは価格破壊のイメージがすっかり消えましたね。内外価格差の解消を目指したユニクロやニトリのイメージが変わり始めています。長く続いた内外価格差の是正であるデフレが終焉するのでしょう。スイスのような選択もあったように感じますが…過去を悔いても仕方がない。ネット文化は我が国が誇る先端技術の結晶で情報化がキーワードになっていますね。皆が参加する社会化現象です。唯一のインフレ型のやる気が溢れる社会ですね。既得権力者が存在しない為に成功できる確率が高いのでしょう。ただ今回のゲームの様に社会規制の問題は常に出てきますが…2006年と同じ選択の失敗を犯さないで欲しいものです。
冒頭のテクニカル論は述べようと思いましたが、グラフ等を作り解説するのが面倒になってきましたね。ほぼ2週間の上昇で強い銘柄は200日線をクリアして株価波動を変え始めています。基本的にはECBやFRBの政策が過度の警戒感を解いた結果ですね。しかし予断は許せませんね。綱引き状態だからですね。ECBの大量の資金供給は実体経済には回っていません。米国はGSEの問題が片付いていません。どんなに頑張ってもこれだけの資産価格の下落調整が短期間に済む筈がありません。3割の価格下落を埋める為に3%成長を10年続けねばなりません。日本は政策対応が失敗し14年の歳月がかかりました。収益還元法価格になっても地価は底這い状態ですね。流動性の罠は続いています。だから金融規制を問う事は必要だが急いではなりません。理想と現実の選択か「トリレンマ」とは…奇妙な響きですね。米国はまだ5年ですからね。はたしてインフレ・ターゲット論だけで、設備投資に火が付くかどうか…。市場と言うのは欲張りですからね。押したり引いたりする綱引き状態はまだ続くのでしょう。
2012年01月21日
問われる対応力
最近、米国では住宅投資が復活している様子で、中古住宅販売の在庫数が適正水準の6.2か月程度まで下がってきたと言う。ただ統計資料もいい加減なもので、途中で集計の仕方を変えるらしく、歴史的に継続的な検証が難しくなっている。3年程度は併記発表してくれるといいのだが…統計資料は時代に合わせ集計の仕方を変えるので、通常は僅かな修正にとどめるべきだが米国の中古住宅販売数はかなり以前の発表の数字と違っているらしい。
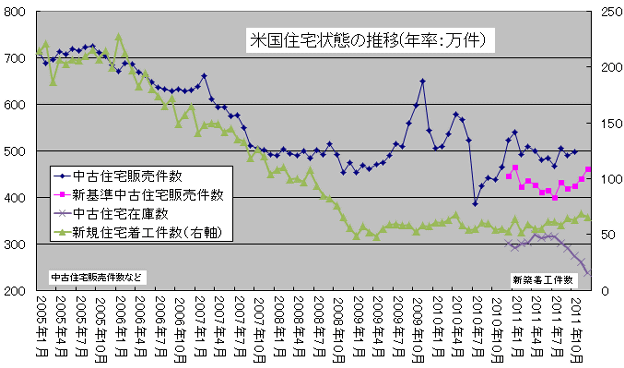
世の中の変化を、自分の生活に取り入れることが出来る人間と、なかなか自分の殻を変えられない人間がいる。東証はオリンパスの上場維持を決定したがライブドアと一体、何が違うのだろう? むしろ本体の決算を長くに渡り偽った罪は重いと思うが…。IHIは粉飾数字を元にして増資を実行し詐欺の片棒を担ぐ東証と批判したが、ルールは自分達の都合により変えられフェアな精神は消えるらしい。東証と大証の統合もその事例だが…僕はこのような事例を見るたびに、日本には本当の意味でフェアな環境でなく市場原理が根付かない原因の一つではないかとも考えるが…僕の考えはきっと間違っているのだろう。
でもオリンパスは上場が維持できてよかった。本来は善意の投資家が損失を被る処置をとるべきではないと考えている。だから今回の事例を見て、もしライブドアの株主が東証を相手に訴訟を起こしたら勝てるのではないかと考えるが…そんな暇な人間は居ないのだろう。最近、この年になって自分の性格がようやく分かり始めてきた。考え方の基本は人間が生きてきた生活感に影響を受けるのだろうが…もともと外務員などは捻じ曲がった精神構造なのだろう。長い相場の低迷で時代に合った投資が必要なのだろうが、僕はずっと従来型の教科書通りの投資感覚を抱いてきた。でも米国と違い日本は市場原理主義に、一線を置く考え方。どちらが幸せなのか分からないが…。
時代の対応に合わせ、自分の考え方を変化させ、投資方法も変化させるべきなのだろうか?どう考えても理屈に合わない安い株価が存在すると…通常はTOBがかかり儲かる筈なのに、この手の投機資金を否定し続け、ブルドックの問題が発生し、最高裁の今井判事はブルドックを支持した。よって海外投資グループは、日本株に一線を引いたのがブルドックから発生した日本株の悲劇。このような事例はたくさん存在する。オリンパスは上場を維持できたのは、きっと個人の不正な蓄財はなく、菊川さんが純然な気持ちで会社を愛していたのだろう。業績推移をみれば素晴らしい経営者の一人だろうが…根底の部分で、昔のお家大事の家老職だったのだろう。
株式投資をしながら世の中を考えると、色んなことを考えさせられる。理不尽な処置もたくさんあるし、理解できない現象もたくさん生まれる。市場経済はそのようなドラマが見られ市場を通じてルールが決められていくのだろう。今回の欧州危機も厳格に財政規律を問うなら解決の道は財政の統一で政治体制も一本化すべき話。ユーロ加盟国は1国になるべきだが通貨だけを共有しようとしたことに、問題の発端がある。この歪をついたのが市場経済だ。そうして格付け会社を使い、市場関係者は正義? 市場のルールを追求しようとする。金融危機が発端になり、膨れ続けるCDSの残高を見て、この投機を戒めたのがBIS規制。
日本はバブル崩壊で体力もなく、このお祭りに参加する力がなく被害を免れたが…。日本はもともと右肩上がりで総資産経営を実施してきたので、資本の価値観、効率化と言う概念がなかった。故に売り上げ至上主義に陥り、シェア争いをしてきたが、その間違いが双日などの結果に現れ、価値観が大きく変化している。この総資産経営の枠組みを変えようとしているのが、みずほだろうが…未だに体質は依然のまま…パナソニックなども…多くの会社がまだ時代対応に変化しきれていない。
野村本体がイタリア国債投資のリスクを取らずに、この提案者は野村を去ったけれど…野村らしい選択だと思ったね。でもリーマンを買収するようなリスクも平気で犯し、僕にはチグハグな展開に見える。野村のやくざ絡みの損失補てんの結果、証券業界は政治力を失い日本は過剰なコンプライアンス規制に突入し、現代にいたる。その結果、産業資金の有効活用が消えたようになっているのも、銀行が融資をしなくなり国債投資をするのも、日本の活力を奪っている。お金など使うものだが…どこか曲がっている。ずいぶん長い時間、堅実派とよばれる人たち清貧思想の世界が続いているが…どこで変化するのだろう。
日経新聞は微妙に姿勢を変化させている。あれほど欧州危機を煽っていたが…ユーロが買われ微妙にコメントを修正し始めた。これ以上、叩けない位置にある株価が僅かな買い物、いや、売りが減ったと言う安心感だけで、急反転し出している銘柄が多く存在する。市場に合わせた目先的な対応と、自分の生き方とのギャップを大きく感じるが、やはり時代に合わせ自分を変化させるのが正しい生き方なのだろう。いつまでも負け犬の遠吠えは続けていられない。
2012年01月14日
市場原理
世界経済の状態を見るには、いくつかのアプローチがあるのでしょう。例えばフィッチがフランス国債の格下げを年内は見送ると発表しましたが、昨晩はS&Pが格下げをすると言う観測予測が報じられています。市場関係者は自分の独自予想を常にニュースの結果である事象によって確かめています。フィッチの発表では思うような反応をしてないから、もう一度、ユーロ圏を叩いてみるのですね。これで先の安値を割るような下げを演じるなら、まだ欧州問題は改善が必要だと言うことです。でもこのように脅しても下げないようなら、今までのECBのやり方で充分だと市場が判断したことになり、新たな政策を求めなくなり次の段階に進みますね。しかし、市場が安値を割り込むようなら新たな対策が必要だと言うことですね。これが市場原理の市場経済です。
市場経済とは…様々なニュースに対応する様子で結果が決まります。選択と結果ですね。問題が生じた時に正しいアプローチでないと市場は反乱を起こし株価が暴落したりします。正しい選択なら株価は上がりますね。これが市場原理です。基本的に市場は常に政策などの選択を評価する場で、その結果を表している体温計のようなものです。そうして基本的に適度なインフレ状態を保つことで成長を続けてきました。人間心理そのものです。「明日は今日より良い生活を…」アメリカンドリームはまさにその体制ですね。無名の若者が大金持ちになるアップルのスティーブ・ジョブズのような英雄が生まれ、その現象に憧れ皆が努力する。これが市場経済です。だから希望を与え続けるには、市場が正しい評価を下し社会に刺激を与えねばなりません。
選択と結果の評価を下している場が、市場と言うことです。経営者は株価の高安で経営の評価を下され、国の政策は株価全般や名目GDPの水準で評価されます。日本は面白いですね。国民幸福度なんか…負け犬の遠吠えに聞こえます。きっと今の僕の心理も同じでしょう。思うように動かない政策に苛立ちを覚え、ずいぶんな時間が経過します。まぁ、歴史を見れば20年程度の低迷は短い時間ですね。権力闘争に明け暮れる自民の態度は変わらない現実を感じますね。自分たちが行った政治の結果、残した負の遺産である借金なのに…まだ権力闘争をしています。反省の欠片もない。本日の日経新聞には亀井静香の悪政である「中小企業金融円滑法」の事が載っています。100社のうち、5社または7社しか復帰しない博打を許容する法律です。
このような間違った選択を繰り返しているから市場が沈みますね。また1年先送りです。当然、市場は低迷を余儀なくされます。66兆円は、今の日本にとって大きな金額ですね。3メガバンクで金利が1%の上昇で2兆円が飛ぶのだそうですね。7%になったら12兆円の損失を被りますね。昨日、三菱UFJの業績を載せて株価が騰がらない不思議の解答ですね。間違った選択を繰り返す能力のない官僚と政治家を打破する可能性があるのが橋下大阪市長で彼だけに期待を背負わせるのは可哀そうですね。誰かが後押しして上げないとなりません。
野田政権の閣僚メンバーをみるとガックリします。相変わらず派閥の力量の上での産物です。…と言うのは田中直紀の起用です。小沢さんに、何故、支持が集まるのか分かる気がします。角栄が「こいつを頼む」と言い、駒形さんに預けた経過を知っている人間としては短命内閣を読んで小沢さんらしいバランスが働いたのでしょうね。考え過ぎかな…創生会結成のお詫びかな?と人事を見て考えました。枝野さんは留任ですね。東電も政治力がなくなったものです。折角のチャンスを逸しましたね。これを見て分かることは既得権力者の時代も終わりつつあると言うことで、新しい幕開けが近づいているのでしょう。岡田さんの真価が問われる局面ですね。
まぁ、内政はどうでも良いのです。容易に片付かない金融危機の対応は二番底を付けて立ち上がるのかどうか…米国の金融株の動向が注目されます。日本は2013年にBIS規制が強化されます。欧州危機はその為の準備ですね。所詮、金融機能が正常に働く状態にならなければ、株式が力強い上昇をするわけがありません。買い一本で臨む以上、待たねばなりませんね。亀井静香の負の遺産処理やBIS規制など…また超えるべき課題は多くありますね。でも米国金融は下のグラフのように注目される位置に来ているようです。きっともっと掘り下げて解説しないと皆さんには理解出来ないかもしれませんね。日経に太郎君の記事が載っていましたね。今年の有望株の一つですね。短期で2倍程度まで可能性がありますが…仕掛け人が存在するかどうか。
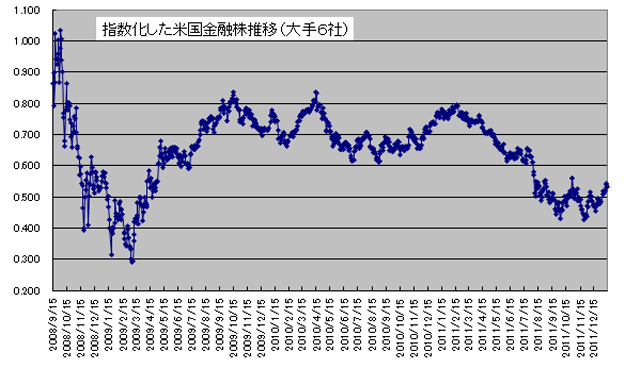
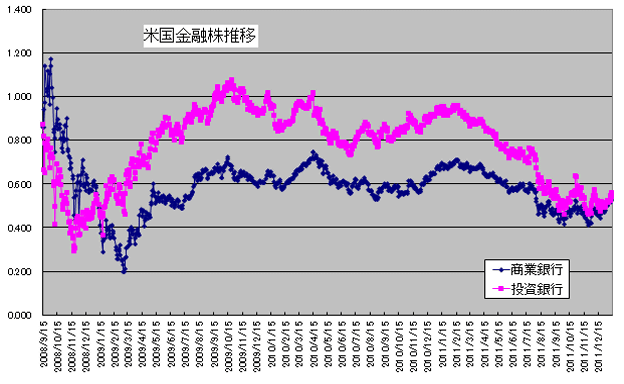
2012年01月07日
欧州危機
年末年初にユーロ安が進行し欧州危機を煽っているように見えますが…本当でしょうか?
そもそも欧州(EU)は世界最大のGDPを誇る国(地域)ですが、日本にとって最大の経済相手は中国なのですね。2番目が米国、そうして3番目にEUなのです。下の表はデータをまとめたものですね。参考にドイツとイタリアも付け加えました。本当はEUと米国に中国とインドだけでいいと思いますが…今日は欧州危機の話しなので…。

日本での一般的な火付けは、昨年の11月頃からですが株式市場では8月頃に顕著になりましたね。昨年の春頃から米国の二番底説が、日本の震災の影響もあるんじゃないかと言われ、疑われ始めたのですね。事実、この仮説はある意味で正しいのでしょう。何故なら自動車販売がトヨタとホンダは落ち込みました。日産は軽微でしたからね。
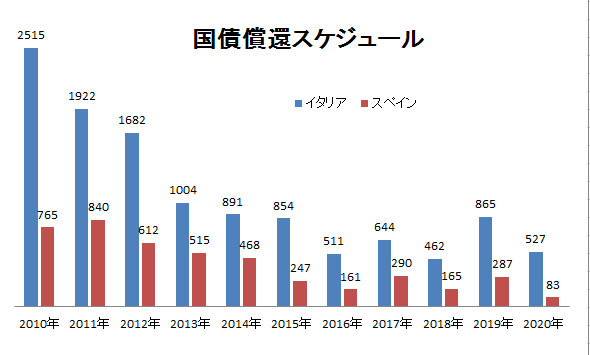
私は昨年末にECBが3年物のオペを実施したので、この問題は終止符が打たれたと考えています。理由はECBが銀行を通じて資金提供することで、間接的にソブリンリスクを軽減しています。懸念されているイタリアとスペインの国債の償還スケジュールを掲載しましたが、この数字はブルームバーグから引用されています。この数字が正しいなら欧州危機と騒ぐ方がおかしいですね。FRBは自らが国債を買い入れ流動性供給をしました。この意味は米国の銀行の民間融資を促す狙いと、基軸通貨の役割である世界経済への流動性の供給ですね。その為に一部資金は投機に流れ、商品指標が上がりました。故に打撃を受けやすい中国が米国を非難したのです。ECBは銀行に直接、低利融資しましたから、目先の資金繰りを助け、銀行へ間接的に利益を与え援助しています。何故なら1%のユーロをイタリア国債に投じれば7%になります。6%の鞘が生まれ50兆円規模ですから3兆円のクリスマスプレゼントです。
ユーロが売られるのは相対的にEUの経済支援をする市場原理ですね。ドイツが一番恩恵を受けますが、ドイツは欧州各国の移民を受け入れ、間接的にギリシャやイタリアを支援する事になります。また通貨リスクの経費を払わされますからね。市場原理はユーロ安になることにより輸出を助けますね。あまりやり過ぎるとインフレを招きますが、今の所、消費者物価は落ち着いています。物価が落ち着いているならドンドン資金を入れればいいのです。FRBのドル資金に続き、ECBのユーロ資金は世界経済に供給され世界のGDPを押し上げます。世界人口は拡大を続け70億人を突破したのですね。しかも中国やインドに代表させる人達の生活水準を押し上げますね。これが市場原理なのですね。日本は間違った選択をしているから、失われた時代を強いられているのです。お金の価値を大切しても豊かになりません。
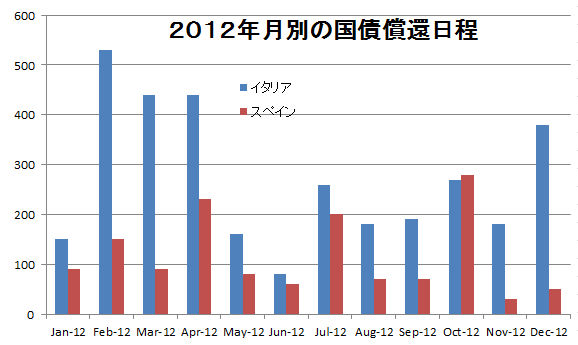
それではいつまで今の欧州懸念が続くのかと言えば…私は1度目が信じられなかったので…(世間から支持を得られなかったので)2度目の注入時期である2月末に、再びECBは資金を供給すると言っていますし、イタリア国債の大量償還が2月から始まるので、この時期が峠かな?とも考えていますね。上記資料は三菱総研からだそうです。フランス国債の引き下げの前にハンガリーが炎上ですか…。日本人は悲観的な国民ですね。米国は持ち直しているのに…。だから冒頭に正しい数字の表を掲げたのですね。GDPの脇にある%は世界シェアの割合で、輸出入の%は関連を分かりやすくするために、日本全体の貿易額の%を用いました。PPP(購買力平価)を掲げたのは、この数字が正しい消費の能力を示していると思うからですね。PPPとGDPの差が少なくなれば、当然経済成長力は落ちますよ。だからインドにも魅力がありますね。
市場の行き過ぎる動きは、良く見られますが、正しい数字を基にして考えれば、悪戯に市場価格に怯えずに済みます。だからチャンスになれば、果敢に挑戦できますね。確かにEUは世界から見て巨大なので、欧州の景気が冷えると世界景気にも影響を与えます。しかし私は米国、そうして、これから緩和政策が実施される中国の上昇分が、はるかにEUの落ち込み分を埋め、プラスに働くと思いますね。忘れてならないことはFRBやECBが巨額資金を投じたことで、他の新興国経済を支えることですね。日本には人口が2億人を超えるインドネシアなどの躍進する途上国が、周辺に豊富に存在するのです。ミャンマーも米国の経済制裁が緩和されるでしょう。ベトナムだって…成長する国はタイだけではありませんね。日本は震災復興に湧き、バラ色なのに…何故、問題解決される方向にある欧州危機を悪戯に怯えるのかな?メディアは少し真実を見つめ直すと良いですね。