« ここからが…正念場 | 最新の記事 | 事件への興味 »
カンフル剤の効果は一時的…(2012年04月07日)
世界の中央銀行による金融緩和の呼び水現象で、本物の景気循環に繋がるかどうかの瀬戸際にいます。通常、金融機関の痛みがなければ、金融機関自身にリスクの許容度がありますから、中央銀行の資金供給や財政出動(例えばエコカー減税もその範疇)などで、銀行からの貸し出しが伸びて企業の設備投資が始まり、やがて雇用がひっ迫し賃金が上がりますから消費が増え、その消費が更なる投資を支える好循環の成長過程に向かいます。
ところが現実は、金融危機の影響で銀行の損失が大きくて、銀行自身がリスクを取れませんし、さらに自己資本規制(BIS)により貸し出しなどの総資産を増やせません。だから企業が増産投資をしたくても銀行が慎重になり、なかなかお金が動きません。折角、緩和政策を実施しても、なかなか景気が浮上しないのが現状です。日本の場合は、更にコンプライアンス規制が過度に効いており、銀行が委縮していますね。
ただアップルの配当復活や自社株買いは、勝ち組のキャッシュリッチ企業の融解姿勢を示すものですね。多くの優良企業は将来の景気落ち込みに対する対策として現金ポジションを積み上げていますが、アップルのように外部に流し始める企業が現れ、VWのように増産投資をする企業も出てきています。日本の東レもその仲間ですね。
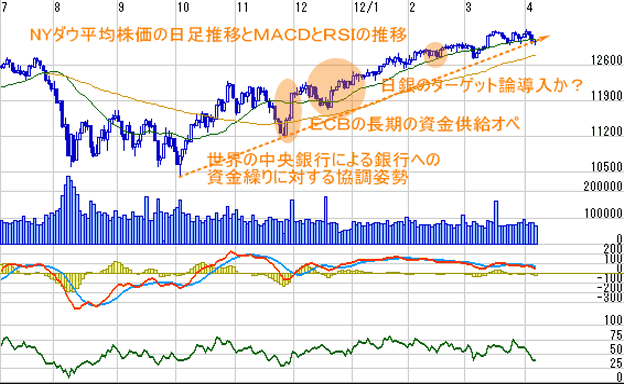
NY市場の株価を見ると…、昨年10月初めより上げ続け約6か月間、上げ続けました。背景には景気回復などの経済指標の好転がありますが、最近は好材料に反応しなくなり、悪材料には敏感に反応しているようにみえます。雇用統計値の発表を受け、来週の動きはどうなのでしょう。FRBはこれまで株価が下がると、必ずアクションを起こしてきました。株価は景気指標に反応し、その反応を見て機動的に金融政策を変化させます。財政政策もそうですね。減税などオバマ政権は継続しています。米国は市場原理が働き、市場動向を見て政策を変化させています。これが市場原理主義です。しかし日本は社会主義的な計画経済の色彩が強く、計画に狂いがあっても政策をなかなか変化させません。仮に変化させても、規模が小さく反応が遅いから、市場の動きの後追いになるだけで、なかなか効果が出てこないのです。だから失われた20年と呼ばれるデフレ時代が続きます。つまり名目GDPより実質GDPが高い、異常な状態が続くのですね。故に円高傾向が続いています。
さて今の焦点は、何度もお話ししているように…世界同時の金融緩和姿勢を日銀も続けるかどうか…先日、為替が円安に振れ、円・ドル・キャリー取引が復活したのは、日銀がインフレターゲット論を採用するとのアクションを起こしたので、お金が動き株価も反応しましたが…長い期間、日銀に騙されているから市場関係者は疑心暗鬼なのですね。事実、『自民党の茂木敏充政調会長は4日午後の記者会見で、日銀の金融緩和について「緩和と言いながら資金量が明らかに減少している」と批判した上で、白川方明総裁の最近の発言に関して「国内で金融緩和と言いながら、海外では金融緩和の副作用を話している。国内外で言っていることが違う。こういったことは国会でも厳しく議論していかないといけない」との考えを示した。』とのニュースが伝わっています。先日の河野さんが人事で否決され…今までと少し様相が変わってきています。
ただ野村証券が下値を切り下げ、みずほが再び公募価格の130円を割れるところを見れば、市場は来週の金融政策決定会議では、日銀は動かないとみているのでしょう。株価を上げることも、さらに土地などの資産価格を上げることも、日銀の姿勢で大きく変わりますね。FRBは少し株価が下がると、不胎化QEの話が出てきたり、常に市場動向を見てアナウンスメントを発しています。だんだん環境はインフレに動いているのです。日銀が抵抗しても、最後は20年にも及ぶ失われた時代の代償を払うことになります。だからこの失われた時代を生き残れば、資産インフレ産業の株価は大きく上がるのですね。何しろ収益還元法でも株価は上がらないのです。本当は日銀だけの責任ではなく、金融庁の指導が間違っているのですね。この点は、まだ国会では話題になっていません。でも一番は日銀ですからね。でも金融庁の後遺症も相当に根が深いのです。景気を浮上させることは簡単ですね。人々に希望を与え、リスクを取れる環境にしてあげれば済むことです。さて来週はどんな動きになるのでしょう。市場は依然、調整段階が続いているようです。