« 2012年05月 | メイン | 2012年07月 »
2012年06月30日
時機到来か?
欧州問題では、EUの共同債や銀行同盟も見送られましたが、銀行監督の一元化やESMによる金融機関への資本注入が決定されたようです。何やらスッキリしませんが市場は好感したようです。基本的にドイツなどの優良銀行が資本投下して買収するような形ですね。国を通さないのは二重の負債を回避するためでしょう。更に利回りが上昇しているスペインやイタリアの国債の買い入れも盛られたようです。やはり抜本的な対策ではなく市場がもう一度、催促するのかどうか…。欧州問題はしばらく様子見になりそうです。成長戦略の12兆円程度の規模では金額は大きくないですね。どのような使い方をするのかが重要なのでしょう。日本のように掘っては埋める生産性の欠けた財政出動では逆効果になります。
野村などのインサイダー事件の日本の処罰は軽すぎますね。インサイダーは通貨の偽造と同じ事で、市場原理の根幹を揺るがすものですから厳罰が当たり前です。米国では禁固20年とか…日本も厳しく望まないと市場原理を歪めます。後出しジャンケンを認めれば、市場参加者はどんどん減ります。いかさま賭博のようなものですからね。
いつも新聞を見ているつもりですが、消費税の一体改革の姿が報じられたことがあるのでしょうか? 小沢一派の民主党離脱や新党結成などの文字が踊り、肝心の政策の中身が見えません。如何にも日本村の論理です。まぁ、兎も角、欧州首脳会合では一定の効果は出ているようですが、やはり僕は釈然としませんね。S&P500の上昇幅は33.12の1362.16だそうで、今年、一番の上げ幅だと言います。日経新聞には不動産投資促進へ税優遇となっており、あとでゆっくりと新聞を読んでみようかと考えています。日本の地価は、おそらく買い場なのでしょう。収益還元法価格に見合う水準なので溢れるマネーが動き出しても良い時期です。
小沢さんの行動など…民主党から割れようが、割れまいが、どうでも良いですね。問題は政策の中身です。何故か、日本のメディアは政局ばかりを話題にして政策を正しく報道していませんね。呆れるモラルです。記者は、一応、エリートの筈ですね。文系では比較的給料も高くソコソコの人間が集まる筈です。それにも拘わらず報道の仕方は、いつも視聴率などを重視する3流の内容です。テレビで、ある程度の事は分かりますから、新聞はもう少し深読みをするコラムを設けて欲しいものです。物の見方には二面性等が存在し、いろんな意見がありますからね。
相場は欧州危機や米国の経済対策に注目が集まっていますが、日本の消費税引き上げ法案などは重要なパーツです。どうも大金融相場が始まっている可能性が高いのです。昨年から行われている世界の中央銀行の協調姿勢が過剰流動性相場を演出していると言うものです。昨日、相対比較で日本の銀行は世界でもトップクラスとの主張を紹介しました。経済の要は銀行なのです。日本は1989年からのバブルの処理に手間取り、米国発の金融デリバティブ競争に後れを取っていました。その米国発の金融デリバティブが行き過ぎたのでサブプライムローンが切っ掛けで、米国の不動産バブルが破たんしたのですね。中国も苦しんでいる様子です。スペインも同じ構造です。日本は20年以上もかけて処理してきた土地のバブルは、最後は収益還元法価格で落ち着きます。しかし日本の事例を見れば採算に合ってもなかなか広がりませんね。むしろ地価が更に下がる有様で、含み損の処理を迫られてきました。
しかし…軒並み格付け会社が欧米の金融機関の格付けを下げ、相対比較で日本が浮上しお金が集まる。世界の中央銀行の中で自らリスク犯し、資産投資しているのは日本だけです。日銀はリートやETFを通じて資産価値を高める行動を起こしています。要するに時間の問題だけで需給バランスの問題だけだったのですね。持ち合い株式の比率はどんどん低下し、パナソニックの例もありますが、どうも…あの無借金会社のパナソニックが資産を手放すのです。時期が到来したのかもしれません。代表的な一銘柄は住友不動でしょう。住友不動はここ数年、積極投資を実施してきました。果たして…消費税引き上げから日本の財務官僚は根本的な政策転換を実行するのかどうか…大きな見所は欧州問題でも米国の景気問題でもなく、日本の政策問題が最重要の見所だと言うことを忘れてはなりません。
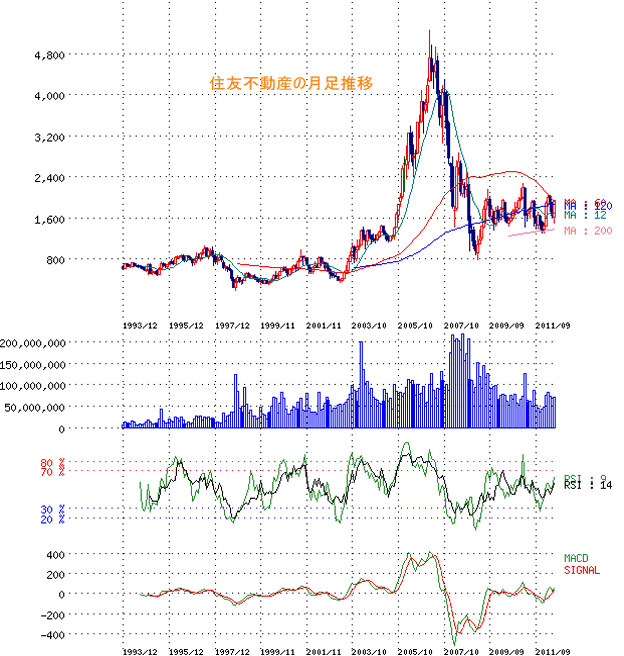
2012年06月23日
資金の回避行動
市場原理は面白いと思います。常に政策が市場のチェックを受け、市場の採点により再び政策が変化し、その変化を市場が更にチェックを繰り返します。逆に格付け会社が勝手に格付けを変えるケースがあり、この影響が市場に反映されることがあります。市場の評価を現実が試すわけですね。仮に格付け会社が格下げしても、市場がまだ大丈夫だと日本国債のように反応することもあります。
最近の事例ではインドでしょうか?
インド経済は政治の混乱が言われており経済成長のスピードが弱くなっています。この動きに拍車をかけるように、S&Pやフィッチなどが格付けを、さらに引き下げ政策を催促しているようです。基本的に新興国はサブプライム・ローンから起こった金融危機のおかげで、世界中の投機資金がリスクより安全を求めており、ドイツ、米国、日本の国債は買われますが、ブラジルレアルからもインドルピーからも資金は引き上げられています。つまり基本的にインフラ整備などが、陰りを見せ始めているわけですね。だからコマツなどは以前のような成長が見られなくなる筈です。CRBなどの商品指標も下げていますね。


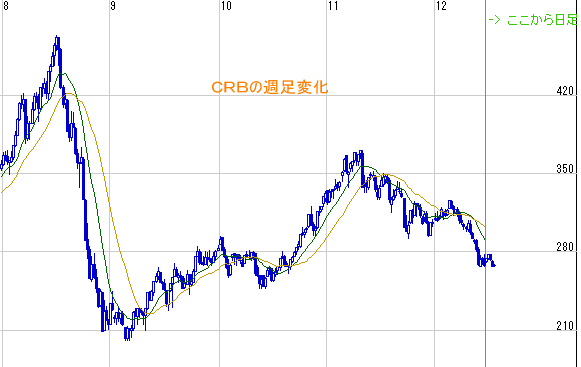
この資金引き上げの背景には金融危機の反省があり、金融デリバティブの縮小が起こっています。BIS規制やボルガー・ルールなどの規制は金融機関の行動に制約をかけます。つまり経済成長率が鈍るのです。そもそも金融工学の発展によりCDSが開発されリスクの分散化が図られ、危険の高い新興国へも資金流入が起こったのですね。この仕組みが新興国の成長を支えた側面なのでしょう。ところが、サブプライム・ローンの破たんで金融工学の穴が見つかったのです。CDSはねずみ講のように発展し、どれが元本か実態が見えなくなりました。鶏と卵の関係です。今でもJPモルガンは多額の損失を計上しましたね。先週、JPモルガンはCDSの売り持ち高を500億ドルも縮小させたと言われています。なんと5兆円ですよ。
故に世界のデフレ化は、未だに止まってないのでしょう。ブラジルレアルもインドルピーも売られるのでしょう。新興国の株価も中国をはじめ冴えませんね。この背景は先進国の投機資金の引き上げが原因の一因でしょう。BISやボルガー・ルールの存在が深く関与しているわけです。欧州の4首脳は13兆円の成長計画を発表していますが、同時に金融取引税を導入すると言います。つまり金融規制ですね。まだ資金の引き上げは続いており、予断は許されません。どこで均等化するのかどうか…。日本はかなりの時間を経て解決しました。しかしスペインなどは銀行にようやく公的資金を投入するわけで、まだ片付いていませんね。
米国のQE3は、必要なのかどうか?
今の基本は規制で萎む金融を中央銀行が補っているのです。コマツはおそらくピークを過ぎたのでしょう。シェールガスの発見は原油価格を押し下げ、イスラム圏の力を削ぐものになります。世界中は金融縮小の道を歩み景気は減速します。お金は充分にあるのですが、未来に対する希望が持てずに資金が寝ているのです。これほど世界中の強い国〈ドイツ・米国などの先進国〉の国債金利が下がり、弱小国〈イタリア・スペイン〉の国債金利は引き上げられています。二極化現象が更に広がり鮮明になるのかどうか…。中央銀行に頼ればインフレになりますね。
ユーロも危機を迎えているのに暢気なものです。11月の米国大統領選挙から、あと5月と言う現在のタイムラグを考えると、まだ株価は下がり続け政策の催促を求めるのが自然の成り行きかな?…とも考えますね。カタルがゲリラ戦の銘柄ばかりを気にするのは、このような背景があるからです。米国株がさらに下落し、政策発動を早めに求めるように感じています。このところの上げは揺り戻しかな?
でも日本株は世界中で一番恵まれている筈なのです。この環境を生かす経営を、日産はしていますが、トヨタは空洞化阻止に拘り、どうにか公約通り300万台体制を維持するようですが、その辺りが限度のようです。リカードの比較生産費説は、ある意味で現状を捉えているのでしょう。なるべく分かりやすく書いているつもりですが、ご理解頂けるでしょうか? 何も僕の見方が正解と言う訳じゃありません。僕のような意見もあると言うことに過ぎませんね。
米国のQE3と同じように、日銀は資産証券の購入枠を、更に増額するかどうか? リートやETFの話ですが…。値動きから見てそろそろ大きな転換が訪れるかもしれません。あと一歩も印象です。仮にETF枠が拡大され、流動性が更に失われると…浮動株が吸い上げられていく相場は面白いですね。今からその候補銘柄をピックアップして、次の相場の景色をイメージしておくことは非常に大切ですね。最近、米国のツイスト・オペも二つの弊害が報じられています。一つはFRBが短期の国債を売るので、安全性を求めその短期債を買うために住宅絡みの証券を売り、民間の資金供給が懸念されています。もう一つは日経だったかな?FTの記事だったか…流動性の懸念ですね。FRBが必要以上に国債を買い続けるから、価格形成が歪むと言う指摘ですね。最近の日本株の上下は、値動きが激しくなっているようにも感じています。米国の国債と同じなのかもしれません。
さて規模の大きな欧州4か国が1300億ユーロの成長計画を発表し、この程度の成長戦略で市場が納得するか…ボールは市場側に投げられました。今度は市場がこの政策に対し答えを返す順番です。EUの共同債は? 銀行同盟はどうなったの?…と市場は政策の解答が不十分だよ。…と解答を出すかどうか、再び市場の反応が問われていますね。FRBのツイスト・オペの発表で米国景気が持つかどうか…市場が更にQE3を求めるかどうか?いろんな焦点が株式市場にはある訳です。
2012年06月16日
相場の分岐点
それにしても日本らしい展開ですね。消費税の増税を巡り財務省論理が優先され、政治の主体性が感じられません。日本村論理の曖昧な妥協により合意がなされた印象です。島国の為か決定的な対立を避けお互いに歩み寄る妥協の産物ですね。米国は主義主張の戦いで選択された結果を重視して、失敗すれば、何故、失敗したのか検証され未来に情報が生かされます。日本は互いの意見を尊重し合い互いに妥協した折衷案が選択されるケースが頻繁にあります。失敗しても…誤魔化し事象を検証すると言う事を嫌いますね。責任論が出て来るからですね。
何故、民主党は無駄を省くことへの努力を弱めたのでしょう。スパコン「京」の予算配分辺りから…何となく勢いがなくなりましたね。本来、税収以上に使う方がおかしいのです。10万円の給料の人が毎月20万円も使い続ければ、誰が考えても借金が膨らみますね。ましてや1997年の名目GDPから現在は1割も減っていると言います。ところが国民の多くが国に頼る依存型社会構成なので、予算が減ることはないですね。本来なら強制的に2割程度はカットすべきでしょう。この分では、折角のチャンスである衆議院における「一票の格差」の違憲判決も生かし切れずに、曖昧な処理でお茶を濁しそうな雲行きです。
ただ消費費税の引き上げは海外投資家から見れば、一歩前進に見えるかもしれませんね。この感覚は僕だけが感じる感覚なのでしょうか? 余りにも日本人は他人に依存しすぎていると感じています。自立心が希薄と言うか…震災にしても確かに可哀そうなので、ある程度の援助は必要でしょうが、1年以上も面倒を見る必要はないでしょう。通常は半年程度で打ち切るべきでしょう。本来、人間は自ら努力して生きるべきです。やはり私は小さな政府の共和党的な考え方ですね。社会保障などの援助は、基本的に最小限にすべきかと考えています。人間、一人が食うだけなら、そんなにお金は必要ではありませんね。
またエルピーダの工場が閉鎖され、どんどん働く機会が失われていきますね。ソニーもパナソニックもどんどん国内工場を閉鎖するでしょう。既に日本と言う国の基本的な概念が間違っているのかもしれません。さて世界の中央銀行が協調して、欧州危機にあたると言います。この動きを期待して米国株は上がったのですね。しかし本当に協調するのでしょうか? スペイン国債をECBが買い入れするのでしょうか? それともドイツが妥協して共同債の発行になるのでしょうか?
貧乏人は、いつも山を張りますね。競馬で言えば3連単を狙いますね。私は今までいつも株が上がることを前提に物事を考えてきました。しかし20年以上に及ぶデフレ社会をみて時代の流れには勝てないことが身に染みてきました。相場に逆らっても努力が無駄になりますね。つらい決断でしたが株屋を辞めた一因でもあります。そんな株も1年に1回、あるいは2回程度は、買いで儲かる場面があります。そんな局面なのかもしれないとも感じていますが、貧乏人は貧乏人らしく相場の流れが確定してから動こうかと考えています。基本は金融ですね。
今回の消費増税のなかで注目されるのは名目成長率が3%で実質成長率が2%と明言していることです。目標が達成されないなら首を切るべきです。日銀総裁はその決定権を持っているわけですね。インフレを沈めるのは大変ですが、デフレを克服するのは簡単ですよ。はたしてどんな選択をするのでしょう。相場の変化点であり面白い環境ですね。
2012年06月09日
相互依存の関係
市場経済とは、実体経済を鏡である株式市場を通じて、未来の変化を読み取りそれに合わせ行動する経済なのですね。基本的に相互依存しています。共鳴と言うか共振と言うか…市場が下がれば、人間心理も弱気に傾き消費を控え実体景気は落ち込みますし、逆に市場が強気に上げ続ければ豊かな気持ちになり消費を増やしますね。米国は市場経済の国で株価が下がれば対策を打ちます。市場を通じて資金を調達するから、市場に潤沢に資金が流れないとファイナンスが出来なくなります。市場を通じて効率的な企業へ競争原理によって優先的に資金が供給される仕組みなのですね。
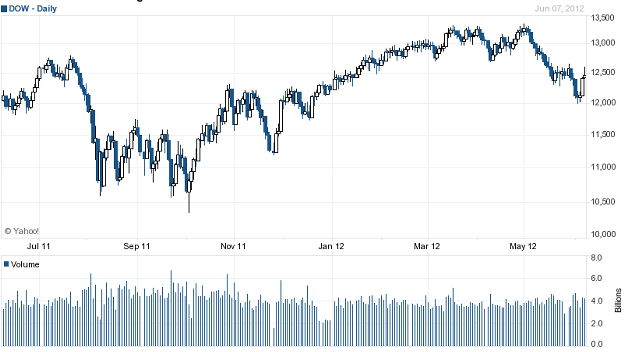
一方、日本はどちらかと言えば役人様が資金の配分を決定して、自分達が必要だと思われる事業に資金を流す計画経済の国ですね。市場原理の資金調達の場もありますが、米国に比べれば恣意的に予算が配分される仕組みです。故に無駄な公共事業なので予算が使われグローバル競争で敗退するようになりました。単純平均株価を見れば分かるように、過去のファイナンスは全て無駄な投資になっています。一昨日のNY市場の286ドル高はECBのドラギ総裁の金融緩和への前向きな発言を受けたものだと解説されています。アナウンスメントだけで、株価が大きく上がると言う事は需給バランスが改善されていると言うことを示しているとも捉えることが出来ます。つまり方向転換の時期は近いと言うサインかもしれません。
しかし市場は慎重なので、もう一度下値を割らないか、何度か再び下値を試す事は良くある現象です。悪材料がどんどん出ても株価が下がらなくなれば反転する時期だと言うことになります。今はその瀬戸際なのでしょう。まだ分かりませんよ。再び下値を確かめに行くのでしょう。しかし前回の下値を簡単に割れるようなら、まだ調整局面は長引くと見た方が良いのでしょう。逆になかなか決まらないスペインの銀行支援やギリシャのユーロ離脱などの悪材料が新たに出現しても株価が下がらなければ、下値を固めることになります。
要するに、誰も分からないのです。市場の反応を見て、そのさじ加減が市場心理を変えるのですね。下がりそうな場面でも株価が上がるとか…そのようなことが度重なれば、だんだん人間心理は強気に傾きますね。そうして消費を刺激し、その消費が株価を押し上げ、更に上がった株価を見て、また消費を増やす人が、次々に連鎖するのが成長ですね。ところが、世界景気は回復しても、アジア景気は高成長を続けても、日本株が下がり続ければ、やがて株をやる人が居なくなり、必要な資金調達ができないようになります。この負の連鎖が日本化現象ですね。
中国の利下げを受け、通常は、上海総合指数は上がるのですが、昨日は下げたようです。よくある現象です。しかし二度、三度と利下げが実行されれば、やがて市場に信頼性が戻り株高に変化します。結局、ここが下値かどうかは、もう少し市場を観察しないと分かりませんが、先の下値を割らなければ、底入れの可能性が高くなります。今はお金のある人は打診を入れ、貧乏人は注意深く市場を見守るのです。そうして変化のうねりが確実になれば自らも参戦すれば良いでしょう。
今日は株価と市場心理の話をしました。要するに相互に干渉し合いながら、実際の景気動向も市場も、育成されて行くのですね。
2012年06月02日
市場原理は振り子
今年、初めにあった景気回復傾向が失われてきましたね。もともと昨年から始まったギリシャ不安は、一度は収拾に向かったはずです。債務を棒引きにして、残りをEUが支援すると言うものでした。ギリシャも納得して緊縮に応じ、一旦は鉾が収まった話がぶり返したのです。基本的に南の国は、良く言えば「おおらか」ですが、悪く言えば「ズボラ」です。税制もどんぶり勘定のようなところがあり、政治家もいい加減です。日本も似たようなものですが、役人様が何とか押さえていました。世界を見渡せば、賄賂は横行し公正な自由競争は理想論ですね。市場経済はお金の動きにルールを加え、公正な仕組みを作ろうとする取決めですね。米国がそのルールの実権を握っています。欧州危機の再熱は中国経済への打撃を狙った細工かもしれません。米国は敵対する中国に対抗するために、日米同盟を重視し太平洋に戦力を集中させています。中国を発展させた資金源を断つ為に、BIS規制からボルガー・ルールとの流れが存在するようにも思えますね。
ここに来てフランスからイタリア、更にアイルランドと…スペインのみならず、ドイツの主張に反感を抱くグループの勢力が増えています。ドイツでもメルケル首相が率いるキリスト教民主同盟は国内選挙では議席を失っています。EUが混乱しユーロが安くなればドイツの車などは、為替メリットが生まれ相対的に有利な立場になります。逆にマツダは苦戦を強いられますね。構造改革の為に増資を実行しましたが、その努力が無駄になる為替の変動です。日本株は3月からの下落ですが米国株は5月から下げ始めました。大統領選は11月ですから、その前の下げ局面なのでしょう。効果的な演出には、下げが必要でスタート地点は低いほど、変化率がありますから政策効果を打ち出せますね。その演出をする引き金が雇用統計や失業率なのでしょう。20万人以上が必要とされるなかで、事前予想の15万5000人を大きく下回る6万9000人は、完全に失速しているように映りますね。欧州危機が叫ばれ、新興国からも資金が引き上げられているのです。金利はどんどん低下し、誰が考えても株価は下げ方向に見えます。その結果、次のステージが用意されるのでしょう。
市場原理って、悪くなれば対策が施され、必ず改善されるのですね。この景気の波、振れが大きくならないようにコントロールし、常に少しずつ改善され成長率を維持するのが目標なのですね。勿論、高い目標値(GDPの成長率)が、人々の生活改善に繋がり目標にされます。しかし先進国の成長を後押しする壁を崩すのは、従来型の物まねではなく、革新的な変革なのですね。つまり先進国が開発した技術の模倣により、安価な製品開発をして成長する時代は終わりを迎えます。アップルの富士康〈フォックスコン〉のような存在ですね。購買力平価での話ですが、新興国が先進国を抜くことは道理的におかしな現象で間もなく振り子の位置が変化します。だってティム・クックCEOは米国回帰を宣言していましたね。
時代が大きく変わる背景には新しい飛躍的な技術革新が存在します。蒸気機関の発明が鉄道開発に結びつき文明が発達しました。BRICsを代表する新興国の躍進は金融デリバティブの発展により加速した先進国の模倣なのです。日本が歩んだ道を中国などが真似をしたのです。資源価格が急騰したように新興国は購買力平価とは言うものの、先生である先進国を抜くと言うことは論理的におかしな話です。模倣では先進国を追い越す事は出来ない筈ですね。インターネットは米国の軍部からの応用ですが、情報化の進展は時代を大きく進めますね。スマフォのアプリは、様々なものが発明され無限の応用があります。私がグリーに惹かれるのは…世界を相手にビジネス展開が出来るのですね。スマフォを通じて無限の可能性があるのです。ゲームだけじゃないのです。
フェースブックは公開価格から下げていますが、やはりバブル的な時価総額が生まれた背景には、先進国の技術革新の匂いがプンプン漂うのですね。情報化は無限の収益を生むのです。私が携帯アプリに惹かれ、サイバードからインデックスに向かい失敗し、DENAだけが残りましたが、今もグリーに惹かれるのは先進国の成長の糧は情報の収益化ですね。日本人は非常に疎いですね。情報の価値観を計り知りません。例えば二つの道があります。右に行くか?左に行くか?大いに迷いますね。ところが衛星写真と言う情報があれば、正しい選択を導き出す確率は高まります。もの造りの世界では、人件費などが割高になった先進国は新興国との競争には勝てませんが、情報を駆使すれば時間を短縮できて、より効果的な選択ができるようになります。
まだ欧州危機は炎上していますが、雇用統計などで、市場経済の国、本家の米国の話に移ったと言うことは…間もなく火消し役のFRBなどが、登場する順番になりますね。もうすぐ、やって来るお正月です。別に心配する必要は、サラサラないのが市場原理ですね。