« 市場原理は振り子 | 最新の記事 | 相場の分岐点 »
相互依存の関係(2012年06月09日)
市場経済とは、実体経済を鏡である株式市場を通じて、未来の変化を読み取りそれに合わせ行動する経済なのですね。基本的に相互依存しています。共鳴と言うか共振と言うか…市場が下がれば、人間心理も弱気に傾き消費を控え実体景気は落ち込みますし、逆に市場が強気に上げ続ければ豊かな気持ちになり消費を増やしますね。米国は市場経済の国で株価が下がれば対策を打ちます。市場を通じて資金を調達するから、市場に潤沢に資金が流れないとファイナンスが出来なくなります。市場を通じて効率的な企業へ競争原理によって優先的に資金が供給される仕組みなのですね。
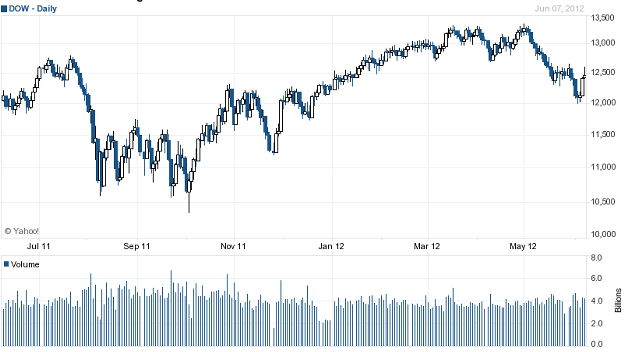
一方、日本はどちらかと言えば役人様が資金の配分を決定して、自分達が必要だと思われる事業に資金を流す計画経済の国ですね。市場原理の資金調達の場もありますが、米国に比べれば恣意的に予算が配分される仕組みです。故に無駄な公共事業なので予算が使われグローバル競争で敗退するようになりました。単純平均株価を見れば分かるように、過去のファイナンスは全て無駄な投資になっています。一昨日のNY市場の286ドル高はECBのドラギ総裁の金融緩和への前向きな発言を受けたものだと解説されています。アナウンスメントだけで、株価が大きく上がると言う事は需給バランスが改善されていると言うことを示しているとも捉えることが出来ます。つまり方向転換の時期は近いと言うサインかもしれません。
しかし市場は慎重なので、もう一度下値を割らないか、何度か再び下値を試す事は良くある現象です。悪材料がどんどん出ても株価が下がらなくなれば反転する時期だと言うことになります。今はその瀬戸際なのでしょう。まだ分かりませんよ。再び下値を確かめに行くのでしょう。しかし前回の下値を簡単に割れるようなら、まだ調整局面は長引くと見た方が良いのでしょう。逆になかなか決まらないスペインの銀行支援やギリシャのユーロ離脱などの悪材料が新たに出現しても株価が下がらなければ、下値を固めることになります。
要するに、誰も分からないのです。市場の反応を見て、そのさじ加減が市場心理を変えるのですね。下がりそうな場面でも株価が上がるとか…そのようなことが度重なれば、だんだん人間心理は強気に傾きますね。そうして消費を刺激し、その消費が株価を押し上げ、更に上がった株価を見て、また消費を増やす人が、次々に連鎖するのが成長ですね。ところが、世界景気は回復しても、アジア景気は高成長を続けても、日本株が下がり続ければ、やがて株をやる人が居なくなり、必要な資金調達ができないようになります。この負の連鎖が日本化現象ですね。
中国の利下げを受け、通常は、上海総合指数は上がるのですが、昨日は下げたようです。よくある現象です。しかし二度、三度と利下げが実行されれば、やがて市場に信頼性が戻り株高に変化します。結局、ここが下値かどうかは、もう少し市場を観察しないと分かりませんが、先の下値を割らなければ、底入れの可能性が高くなります。今はお金のある人は打診を入れ、貧乏人は注意深く市場を見守るのです。そうして変化のうねりが確実になれば自らも参戦すれば良いでしょう。
今日は株価と市場心理の話をしました。要するに相互に干渉し合いながら、実際の景気動向も市場も、育成されて行くのですね。