資金の回避行動(2012年06月23日)
市場原理は面白いと思います。常に政策が市場のチェックを受け、市場の採点により再び政策が変化し、その変化を市場が更にチェックを繰り返します。逆に格付け会社が勝手に格付けを変えるケースがあり、この影響が市場に反映されることがあります。市場の評価を現実が試すわけですね。仮に格付け会社が格下げしても、市場がまだ大丈夫だと日本国債のように反応することもあります。
最近の事例ではインドでしょうか?
インド経済は政治の混乱が言われており経済成長のスピードが弱くなっています。この動きに拍車をかけるように、S&Pやフィッチなどが格付けを、さらに引き下げ政策を催促しているようです。基本的に新興国はサブプライム・ローンから起こった金融危機のおかげで、世界中の投機資金がリスクより安全を求めており、ドイツ、米国、日本の国債は買われますが、ブラジルレアルからもインドルピーからも資金は引き上げられています。つまり基本的にインフラ整備などが、陰りを見せ始めているわけですね。だからコマツなどは以前のような成長が見られなくなる筈です。CRBなどの商品指標も下げていますね。


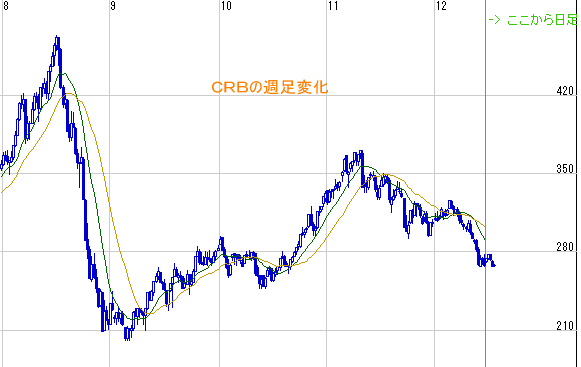
この資金引き上げの背景には金融危機の反省があり、金融デリバティブの縮小が起こっています。BIS規制やボルガー・ルールなどの規制は金融機関の行動に制約をかけます。つまり経済成長率が鈍るのです。そもそも金融工学の発展によりCDSが開発されリスクの分散化が図られ、危険の高い新興国へも資金流入が起こったのですね。この仕組みが新興国の成長を支えた側面なのでしょう。ところが、サブプライム・ローンの破たんで金融工学の穴が見つかったのです。CDSはねずみ講のように発展し、どれが元本か実態が見えなくなりました。鶏と卵の関係です。今でもJPモルガンは多額の損失を計上しましたね。先週、JPモルガンはCDSの売り持ち高を500億ドルも縮小させたと言われています。なんと5兆円ですよ。
故に世界のデフレ化は、未だに止まってないのでしょう。ブラジルレアルもインドルピーも売られるのでしょう。新興国の株価も中国をはじめ冴えませんね。この背景は先進国の投機資金の引き上げが原因の一因でしょう。BISやボルガー・ルールの存在が深く関与しているわけです。欧州の4首脳は13兆円の成長計画を発表していますが、同時に金融取引税を導入すると言います。つまり金融規制ですね。まだ資金の引き上げは続いており、予断は許されません。どこで均等化するのかどうか…。日本はかなりの時間を経て解決しました。しかしスペインなどは銀行にようやく公的資金を投入するわけで、まだ片付いていませんね。
米国のQE3は、必要なのかどうか?
今の基本は規制で萎む金融を中央銀行が補っているのです。コマツはおそらくピークを過ぎたのでしょう。シェールガスの発見は原油価格を押し下げ、イスラム圏の力を削ぐものになります。世界中は金融縮小の道を歩み景気は減速します。お金は充分にあるのですが、未来に対する希望が持てずに資金が寝ているのです。これほど世界中の強い国〈ドイツ・米国などの先進国〉の国債金利が下がり、弱小国〈イタリア・スペイン〉の国債金利は引き上げられています。二極化現象が更に広がり鮮明になるのかどうか…。中央銀行に頼ればインフレになりますね。
ユーロも危機を迎えているのに暢気なものです。11月の米国大統領選挙から、あと5月と言う現在のタイムラグを考えると、まだ株価は下がり続け政策の催促を求めるのが自然の成り行きかな?…とも考えますね。カタルがゲリラ戦の銘柄ばかりを気にするのは、このような背景があるからです。米国株がさらに下落し、政策発動を早めに求めるように感じています。このところの上げは揺り戻しかな?
でも日本株は世界中で一番恵まれている筈なのです。この環境を生かす経営を、日産はしていますが、トヨタは空洞化阻止に拘り、どうにか公約通り300万台体制を維持するようですが、その辺りが限度のようです。リカードの比較生産費説は、ある意味で現状を捉えているのでしょう。なるべく分かりやすく書いているつもりですが、ご理解頂けるでしょうか? 何も僕の見方が正解と言う訳じゃありません。僕のような意見もあると言うことに過ぎませんね。
米国のQE3と同じように、日銀は資産証券の購入枠を、更に増額するかどうか? リートやETFの話ですが…。値動きから見てそろそろ大きな転換が訪れるかもしれません。あと一歩も印象です。仮にETF枠が拡大され、流動性が更に失われると…浮動株が吸い上げられていく相場は面白いですね。今からその候補銘柄をピックアップして、次の相場の景色をイメージしておくことは非常に大切ですね。最近、米国のツイスト・オペも二つの弊害が報じられています。一つはFRBが短期の国債を売るので、安全性を求めその短期債を買うために住宅絡みの証券を売り、民間の資金供給が懸念されています。もう一つは日経だったかな?FTの記事だったか…流動性の懸念ですね。FRBが必要以上に国債を買い続けるから、価格形成が歪むと言う指摘ですね。最近の日本株の上下は、値動きが激しくなっているようにも感じています。米国の国債と同じなのかもしれません。
さて規模の大きな欧州4か国が1300億ユーロの成長計画を発表し、この程度の成長戦略で市場が納得するか…ボールは市場側に投げられました。今度は市場がこの政策に対し答えを返す順番です。EUの共同債は? 銀行同盟はどうなったの?…と市場は政策の解答が不十分だよ。…と解答を出すかどうか、再び市場の反応が問われていますね。FRBのツイスト・オペの発表で米国景気が持つかどうか…市場が更にQE3を求めるかどうか?いろんな焦点が株式市場にはある訳です。